情報通信・インターネット(16) サブカテゴリ
第40回
147年にわたって木材からゴムの長靴まで幅広い分野で事業を展開していた企業を、オリラは就任から8年も経たないうちにヨーロッパ最大の時価総額を誇る企業にした。
![ヨルマ・ヤコ・オリラ[ノキアCEO]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/4/7/240wm/img_47342145cba2398919808a411c4438979099.jpg)
第3回
前2回でソーシャル・ウェブ革命の申し子、米ザッポスの常識破りの経営手法を紹介した。今回はさらに深堀りし、顧客を虜にする同社のコミュニケーション術を分析する。

第5回
新聞社から不動産売買や求人・求職などの3行広告を根こそぎ奪いつつあるクレッグズ・リストというネット企業をご存知だろうか。米国ではすでに紙媒体から“天敵”扱いされている。

第2回
ソニーに袖にされても復調プラズマ増産する松下の強気
パイオニアのパネル生産撤退、日立製作所のリストラ、韓国LG電子の追加投資の凍結――。プラズマテレビ市場が失速するなか、首位の松下が孤軍奮闘している。

第35回
好調なデジカメ市場に、これまでにはなかったコンセプトのデジタルカメラが登場したのでご紹介しよう。ズバリ高速連写を極めたカシオ「EX-F1」だ。

週刊ダイヤモンドで人気経済小説『ハゲタカ』の著者、真山仁氏による新連載「ザ・メディア 新聞社買収」がスタートした。真山氏に作品への思いなどを語ってもらった。

第33回
過去のアメリカ大統領選について、選挙以前の時点でのニューヨーク・タイムズ記事数の推移はどうだったのか?ここでも、選挙の結果を正しく、しかも「大接戦であった」ことまで予測していたのだ。
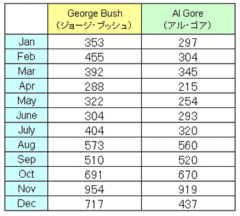
第7回
デジタル関連商品では今や不可欠となった液晶タッチパネル。しかしそのサイズゆえに、操作には「慣れ」が必要な場合もある。ストレスなく液晶タッチパネルを使う上で効果的なタッチペンの選び方を紹介する。

第39回
ほとんどの人は1つのキャリアで成功すればそれで幸せだと思う。アメリカの起業家セオドア・ニュートン・ヴェールは、そうした幸せをいくつか味わっている。
![セオドア・ニュートン・ヴェール[AT&T社長]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/240wm/img_7e09404e0c6841d8d1a5d6e7ddb9a32f9546.jpg)
第2回
昨日の常識は今日の非常識――。ウェブの進化がもたらしたのは、効率重視のデル・モデルの衰退と感動(エモーション)重視のザッポス・モデルの隆盛だった。両社の比較から明日の経営モデルを探る。

第161回
三洋電機がリチウムイオン電池で“一人勝ち”する理由
リチウムイオン電池業界が活況にわいている。完全な売り手市場でいくら作っても供給が追いつかない状態。特に好調なのがシェアトップの三洋と韓国サムスンSDIだ。
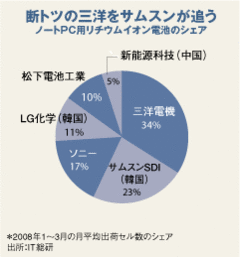
第32回
前回、ニューヨーク・タイムズの検索がアカデミー賞の結果を事前に予測していたように見えると述べた。政治的な動きについても同じような予測がありうるのか、大統領選を例にとって見てみよう。
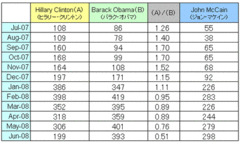
第37回
今日では頻繁に耳にする単語の一つが「コンテンツ」。池田昌史はコンテンツという言葉が世に定着していくシーンで常に最先端にいた業界の有名人だ。

第34回
ソフトバンクの「期待の星」iPhone発売が7月11日に迫ってきた。連結ベースで3兆7101億円の負債、しかも低いARPU(1人あたり通信量収入)に苦しむ同社の収益力を改善する力が本当にあるのか検証する。
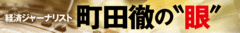
第3部
勝間和代vs小飼弾 異色対談第3回「テレビを刈れ!」
シリーズでお伝えしている知的生産術の女王・勝間和代とカリスマαブロガー・小飼弾の豪華対談。第3回は、テレビの限界について考える。

自らの技術と事業を守るために存在してきた特許が、研究開発の成果を移転するためのマネーに変貌しつつある――。好評シリーズの英語バージョンをお届けする。
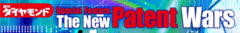
第1回
ソーシャルウェブ革命の寵児といえば、ネット通販のザッポスだ。日本では無名だが、本国アメリカではあのノードストロームを超える感動のサービスの実践者との評価すら受けている。
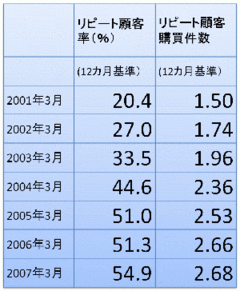
第5回
情報化に奥手なことで知られる建築・建設業界に果敢に攻め込むIT企業がある。ハンガリーのグラフィソフトだ。同社のドミニク・ガレロCEOに、急成長の秘密を聞いた。

第2部
勝間和代vs小飼弾 異色対談第2回「グーグルをなめるな!」
シリーズでお伝えしている知的生産術の女王・勝間和代とカリスマαブロガー・小飼弾の豪華対談。第2回は、強大化するグーグルの本質に迫る。

第3回
ネット小売首位の座に安住せず、ウェブサービスや電子書籍リーダーなど新事業に相次ぎ乗り出すアマゾン。グーグルやアップルの事業領域すら侵食する、その挑戦は実を結ぶのだろうか。
