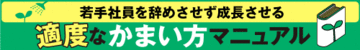間杉俊彦
第7回
目の前の仕事に追われていると、部下から話しかけられたとしても、顔をパソコンに向けたまま“生返事”していませんか? 自分の話にきちんと耳を傾けてくれないような上司を、部下は信頼することはできません。
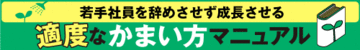
第6回
評価を必ずフィードバックすること。それが「適度なかまい方」のもっとも重要なポイントであると前回は指摘しました。しかし、フィードバックをすればいいというものではありません。フィードバックがモチベーション・アップにつながるための条件は、上司と部下のあいだに良好な関係性があることです。 逆に良好な関係性がないと、たとえ上司が部下をほめても、部下の責任感は低下するという研究結果があります。JR西日本が福知山線脱線事故を契機に取り組み始めた安全運行のための研究の一環で、「効果的なほめ方・叱り方に関する研究」がそれです。今回は、この興味深い研究結果について詳しくレポートしましょう。
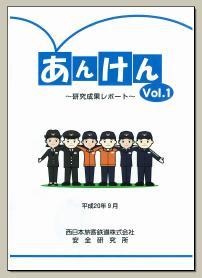
第5回
業務に不満を感じていたA君は、思い切って上司に異動を願い出たそうです。しかし、上司はA君の言い分をまったく認めませんでした。認めないばかりか、頭ごなしに否定されたと言います。 「もの凄くきつい言い方でした。『なんでお前の為に俺が他の部署と調整しなければならないのか』と言われましたね」 もちろん社員の言い分をすべて認めるわけにはいかない、というのは当然のこと。A君とて、それは承知していました。むしろ、自分が考えていることを理解してもらいたいという気持ちが強かった、と言うのです。しかしその後、A君への態度はエスカレートしたそうです。 「『お前は会社に対して不信感をもっている、そういうやつをチームに置いておくわけにはいかない。この会社に残ったとしても、もう出世はできないぞ』なんて言われました。会社が嫌いなわけではなかったけど、最後は『じゃあ辞めます』って言ってやりました」
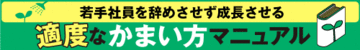
第4回
「若手の気持ちがわからない」と嘆く前に、彼(女)たちが育った時代背景を知ることも大切。そうすることで、若手がなぜ成長を急ぐのか、早々と会社に見切りをつけるのか、その理由の一端が見えてきます。
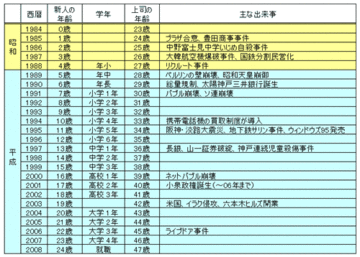
第3回
近頃の新人は、上司に電話対応について褒められたぐらいでは、喜びません。いまどきの若手が総じて成長意欲が強いことは、皆様も感じておられると思います。しかも、それぞれがイメージする成長を、短期間の間に達成したいと考えていることも特徴です。20年前に社会人になった私たちの多くが「30歳ぐらいまでには、目鼻が付けばいいや」と思っていたのとは、大きな違いがあります。バブル崩壊後のリストラ全盛期にものごころがついた彼(女)らは、会社に骨がらみで依存することのリスクをわかっています。どこに行っても通用するような仕事力を、一刻も早く身につけようという切迫感には、時代的必然性があるのでしょう。
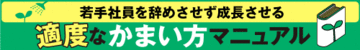
第2回
部下の昼メシ相手までいちいちチェックする上司。こうした「過干渉上司」は、若手社員にとって甚だ迷惑な存在となります。過度な干渉は、若手のモチベーションを下げるだけでなく、彼らの成長を阻害する障害でしかありません。人事担当の方には、この手の管理職に入社3年以内の若手を近づけないことをお勧めします。名のある大手企業であっても、永続性が保証できない時代。そんな時代に権力志向であることこそが時代遅れです。なにより、この手の人々には若手を一人前にする教育能力がありません。若手をツブすだけです。せいぜい、「小さい自分」を作ることにしか関心がないのです。
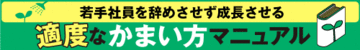
第1回
大卒新入社員の30%強が、3年以内に会社を辞めるという時代。企業にとっては採用コストが捨てガネになり、当の若手にとっては成長機会をムダにする、どちらにとっても大きな損失となります。転職ビジネスが隆盛をきわめる一方、若手は打たれ弱くなっており、早期離職しやすい状況は内も外も色濃くなっていることは間違いないでしょう。そこで問われるのは、若手とダイレクトにかかわる上司・先輩の人材マネジメント。しかし、適切なタイミングで若手社員のフォローができない「放置プレー上司」は意外と多いもの。そういう上司はある日突然、部下から退職届を突きつけられることも少なくないのです。