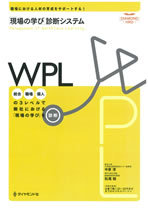間杉俊彦
第24回
若手自身の自助努力に加えて必要な「マネジャーのサポート力」と「組織の関与力」
職場で「人が育った20年前」と「育たなくなった今」は何が違うのか。このような問いかけから、本連載はスタートしました。現代の事情にフィットした育成とはどうあるべきか。今回から、数回のまとめ編に入ります。
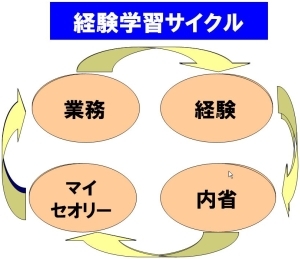
第23回
1対1の若手育成は、必然的に上下関係になりますから、お互いにかなり煮詰まりやすいことは明らかです。まずはn対nの関係が成り立つ職場の風土をいかに醸成するかを考えてみる必要がありそうです。
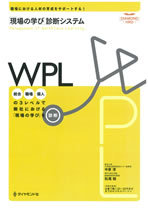
第22回
お互い逃げ場のないOJT指導‐被指導の関係を脱する
優れたOJT指導者の指導行動について、前回まで4回にわたって解説してきました。では、リーダーが個人として行動を変容させれば、OJT全体が再活性化するものでしょうか?
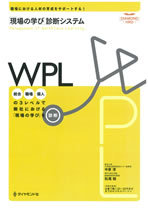
第21回
「育て上手」の上司たちの調査でわかったOJT成功のセオリー(その4)
本連載では、職場で人が育たない理由と背景について述べ、そこには構造的な要因があることを指摘してきました。では、どうすれば職場で人が育つようになるのか。今回は対策編、ソリューション編の第4回です。
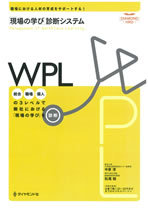
第20回
「育て上手」の上司たちの調査でわかったOJT成功のセオリー(その3)
本連載では、職場で人が育たない理由と背景について述べ、そこには構造的な要因があることを指摘してきました。では、どうすれば職場で人が育つようになるのか。今回は対策編、ソリューション編の第3回です。
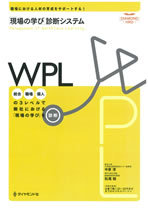
第19回
「育て上手」の上司たちの調査でわかったOJT成功のセオリー(その2)
本連載では、職場で人が育たない理由と背景について述べ、そこには構造的な要因があることを指摘してきました。では、どうすれば職場で人が育つようになるのか。今回は対策編、ソリューション編の第2回です。
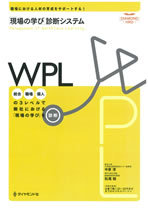
第18回
「育て上手」の上司たちの調査でわかったOJT成功のセオリー(その1)
本連載では、職場で人が育たない理由と背景について述べ、そこには構造的な要因があることを指摘してきました。では、どうすれば職場で人が育つようになるのか。今回からは対策編、ソリューション編に入ります。
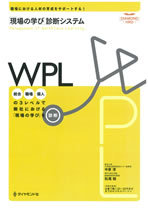
第17回
就活スタートを3年の秋から4年の夏に――商社業界の問題提起で、優秀な人材が採用できるようになるか?
「採用活動を4年生の夏以降に」という商社業界の問題提起が、企業、大学、学生に大きなインパクトを与えています。3年から4年の時期を就職活動に費やすことなくしっかり学ばせ、人材の能力アップを図ろうという考えのようです。
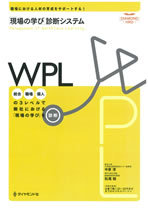
第16回
子どもをブラック企業に入れないためにも、就職難の時代こそ経験豊富な親のバックアップが有効
「わが子の就職」は、今も昔も親にとっては重要な関心事です。子どもの就職へのかかわり方として、経験に基づく正当・妥当なバックアップはあり得るし、こういう厳しい環境下こそ、そうすべきではないでしょうか。
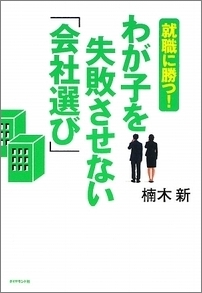
第15回
会社選びを飲み屋選び並みに安直にした「ネット就職」の功罪を考える
前回は、採用のミスマッチを減らし、学生が自分に合った企業選択をするために、大学と企業の間にある断絶を埋め、連続性を持たせる試みが必要だ、と書きました。今回も引き続き、採用について考えてみます。
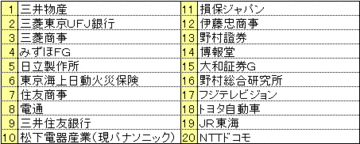
第14回
企業と学生の相互発見を阻む大学と企業の間にある見えない断絶
夏休みが終わると、大学3年生の就職活動が始動します。多くの学生が、この時期に初めて「産業企業」や「世の中」のこと、さらには「自分のキャリアビジョン」について考えることになりますが、しばしば「情報のミスマッチ」が発生します。
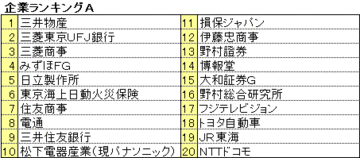
第13回
なぜ、若手の成長が組織の収益にプラスになるという視点を持てないのか
最近の調査によると、企業の経営層が認識している社内の課題は「人材育成」がもっとも多く、前年トップの「収益性向上」を上回って最大の関心事となったそうです。しかし、この調査結果には少し違和感があります。
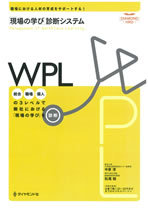
第12回
そもそも、あなたの会社ではどんな人材を求めているのですか?~多様な人材によって職場は活性化し、パフォーマンスは上がる
会社は若手に、いかなる成長を期待しているのか。また、それは「一つのモノサシ」で計られるべきものなのか。もっと言えば、「一つのモノサシ」で計り続けた結果、職場は人が育ちにくい環境になってしまったのではないでしょうか。
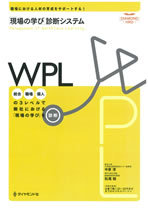
第11回
即戦力化を求める企業と成長を急ぐ若手との「すれ違い」解消法
若手を早期に一人前に育てたい企業と「早く一人前になりたい」若手社員。そこでは思いが一致しているように見えますが、現実には、なかなかしっくりとしておらず、微妙にすれ違っていることが少なくありません。
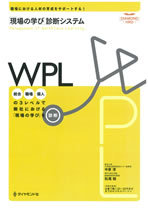
第10回
若手をつぶす?“スパルタ式”新入社員研修「厳しさ」と「理不尽さ」の曖昧な境界線
王将フードサービスの“スパルタ式”新入社員研修を批判的に取り上げた前回の記事に対して賛否両論の意見をいただきました。もちろん私自身、「厳しいこと」を否定するつもりはありません。批判したいのは「理不尽な厳しさ」です。

第9回
ネットでも話題になっている「餃子の王将」のスパルタ研修と前回の記事でもご紹介した対話型研修。両者には激しい落差がありますが、果たしてどちらが新入社員のステップとして相応しいのでしょうか?
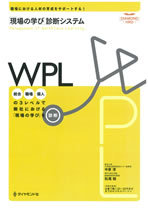
第8回
「なぜ給料をもらえるのか――」新入社員研修での問いへの手ごたえ
ある大手メーカーの新入社員研修で、「仕事への心構え」の講師を務めました。「なぜ給料をもらえるのか」というテーマについて新入社員に話し合いをしてもらったところ、教える立場であるはずの私自身に多く発見がありました。
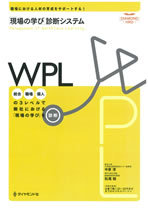
第7回
「使えないヤツを配属するな!」と言わせない新入社員研修のススメ
新入社員が入社する季節になりました。人事マンは、一方で採用試験への対応もあり、超多忙。さらに気の毒なのは、後に新人たちが配属される現場からは「ちゃんと教育して配属させろ!」クレームがついてしまうことです。
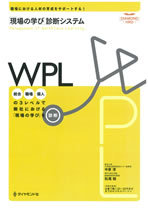
第6回
人が育たないのは“就活”のせい!?時代遅れの新卒採用の弊害
職場で人が育たなくなった背景には、就職=採用にまつわる問題点も1つとしてあるはずです。今回は、話題の『<就活>廃止論』を上梓したジョブウェブの代表である佐藤孝治さんにお話を聞きました。

第5回
なぜ過剰な期待をすると潰れてしまうひ弱な日本人が増えたのか
日本の上司が若手に「石川遼」像を求めることに対して、サンフランシスコで大学の教員をしている友人から「米国の学生ならむしろがんばるだろう」と彼は言います。その差が生まれてしまうのはなぜでしょうか。