
真壁昭夫
経済の実力低下によって、わが国が円安の負の影響を吸収することが難しくなった。悪い円安の具体例として、エネルギーや食料品への家計支出が増える一方、余暇への支出は減る。コスト増加によって業績予想を下方修正する企業も出始めた。

3月に開催された中国の「全国人民代表大会」で、2022年の実質GDP成長率目標が、「5.5%前後」に引き下げられた。過去30年程度で最低の水準だ。不動産市況の悪化、新型コロナ感染再拡大による人流・物流の寸断、およびIT先端企業への締め付け強化といった、中国経済が抱える「三重苦」に、ウクライナ危機の影響が加わり、中国経済への下押し圧力が強まっている。

欧米諸国とロシアの分断=ブロック化によって、人々は欲しいものを自由に買うことが難しくなる。供給制約で、モノの値段は上がり、コストアップで企業の効率性は低下、景気が減速する国は増える。物価が上昇すると、景気が下落しても、金融政策にできることは限られる。世界は物価上昇と同時に、景気が下落する、「スタグフレーション」に追い込まれる可能性がある。

日米欧の政府が、ロシア中央銀行の資産を凍結する制裁は、かなり大きなインパクトを持つ。ロシア主要銀行が、国際的な金融システムである国際銀行間通信協会(SWIFT)から除外されたのをきっかけに、ルーブルは急落した。今後、世界的にどんな経済・金融危機が起きるのか、あらゆる可能性を考えてみたい。当然ながら、日本人も決して他人事ではない。

キリンホールディングスが、ビール会社から医薬品・健康関連企業へ大転換を図っている。旧協和発酵(現、協和キリン)が急成長し、一時は協和キリンの時価総額が親会社のキリンHDを上回った。健康関連分野では「プラズマ乳酸菌」を用いたサプリなどを強化し、「免疫の維持」という強い消費者ニーズのあるマーケットでも存在感を高めている。一方、国内ビール事業は今後、リストラの可能性も否定できない。

ウクライナ問題が「戦争」へ発展した場合、世界経済はどうなるのか。株価や通貨、債権は暴落する一方、エネルギーや鉱山資源、穀物の価格は上昇し、世界的な物価上昇圧力が一段と高まり、各国で企業の業績が悪化するだろう。戦争が回避されたとしても、各国の制裁により、供給制約が深刻化するはずだ。例えば半導体製造に用いられる「希ガス」の一つである、「ネオン」はロシアとウクライナでその多くが生産されている。ロシアが報復措置として希ガスの輸出を制限すれば、半導体不足に拍車がかかる。

西武ホールディングス(HD)は、ホテルやゴルフ場、スキー場など31施設をシンガポールの政府系ファンドであるGICに売却する。売却額は約1500億円、売却益は約800億円となる見通し。資産売却によって身軽になる=「アセットライト」経営へ方針転換を図り、ウィズコロナ時代に生き残りをかける。

「メタ・プラットフォームズ」に社名を変えた旧フェイスブックが、有力ゲームメーカーを多額の資金でM&Aの対象とするなど、世界の有力企業がメタバース分野の取り組みを急速に強化している。米マイクロソフトは687億ドル(約7.9兆円)を投じてゲームソフト会社アクティビジョン・ブリザード(アクティビジョン)を、ソニーグループは米バンジーを36億ドル(約4100億円)で買収する。突き詰めて言えば、「こんなことができたらいい」という人々の根源的な欲求や夢を実現することが、メタバースだ。メタバースは「ほんやくコンニャク」や「どこでもドア」などが飛び出す「ドラえもんの四次元ポケット」に例えることができる。

韓国の労働市場の改善ペースが鈍い。半導体輸出などに支えられ、GDP(国内総生産)は増えているにもかかわらずだ。21年の労働参加率は62.8%で、19年の63.3%を下回った。また、21年の就業者数は前年から36万9000人増えた。ただ、増え方に問題がある。世代別では、60歳以上の就業者数が33万人増と他の世代よりも多い。本来なら、景気回復によって人々の労働意欲が向上し、若年層を中心に就業者が増加するのが望ましい。韓国の労働市場は、若年層のチャンスが少ない状況が深刻化している。

2021年の中国の出生数は、1062万人だった。1949年の建国以来、最低水準だ。人口ピラミッドは15歳未満の年少人口が減り、65歳以上の老年人口が増加する「逆三角形型」が鮮明化しつつある。共産党政権は少子化を食い止めるために「三人っ子政策」を実施しようとしているが、党の考えとは逆に、人口減少はさらに深刻化することが懸念される。

世界経済全体で物価上昇圧力が高まっている。米連邦準備制度理事会(FRB)は、「利上げ」とバランスシートの縮小による「流動性の吸収」を急ぐ考えに転じた。今後、米国を中心に金融緩和から金融正常化へとシフトすることによって金利が上昇し、世界的に金融市場が不安定化する恐れがある。

毛沢東に次ぐ中国の最高指導者としての立場を確立したい、習近平国家主席。今後のシナリオの一つとして、中国のゼロ・コロナ運営によって、半導体の需給がさらに引き締まり、米国や欧州各国、わが国による「半導体争奪戦」が激化する可能性がある。

次世代の仮想空間である「メタバース」が注目を集めている。インターネットを使いこなせる人や企業と、そうではない経済主体の差が広がる「インターネット・デバイデッド」、あるいは「デジタル格差」と呼ばれる状況が出現したように、メタバース市場に参入できる企業と、それが難しい企業の差が鮮明になる「メタバース・デバイデッド」社会が、近く到来するだろう。

カーボン・クレジットの取引が盛り上がり、既にバブルの様相を呈している。一例が航空業界だ。二酸化炭素1トン当たりのクレジット価格は、21年1月4日の80セントから11月10日には8.35ドルに上昇した。価格高騰の原因の一つは、世界で統一されたルールがないことだ。わが国は、エネルギー政策の転換と脱炭素に関する国際ルール策定に、より真剣に取り組まなければならない。

日本工作機械工業会によると、11月までの年初来の受注額は、前年同期比で内需が56.8%増、外需は84.9%増だった。東南アジアで電気自動車と半導体の直接投資が増えているのが背景だ。中国から移管した生産拠点をさらに別の国に移す企業が増加し、世界のサプライチェーンの再編が一段と加速していることは大きい。

インテルは自前で設計・開発し、微細化(ロジック半導体などの回路線幅を小さくする製造技術)を進めて最新の生産体制を整える、「垂直統合」のビジネスモデルを急ピッチで見直している。その姿勢に、わが国企業が学ぶべき点は多い。詳細は後述するが、過去の成功体験を捨て、大胆な事業運営体制の変革に挑んでいるのだ。
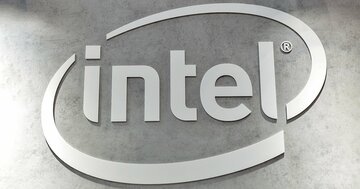
日産自動車が11月末、今後5年間で2兆円を投資し、電気自動車(EV)の開発を加速させる戦略を発表した。背景にはカルロス・ゴーン氏がトップだった時代の「負の影響」を払拭(ふっしょく)し、EV開発によって次のステージで巻き返しを図る意図があるだろう。ただ、5年で2兆円の投資規模は、十分とはいえないかもしれない。今後、日産がどう生き残りを目指すか、先行きを懸念する利害関係者が増えている。独ダイムラーによる仏ルノー株売却は、その一つだ。

11月から国内の自動車生産台数が回復し始めた。にもかかわらず、日本株の上値は重い。対照的に、米国の株価は最高値を更新し続けている。カネ余りの影響に加えて、GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)等のIT先端企業が経済運営の効率性を上げている。わが国経済は、「自動車一本足打法」を続けるか否かの分水嶺を迎えた。このまま自動車依存が続けば、わが国の地盤沈下は避けられず、国民の生活水準をも引き下げなければならない恐れが出てくる。それほど脱炭素やデジタル化への遅れは深刻だ。

トラック・バスメーカーのいすゞ自動車は、電気自動車(EV)のトラックの量産を目指している。いすゞは、航続距離の短さというEVトラックの課題を克服する技術的なブレークスルーの実現にめどをつけたようだ。それは、ハイブリッド車(HV)技術を重視し、結果としてEVシフトへの対応が遅れたわが国自動車産業の巻き返しにつながる可能性を秘めている。

習近平国家主席が「歴史決議」を採択した。まさに中国が新しい時代に足を踏み入れるとの宣言だ。新時代に向かう経済では、「共同富裕(国全体で豊かになる考え)」が重視され、民間企業への締め付けは強まることが懸念される。習氏は経済活動の一部を犠牲にしてでも、習氏を頂点とした政治体制を作ろうとしているようだ。
