上田惇生
第219回
社会的な目的を実現してよりよい社会をつくる経済はそのための手段である
経済の発展は、社会的な目的の達成を約束する限りにおいて望ましい。約束が幻想であることが明らかになれば、当然その価値は疑わしくなる。

第218回
企業家精神とは気質の問題ではなく行動の様式である
企業家精神とは、独特の特性をもつ何かである。気質とは関係ない。実際のところ、私はいろいろな気質の人たちが、企業家的な挑戦を成功させるのを見てきた。

第217回
株主の利益のみを最大化?企業の長期的な成果は短期的な成果の累積にあらず
企業の経営陣は、近頃では、利害関係者間の均衡ある利益を実現すべき者とはされていない。株主の利益のみを最大化すべき者とされるにいたってしまった。

第216回
「環境問題」は人類全体の問題であるとの共通認識なくしては効果なし
今後ますます、生態系に対する配慮、つまり危機に瀕した人類の生存環境の保護を政策に織り込むことが必要になってくる

第215回
ほとんどの企業は本当に重要な数字について知ろうとはしていない
かつては、生活水準の高さを示す数字として、エンゲル係数なるものが使われた。消費支出に占める飲食費の割合のことだった。ドラッカーは、経営環境の変化を知るには、このエンゲル係数に相当するものを見つけよと言う。

第214回
65歳定年は誤り高年齢者パワーをあなどるなかれ
96歳を迎える直前まで活躍していたドラッカーにしてみれば、65歳の定年退職が間違っていることは当然だった。
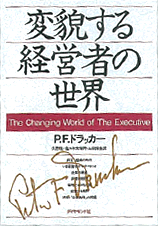
第213回
組織の全員が自ら変化を引き起こすチェンジ・エージェントたれ
「組織が生き残りかつ成功するには、チェンジ・エージェントすなわち変革の機関とならなければならない。変化をマネジメントする最善の方法が、自ら変化をつくりだすことである」

第212回
セーフティネットであらゆる者が自信を持ち自立できるようにせよ
「社会の大転換が進行中である。その結果、いたるところで社会的なミスマッチが生じている」社会的なミスマッチばかりではない。経済的なミスマッチも生じている。両者は連動している。
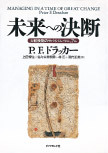
第211回
教師の生産性を上げるには学ばせるための監督よりも教えるための時間を与えよ
教わることとは、意味と理解にかかわることである。ドラッカーは、教わることと学ぶことを峻別して考えている。

第210回
顧客に対してはベストのチームで臨むべし自前主義を捨てよ
元GE会長のジャック・ウェルチは、その昔、自分がCEOに任命されたらすぐにしようと思っていたことがあった。ドラッカーに会って教えを請うことだった。

第209回
企業の経営幹部には自らの課題を超えた責任がある
今日、マネジメントの最大の社会的責任は、一般人、すなわち企業の外にあって企業について何も知らない教育ある人たちが、企業は何を行い、何を行うことができ、何を行うべきであるかを理解できるようにすることである。

第208回
やがて来る年金基金における資本形成の不足
個人にとって、年金基金へ拠出した金は貯蓄である。しかしそれは、社会にとっての資本形成ではない。移転支出にすぎない。就業者の購買力を退職者に移転させたにすぎない。
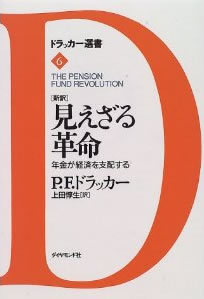
第207回
人にとって経済は目的ではなく手段である
私は、経済を支配的な領域として認めることはもちろん、独立した領域として認めることもできない。オーストリア学派の経済学者のように、経済的な領域を唯一の意味ある領域とする考えはさらに認められない
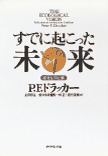
第206回
最高の力を発揮してもらい最大の貢献をしてもらうための手立てを講じているか
ドラッカー本人の求めによって、最晩年の1年半を独占インタビューし、世界各地にいる彼の教え子たちに取材したエリザベス・H・イーダスハイム博士は、ドラッカーとそのクライアントたちが求めたものは、つまるところ、人が主役の理想企業だったという。

第205回
世界は日本的な日本を必要とする
日本は、外国からの影響を自らの経験の一部とする。外国の影響のなかから自らの価値、信条、伝統、目的、関係を強化するものだけを抽出する。
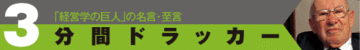
第204回
組織の中にプロフィットセンターはないすべては顧客のところにある
じつは、プロフィットセンターという言葉をつくったのはドラッカーである。あらゆる活動を事業として把握することの必要を強調するためだった。ところが、言葉は独り歩きをする。プロフィットの源泉が組織の中にあるかのごとき錯覚を持たせてしまった。

第203回
広く理解されて行動の基盤となってこそ知識と言える
学問の世界では、書かれたもの、すなわち論文を知識と定義する。それどころか、その論文の書き方までをとやかくいう。そのくせ、まるで理解不能な文章があっても平気である。

第202回
組織の正統性とは現実に世の中に貢献するとき初めて手にすることができる
「過去100年の間に、重要な社会的機能は、すべてマネジメントをもつ組織に託されるようになった」。ということは、マネジメントが致命的に重要な意味を持つ時代が来たということだった。

第201回
自由市場といっても無秩序な市場は存在しない不心得者は淘汰される
いわゆる自由市場には、どんな種類の制約も存在しないといわれてきた。政府が企業や個人の経済活動に干渉せず、市場の働きに任せる状態をレッセフェール(自由放任主義)という。仏語で「なすがままに任せよ」の意味だ。

第200回
新しい任務で成功するには過去を捨て今、何が求められているかを考える
ドラッカーはコンサルティングを60年以上も経験し、たくさんの人事を目にしてきた。ところが残念なことに、前の仕事で有能だった人の多くが実力を発揮できなくなっているという。
