上田惇生
第199回
社員流動化時代に「人が宝」をお題目にしない
あらゆる組織が、『人が宝』と言う。ところが、それを行動で示している組織はほとんどない。本気でそう考えている組織はさらにない。

第198回
自らの強み、仕事の仕方、価値観を知り最高のキャリアをつかむ
自らの強み、仕事の仕方、価値観がわかっていれば、機会、職場、仕事について、私がやりましょう、私のやり方はこうです、こういうものにすべきです、他の組織や人との関係はこうなります、これこれの期間内にこれこれのことを仕上げます、と言えるようになる。

第197回
何のために存在するのか何のために活動するのかそれを考えることが経営だ
組織は、社会、コミュニティ、個人のニーズを満たすものである。それができずして、人に命令したり、資源を使ったり、空間を占有することが許されるはずがない。

第196回
「変な客こそ、本命」予期せぬ成功がイノベーションにつながる
経営者にはビジョンがある。夢もある。技術もあれば、ノウハウもある。そして無事、新製品、新サービスを世に出す。当然買いに来てくれる人をイメージしている。そこへ想定外の客が現れる。腹が立つ。

第195回
時代の変化を日本人ならではの企業家精神で乗り切れ
人の世のものはすべて変化する。企業家とは、その変化を利用して価値あるものを生み出し、さらに変化を増幅して文明をつくっていく者のことである。

第194回
明日をつくる者としてわれわれの今日の生き方が問われている
ドラッカーは、人の幸せの基盤たる文明をつくる者は、財とサービスを創出する機関である“組織”で働く普通の人であるという。

第193回
組織変更で業績悪化は解決しない「組織は戦略に従う」
業績が悪化すると、組織のせいにして、組織をいじり出す。組織改革なるものの多くが、この手のものである。ところがさしたる知恵もないために、どこかからモデルを借りてくる。構造に取り組むには、戦略から入らなければならない。

第192回
知識を身につけ何百年かに一度の転換期を生き抜け
何百年かに一度、際立った転換が行われる。社会は歴史の境界を越える。次の新しい時代のために身繕いをする。こうして社会は、50年後あるいは60年後には、新しい社会へと生まれ変わる。

第191回
「世界のモデルたりうる日本」人の流動化を実現し人を大切にする社会
「日本は、働く人が動かないようにすることによって、歴史上類のない成功を収めた」。それが終身雇用制だった。ドラッカーは、終身雇用制のメリットとして人と人の絆を重視した。

第190回
会社オンリーで終わらせない「第二の人生」の準備
ドラッカーは、われわれが今、直面している社会を知識社会(ネクスト・ソサエティ)と呼ぶ。知識社会には、3つの特徴がある。

第189回
何によって憶えられたいかその問いかけが人生を変える
私が13歳のとき、宗教の先生が、何によって憶えられたいかねと聞いた。誰も答えられなかった。すると、今答えられると思って聞いたわけではない。でも50になっても答えられなければ、人生を無駄に過ごしたことになるよといった。

第188回
「ミッションは何か」ミッションが定まれば取るべき行動は明らかである
成果をあげることは、新入社員であろうと中堅社員、経営幹部であろうと、彼ら自身の自己実現のための前提だという。しかし知識労働者たる者は、組織において、自らをマネジメントしなければならない。

第187回
昨日を切り捨て廃棄することで新しいことを始める
あらゆる製品、あらゆるサービス、あらゆるプロセスが、常時、見直されなければならない。多少の改善ではなく、根本からの見直しが必要である。なぜなら、あらゆるものが、出来上がった途端に陳腐化を始めているからである。

第78回
必要なのは成果をあげる政府である
あらゆる機関、政策、計画、活動について、使命は何か、それは今も正しいか、価値はあるか、すでに行なっていなかったとして、今始めるかを問わなければならない。
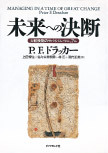
第186回
知識労働者は組織を通じて成果をあげなければならない
成果をあげることは、新入社員であろうと中堅社員、経営幹部であろうと、彼ら自身の自己実現のための前提だという。しかし知識労働者たる者は、組織において、自らをマネジメントしなければならない。

第185回
経営幹部よ外へ出よ!そして顧客を知れ!
ドラッカーは、経営幹部に対する最も有効な助言は、休暇を取ったセールスマンに代わって顧客を訪問することだという。あるいは、店先に立って客の相手をすることだという。

第184回
現代の組織は知識の専門家によるフラットな組織である
いまや先進国では、あらゆる組織が、専門家によって構成される知識組織である。そのため昔と違って、ほとんどの上司が、自分の部下の仕事を知らない。
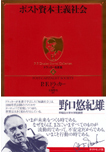
第183回
逆境のとき趣味を超えた第二の仕事が大きな意味をもつ
知識労働者には、いつになっても終わりが無い。文句は言ってもいつまでも働きたい。とはいえ、30のときには心躍った仕事も、50ともなれば退屈する。ドラッカーは、問題の解決には3つの方法があるという。

第182回
経営者にとって真摯さほど重要なものはない
好むと好まざるとにかかわらず、経営者は、共に働く人たちの範となることが求められる。さらには、社会を構成するあらゆる人たち、やがて社会の担い手となる若い人たちの範となることが求められる。

第181回
マネジメントで社員の幸せと企業の存在意義が決まる
マネジメントとは、まぎれもなく、産業社会における主導的な存在である。マネジメントが主導的な機関として出現したこと自体が、人類史上、画期的な出来事である。
