
新村直弘
中国が猛烈な勢いで進めるEVシフトの真の狙いは、脱炭素や産業競争力の強化といった表向きの理由ではなく、米国による「シーレーン封鎖」という国家存亡の危機への対抗策だった。エネルギーと食料の輸入依存という中国の致命的なアキレス腱に着目し、習近平政権が描く壮大な安全保障戦略の全貌を解き明かすとともに、中国による資源サプライチェーン支配が進む中で、日本企業がとるべき「生存戦略」として、価格リスク制御を含めた真の競争力を磨くための具体的な処方箋を提示する。

2025年の原油相場はほぼ一貫して下落傾向だった。しかし、26年の相場は上下への振れ幅が大きい展開になりそうだ。26年の原油相場の行方と注目の商品市況を展望する。
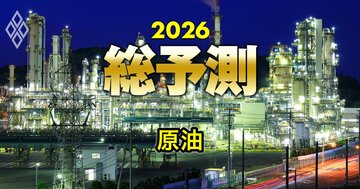
原油価格の下落が止まらない。トランプ政権の関税政策による世界経済の減速懸念に加え、OPECプラスの増産観測が強まり、市場では2026年に1バレル=50ドル割れも視野に入るとの悲観論が支配的だ。米エネルギー省も大幅な供給過剰を予測する。だが、この一方的な下落シナリオを鵜呑みにしてよいのだろうか。原油の供給過剰説の裏に潜む複数の「価格上昇リスク」として、制裁と攻撃で疲弊するロシアの供給能力低下などの見落とされがちな強材料を指摘し、中東情勢の緊迫化や2026年の米中間選挙という政治的要因も絡み市場のコンセンサスに潜む死角を読み解く。

米中対立が激化するなか、資源をめぐる静かな戦いが緊張の度を増している。とりわけ注目すべきは8月からの適用が予告された銅への50%関税だ。米国内のデータセンター需要や再産業化戦略と結びつくこの決定は、果たして現実的なのか。本稿では、トランプ政権の関税政策が同盟国との関係に与える影響とともに、タングステンをはじめとする戦略資源の地政学的重要性を検証する。加えて、米国や欧州が依存からの脱却を図るべく進める鉱山プロジェクトや、ベトナム、スペイン、オーストラリアといった同盟国における埋蔵ポテンシャルにも光を当てる。表向きの関税の裏で進行する資源戦争の最前線を追う。

トランプ政権の誕生を機に原油価格は大きく水準を切り下げ、世界の原油市場に新たな局面が訪れようとしている。米国主導の関税政策がもたらす世界経済の減速懸念に加え、OPECプラスによる増産再開や米国のシェール増産の限界が複雑に絡み合い、原油の需給構造は緩和方向へと動いている。一方で、供給過剰が拡大しつつあるにもかかわらず、価格は一方向に動かず、地政学的リスクや各国の政策スタンスによってボラティリティ(価格変動率)が今後一段と高まる兆しを見せている。需給見通しや主要国の成長率予測、米エネルギー政策の動向などから中期的な原油価格の変動幅を分析し、原油価格の変動がもたらす景気への影響、さらには価格の上下どちらにも振れうる現在の状況を踏まえ、企業や個人が取るべき対応についても掘り下げていく。

日本で電力先物オプション取引が2月3日から始まった。取引が浸透することで、消費者・生産者共に価格リスク制御のバリエーションが増えることが期待される。しかし、正しい使い方をしなければ思わぬ損失が発生することになる。

#27
金相場は2024年10月に史上最高値を更新し、米大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利した後も歴史的な高値圏で推移する。一方、原油相場は年初から4月まで上昇した後に下落基調に転じた。25年の金と原油相場の見通しと価格変動要因を分析する。

銅を含む非鉄金属である鉱物資源の価格が、急上昇している。石油に並んで鉱物資源は、私たちの経済活動を支える資源である。では、鉱物資源の価格は今後も上昇を続けるのだろうか。

原油価格が半年ぶりの高水準となり、1バレル当たり90ドルを目指す動きを見せている。今後の原油価格はどのように推移するのか。実は、米国の量的緩和がその行末を大きく左右するかもしれないのだ。

台湾総統選で対中強硬派が勝利し、台湾と中国の緊張関係が続く見通しだ。「台湾有事」は、起き得るのか。その場合、世界経済にどのようなインパクトを与えるのか。そのリスクシナリオを考えてみた。

#10
高騰する金と原油価格は、2024年どうなるのか?それを読み解くカギは、米国の金融政策と地政学リスクだ。24年の原油と金の価格を予想する。
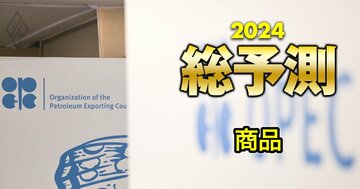
イスラム組織ハマスがイスラエルへの奇襲攻撃を仕掛けたことをきっかけに、パレスチナ情勢が緊迫化している。すでに米中対立やウクライナ危機などによって、これまでの世界秩序は大きく変わった。そうした中で、各企業は資源調達のあり方を再考する時期に来ている。

経営難に陥っていた中国の不動産大手、恒大集団が米連邦破産法第15条の適用を申請した。いよいよ中国の不動産バブルは崩壊するのか。それによる世界経済、商品市況への影響は。そのリスクシナリオを読み解く。

2023年度に入って以降、原油価格は1バレル当たり75ドル~65ドルの価格レンジで推移している。原油価格の動きは今年度後半にかけて、どのようなシナリオが考えられるのだろうか。
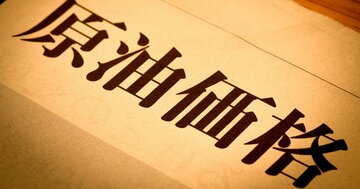
気象状況は商品市況、とりわけ穀物の価格形成に大きな影響を及ぼす。ここ3年間は、ラニーニャ現象が続いていた。このほど発表された長期予報を基に、穀物価格の行方とリスクシナリオを考えてみたい。

今年に入ってから騰勢を強めている商品が、金である。金価格の動向を探ると、従来のロジックでは説明がつかない部分がある。「有事の金」にいったい何が起こっているのか。

世界景気の動向を示す「ドクター・カッパー」こと銅価格が、年初から騰勢を強めている。果たして、2023年の銅価格はどのように推移するのか。

#9
2022年はウクライナに侵攻したロシアへの制裁強化により、原油価格が一時前年比2倍近くまで急上昇する波乱の年となった。23年の原油、金相場はどのように推移するのか。利上げや地政学的要因が商品価格に与える影響を分析し、23年の平均価格を予測する。

中国共産党大会が閉幕し、習近平政権3期目が始まった。習政権の新しい布陣や目指す政策が世界経済に及ぼす影響は大きい。習政権の動向が今後の商品市況に与えるリスクシナリオを読み解く。

人口動向は経済を予測する上で、重要な指標だ。世界経済をけん引する中国やインドは人口増加が続く一方で、日本は人口減少が止まらない。これに伴い労働力不足が懸念され、さらに資源に乏しい日本において、今後、どうエネルギーを確保するかも大きな課題だ。
