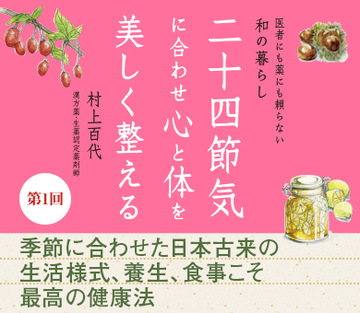村上百代
感情の起伏が激しくなる【春分】の時期を健やかに過ごすための養生法
四季を六つに分けた「二十四節気」を活用して心と体の養生法を説いた話題の本が『二十四節気に合わせ心と体を美しく整える』です。今回は同書より「春分」の健やかな過ごし方を紹介します。感情の起伏が激しくなるこの時期の養生法とは?

【あらゆる生命が蠢きだす「啓蟄:けいちつ」が今日から始まる】心と体のバランスに要注意!
春夏秋冬の四季をさらに六つに分けた「二十四節気」を活用して心と体の養生法を説いた話題の本が『二十四節気に合わせ心と体を美しく整える』です。今回は同書より「啓蟄」の健やかな過ごし方を紹介します。精神的に不安定になりがちなこの時期に心がけるべきこととは?

【2月19日は「雨水」!】春めくこの時期に、長く続く若さと健康を手にする方法とは?
四季をさらに六つに分けた「二十四節気」。この二十四節気を活用して心と体の養生法を説いた話題の本が『二十四節気に合わせ心と体を美しく整える』です。今回は同書より「雨水」の健やかな過ごし方を紹介します。春の訪れを感じ始めるこの時期に心がけるべきこととは?

「立春」をリラックス&デトックスして過ごすために効果抜群の4つの食材とは?
春夏秋冬の四季をさらに六つに分けた「二十四節気」。この二十四節気を活用して心と体の養生法を説いた話題の本が『二十四節気に合わせ心と体を美しく整える』です。今回は同書より「立春」の健やかな過ごし方を紹介します。この時期ならではの体調や食事の管理とは?

【一年の計は「立春」にあり】旧暦の新年を心豊かで健康に過ごすための養生法
春夏秋冬の四季をさらに六つに分けた「二十四節気」。この二十四節気を活用して心と体の養生法を説いた話題の本が『二十四節気に合わせ心と体を美しく整える』です。今回は同書より「立春」の健やかな過ごし方を紹介します。旧暦では新年にあたるこの時期に心がけるべきこととは?

【「大寒」到来】一年で最も寒く体調を崩しやすいこの時期に、何を食べ、どう体を整えればよいか?
春夏秋冬の四季をさらに六つに分けた「二十四節気」。この二十四節気を活用して日々を健やかに過ごすことを説いた話題の本が『二十四節気に合わせ心と体を美しく整える』です。同書より、1月20日から始まった「大寒」の過ごし方を紹介します。最も寒さが厳しいこの時期の体調管理やオススメの食べ物とは?

一年でもっとも寒い「大寒」を乗り切って、今年の運気を上げるための日々の過ごし方とは?
春夏秋冬の四季をさらに六つに分けた「二十四節気」。この二十四節気を活用して開運と健康を呼び込むことを説いた話題の本が『二十四節気に合わせ心と体を美しく整える』です。同書より、1月20日から始まる「大寒」の開運・健康法を紹介します。一年で最も寒さが厳しいこの時季を乗り切ることで、素晴らしい一年をスタートできるのです。

第5回
冬の養生法:「黒い食べ物」を多めに食べる
連載最終回は冬の六節気の養生法を紹介します。冬は貯蔵の時。種になって次の生まれ変わりを待ちます。方向は北、色は黒、ミネラルを含んだ大海原の海がこの季節を象徴します。黒い食べ物の黒豆・黒きくらげ・黒ゴマなどや精力のつくすっぽん・うなぎなどを根菜と一緒に鍋として食すと効果的です。

第4回
秋の養生法:便通をよくする発酵食品をしっかり摂る
今回は、秋の六節気の具体的な養生法を紹介します。秋は実りの時、果物がたわわに実り、今までの成熟が形になって現れます。方向は西、色は白、宝石がこの季節を象徴します。ねぎ、生姜、白い大根、レンコンといった野菜や銀杏、梨、柿などを食し、便通が整うよう発酵食品も摂りましょう。

第3回
夏の養生法:トマトや玉ねぎなどを多めに食す
今回は夏の六節気の養生法を紹介します。夏は開花の時、あらゆる草花が繁茂して成熟します。方向は南、色は赤、真っ赤な太陽がこの季節を象徴します。ゴーヤ、山菜のような苦味、赤いトマトや玉ねぎなどを多めに食しましょう。急な運動はせず、早寝早起きして太陽の光に感謝することが大切です。
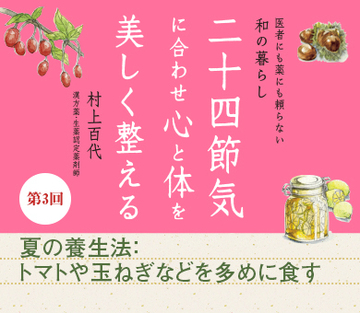
第2回
春の養生法:苦味と酸味の食材を多めに摂る
今回からは二十四節気ごとの具体的な養生法を紹介します。まずは四季の始まりの春から。春は芽吹きの時、新しく命が生まれ育ちはじめます。ふきのとうなどの苦味と酢の物やイチゴなどの果物の酸味、ニラや椎茸・緑黄色野菜などを多めに食すべきです。ストレッチと心のリフレッシュも忘れずに。
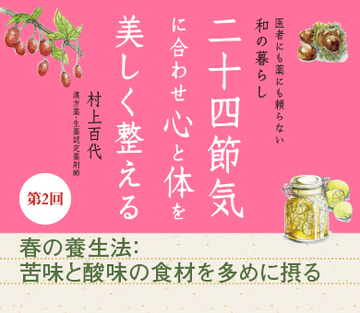
第1回
季節に合わせた日本古来の生活様式、養生、食事こそ最高の健康法
昨今、日本古来の生活様式が見直されています。四季折々の自然を感じ、味わい、昔ながらの知恵を学べば、より心豊かで健康な人生を過ごせるのです。本連載では四季をさらに細かく六つずつに分けた「二十四節気」を用い、各時季にどう体調管理をし、どんな食事を摂ればよいかを具体的に紹介します。