三原 岳
公的医療保険の重要性を理解するため、米国の医療制度の惨状を描いたマイケル・ムーア2007年製作の『Sicko』に加えて、戦前の小津映画で描かれている様子を比較します。

2018年4月から障害者雇用の制度が変わる。障害者の「法定雇用率」が0.2%引き上げられるのだ。だが、そもそも障害者に対する理解が乏しい現状がある。そこで田村正和主演の映画などを通し、障害者福祉に欠けている点を考えていく。

厚生労働省は現在、地域住民が支え合う「地域共生社会」を進めようとしている。だが、『ALWAYS三丁目の夕日』と、小津安二郎監督の映画『お早よう』を見てみると、その政策の難しさが理解できる。

4月から「介護保険制度」が変わる。高齢者の「自立」を支援するため介護予防を強化し、介護を必要としない状態に改善することを目指すという。しかし、制度創設時とは「自立」という言葉の意味が全く違っている。30年前の映画から、制度の"原点"を振り返る。

2018年4月から医療費の公定価格、「診療報酬」が変わるのを前に、現在、議論が進んでいる。政府は在宅医療の普及を推し進めているが、難しいのが現状。しかし映画『東京物語』を見れば、ヒントが隠されている。

古今東西の映画を通じて、社会保障制度の根底にある考え方や、課題などを論じていく連載「映画を見れば社会保障が丸わかり!」。第3回は、少子化対策が失敗する理由について、1955年に製作された日本映画『愛のお荷物』を通して考えていく。

2018年4月から「診療報酬」の価格が変わり、紹介状なしで大病院に行くと5000円を追加で徴収されるなど、色々な変化が起きる。だが、診療報酬の仕組みを知らなければ実感しづいらい。そこで川口浩主演の映画『満員電車』に基づいて解説する。
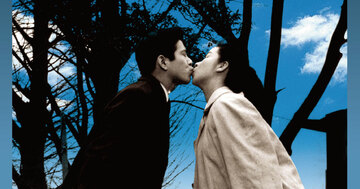
殺人という非人道的な行為を組織的かつ効率的に進める「戦争」と、病人や障害者、貧しい人の人権を保障する「福祉国家」。一見すると縁遠いようだが、実は深いつながりがあった。それは映画『ダンケルク』に表れている。
