三原 岳
『スター・ウォーズ』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』などSF映画の描写を使いつつ、社会保障制度の将来像と、その明暗を考えます。

政府は今、「働き方改革」を進めている。議論の経緯を見ると、社会保障政策ではなく、産業政策の側面が強そうだが、社会保障とは不可分だ。そこで、映画『君も出世ができる』『のんちゃんのり弁』から、政府が進める「働き方改革」の論点を考える。

高齢化の進捗によって、家族の中での老親の扱いが大きく変わっている。そこで、山田洋次監督が製作した『家族はつらいよ』シリーズのほか、2014年製作の『0.5ミリ』、1960年製作の映画『娘・妻・母』などを基に、社会保障と家族の関係を考える。

安楽死や尊厳死を巡っては、さまざまな論点があって、世界各国で議論が続いている。それは、高齢化が進む日本も例外ではない。そこで、2012年製作の『終の信託』に加えて、海外の映画を交えつつ、安楽死や尊厳死という論争的なテーマを見ていく。

児童虐待の分野は近年、さまざまな制度改革が進められている。深刻な児童虐待事件が後を絶たないため、国として対応策を迫られているからだ。しかし、その解決は決して容易ではない。

政府が進めている医療提供体制改革、特に過剰な病床の適正化や医療過疎といった問題について、戦前と戦後に製作された日本映画の『暖流』、さらに2009年製作の『ディア・ドクター』などを通じて考えてみよう。

労働衛生の目的は何なのか、そしてどんな政策が実施され、どんな影響を私の生活に与えているのか。寅さんシリーズのセリフ、吉永小百合が出演した青春映画『風と樹と空と』『いつでも夢を』などを題材に、その必要性と歴史的な変遷を考えてみる。

一見、社会保障制度と無関係に映るかもしれない「住宅政策」は、実は非常に密接に関係している。2014年公開の『東京難民』を始めとするいくつかの映画から読み解く。

なぜわれわれは公的年金に加入しているのか。それは何を意味するのか。親の年金目当てに同居する「家族」を描いていた2018年公開の『万引き家族』など4本の映画を通して年金制度の論点や課題を考える。

患者が終末期医療の方針を示す書類を事前に作ることで、その人の希望に沿った医療を受けられるようにすることを目指すという制度をご存じだろうか。1993年製作の邦画『大病人』と、2007年製作の米国映画『最高の人生の見つけ方』を通じて、終末期医療の在り方や、「ACP」と呼ばれる事前指示書の有効性を考える。
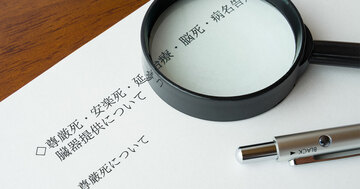
古今東西の映画を通じて、社会保障制度の根底にある考え方や、課題などを論じていく連載「映画を見れば社会保障が丸わかり!」。今回は、2つの映画から、安倍政権が掲げる「女性活躍」と社会保障制度の関係を考える。

21世紀に入って重症急性呼吸器症候群(SARS)や新型インフルエンザなどの脅威が顕在化している。そこで1995年製作の『アウトブレイク』、2009年製作の『感染列島』を通じて、大規模感染症対策の難しさを考えてみる。

1973年製作の『恍惚の人』、2006年製作の『明日の記憶』など認知症を取り扱った新旧の映画を通し、認知症ケアに対する意識の変化と、どう対応すればいいのかについて考えます。

乳幼児から見た育児のドタバタを描いた1962年製作の『私は二歳』、高校生・妻・母の三役を演じることになった女性を主人公とした1970年製作の『おさな妻』という風変わりな映画を通じて、保育所の整備など子育て支援策が遅れた理由を考える。

古今東西の映画を通じて、社会保障制度の根底にある考え方や、課題などを論じていく連載「映画を見れば社会保障が丸わかり!」。数々の映画から、日本人を取り巻く病気の構造、つまり「疾病構造の変化」を見てみましょう。

「公衆衛生」と言われる社会保障政策を考える素材として、1952年製作の『カルメン純情す』で、主演女優が一瞬見せるコスプレの格好から健康問題をひも解き、現在に繋がる論点を模索する。

「雇用と福祉の連携」を表す「ワークフェア」という言葉をご存知だろうか。その論点を探るため、1951年製作の映画『めし』、2016年製作の『わたしは、ダニエル・ブレイク』という新旧2つの映画を見ていくことにする。

ダイエットを巡る人間模様を描いた2013年製作の映画『体脂肪計タニタの社員食堂』に着目し、ここで描かれているダイエットと、国が40歳以上の人に実施している「メタボ健診」を対比させることで、メタボ健診の「笑えない」側面を明らかにします。

10回
今年4月から一定規模以上の会社に対し、精神障害者の雇用を義務付ける法令が改正された。しかし、そもそも「精神障害」の判断は難しいもの。それは、映画『彼女が目覚めるその日まで』『ツレがうつになりまして』を見ればよく分かる。

古今東西の映画を通じて、社会保障制度の根底にある考え方や、課題などを論じていく連載「映画を見れば社会保障が丸わかり!」。公的医療保険の原点を探るため、1979年製作の映画『あゝ野麦峠』を取り上げます。
