古井一匡
コロナ就活の重要キーワードは「ジョブ型雇用」と「人生100年時代」
2022年3月卒業予定(現在大学4年生など)の学生の就職活動が本格的に始まっている。ウィズコロナ時代の就活を成功させるために、学生は、目指す企業の “経営のあり方と人事戦略の方向性”を知っておく姿勢が必要だ。「働き方改革」をベースに、そのキーワードとなる「ジョブ型雇用」と「人生100年時代」について考えてみよう。

コロナ時代の就職活動は「企業の人事戦略」をスタート地点に考える
2022年3月卒業予定(現在大学4年生など)の学生の就職活動が本格的に始まった。言うまでもなく、学生にとっての就活は、企業側からみれば“人材の採用”であり、それぞれの企業の人事戦略に基づいて行われるものだ。学生は、目指す業界や企業の“ウィズコロナにおける企業経営のあり方と人事戦略の方向性”を知っておくことが就活成功のカギとなる。
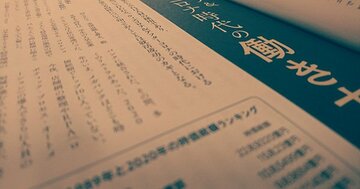
コロナで就活はどう変わっていく?学生の志向、スケジュール…
2022年3月卒業予定(2021年4月から大学4年生など)の学生の就職活動が本格的に始まっている。コロナ禍の影響で、内定出しのピーク時期が先行き不透明な状況のなか、前稿に続き、いま改めて、“就活”そのものの歴史やルールを理解し、ウィズコロナでの就職活動の“常識”がどう変わっていくのかを考えてみたい。

新卒一括採用、世界でも珍しいルールが日本で定着した理由
この3月、来年2022年3月卒業予定(現在大学3年生など)の学生の就職活動が企業側による採用情報の解禁で本格スタートとなった。採用から内定に至るおおまかなスケジュール感は昨年度から変更はないが、コロナ禍の影響で、「企業次第」という不透明さが増している。そうしたなか、いま改めて、新卒一括採用の理由といった就活の歴史やルールを理解し、ウィズコロナでの就職活動の“常識”がどう変わっていくのかを考えたい。
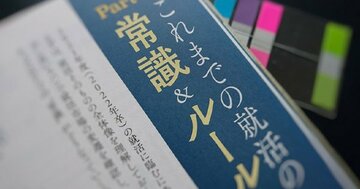
22年卒の就活戦線大予測!採用人数は絞られスケジュールは前倒しに
“コロナショック”で世界中が大混乱・大激変の一年となった2020年――その2020年度(2021年卒)の就活戦線は、一部を除いてほぼ終わりを迎えたが、2022年卒の就活市場はどうなるのか? 企業へのアンケート調査をはじめとした最新の情報をもとに、その行方を考える。

新型コロナウイルス感染症拡大で激変する採用市場(2)
“コロナショック”で世界中が大混乱・大激変の一年となった2020年――その2020年度(2021年卒)の就活戦線は、一部を除いてほぼ終わりを迎えたが、2022年卒の就活市場はどうなるのか? 本稿では、コロナ禍が21卒生の就職活動に及ぼした影響やそこに至る経緯を振り返りつつ、次年度以降に向けて改めて見えてきた“地殻変動”について考察する。

新型コロナウイルス感染症拡大で激変する採用市場(1)
“コロナショック”で世界中が大混乱・大激変の一年となった2020年――その2020年度(2021年卒)の就活戦線は、一部を除いてほぼ終わりを迎えたが、2022年卒の就活市場はどうなるのか?本稿では、コロナ禍が21卒生の就職活動に及ぼした影響やそこに至る経緯を振り返りつつ、次年度以降に向けて改めて見えてきた“地殻変動”について考察する。
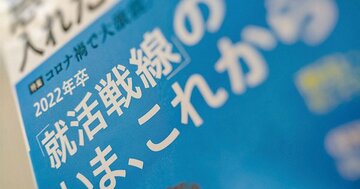
2045年の日本社会の変化を「ダイバーシティ」の観点から考える
働き方改革とともに、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容)が進む日本社会の動向を、前稿「LGBT・障がい者・外国人・要介護者……多様な人が多様に暮らす社会の現在形」でまとめたが、それでは、いまから四半世紀後=2045年の社会はどうなっているのだろう? 今回は、テクノロジーの進化がもたらす変化ではなく、あらゆる人が暮らし働く“ダイバーシティ社会”の観点から考えてみよう。
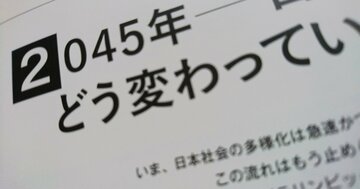
LGBT・障がい者・外国人・要介護者……多様な人が多様に暮らす社会の現在形
「働き方改革」とともに、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容)が進む日本の社会――外国人労働者のほか、高齢者、障がい者、LGBTなど、「働く人」の多様化が顕著だ。また、要介護者・がん患者などの存在も目立ってきている。それぞれの数字をもとに、日本の「ダイバーシティ&インクルージョン」の現在地を見てみよう。
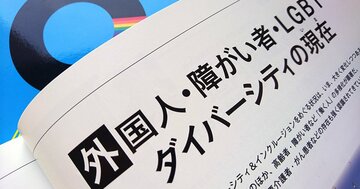
「ダイバーシティ&インクルージョン」はどう生まれたのか?その歴史を振り返る
「多様性(ダイバーシティ)」という言葉が、ツイッターなどのSNSでもすっかり目立つようになり、「ダイバーシティ」は「インクルージョン」という言葉とセットで、ビジネス用語としていまや一般的になりつつある。今後、新型コロナウイルス感染症の拡大が終息すれば、なおさらキーワードになっていくにちがいない。では、その“ダイバーシティ&インクルージョン”は、どう生まれ、日本においてはどう展開してきたのか――いま、その歴史を振り返ってみよう。
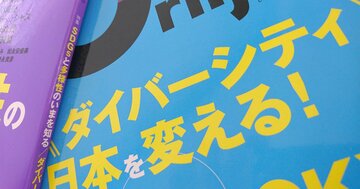
「ダイバーシティ」は、なぜSDGs実現のキーワードになるのか
前稿で、国際連合(国連)の提唱するSDGs(持続可能な開発目標)を「人類共通の課題カタログ」と称した。ダイバーシティ&インクルージョンマガジン「オリイジン」では、そのSDGsを統合するひとつの軸として「多様性(ダイバーシティ)」を提案している。多様性の視点を持つことで17のゴールそれぞれの実現が近づき、また、17のゴールがつながっていく効果も期待できるのだ。
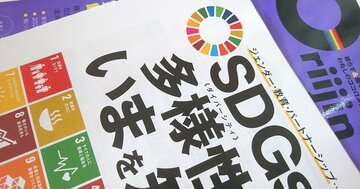
「SDGs」の誕生理由とは?今後どんな成果を実現していくのか、改めて振り返ってみる
国際連合(国連)が提唱し、2030年へ向けた世界の羅針盤として注目されるSDGs(持続可能な開発目標)。日本においても、国や自治体、民間企業が、それぞれさまざまな取り組みを進めている。これからの10年で、どのような成果を実現していくのか――その17の目標と169のターゲットを理解するだけではなく、一歩踏み込んだアプローチや角度を変えた視点が求められているいま、SDGs誕生の理由を再考してみよう。

企業も警戒する「親子就活」の実態、親の反対で内定辞退も!
近年、増えているのが子どもの就活に親が関わるケースだ。口を出し過ぎるのはマイナスだが、親として上手に子どもの就活を支援するにはどうすればいいのだろうか。実りある就活にするために親が子どもの就活にどう関わるべきかを考える。

3月に入り、今年も就職活動が実質的に解禁された。「売り手市場」と呼ばれ、学生優位に活動が進んでいると思われているが、さまざまなデータをみていくと、すべての企業で売り手市場とはとても呼べない状況だ。一体、いま就職市場では何が起きているのか。
