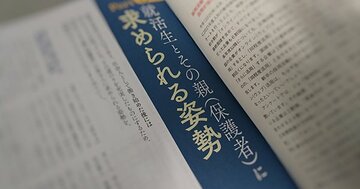古井一匡
急速に進む「人的資本経営」の流れは人事部門にとって大きなチャンス
近年、企業経営におけるキーワードとしてクローズアップされているのが「人的資本経営」だ。日本では2020年9月に公表された「人材版伊藤レポート」をきっかけに、いまや、岸田政権が掲げる経済政策「新しい資本主義」における目玉施策となっている。上場企業はもとより、すべての日本企業にとって「人的資本経営」への対応は待ったなしの状態であり、人事部門にとっては新たな“黒船”出現の感さえある。今回は、さまざまな企業の人事部門と関わりがあり、「人的資本経営」の本質を伝え続けている伊藤裕之氏(WHI総研シニアマネージャー)に、その現状と人事部門の望ましい対応について伺った。

#16
遺骨を粉状にして海にまく「海洋散骨」。日本で公式に登場したのは1991年で、2021年に厚生労働省のガイドラインが公表されたことで一定の公的な位置付けがなされた。海洋散骨のお値段と、信頼できる業者選びの6つのポイントをお届けする。

#15
私が死んだら財産はどうなるのか。おひとりさまでも避けられないのが相続だ。何もしなければ、財産が見知らぬ親族に渡ることも。法定相続人がいない場合は最終的に国のものになる。おふたりさまのうちから相続に備えておきたい。

#14
おひとりさまにとって、自分のお墓とともに気になるのが先祖のお墓だ。自分が祭祀承継者になっている場合、何の手当てもせずに亡くなれば無縁墓となりかねない。先祖の遺骨を移す「改葬」は年10万件を超える。“墓じまい”の上手なやり方のポイントは?

#13
自分が亡くなった後、医学部や歯学部における解剖学の教育・研究のために、無条件・無報酬で遺体を提供する「献体」。登録数は年間3000件程度だ。今、献体を希望するおひとりさまが増えている。いったいなぜか。

#12
一般葬から直葬や火葬式の葬儀へ、一般墓から樹木葬や合祀墓へ。おひとりさまに限らず、簡素化・小規模化の動きが止まらない。コロナ禍もその動きに拍車を掛ける。葬儀とお墓の最新事情とおひとりさまに適したお墓を探った。

“就職人気企業ランキング”の変遷で知る、学生の動きと採用活動のヒント
毎年、新聞系のメディアや人材紹介会社によって“就職人気企業ランキング”が発表されている。なかでも、株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソースの“就職人気企業ランキング”は、文系男子・理系男子は1978年から、文系女子・理系女子は1999年から続き、最も長い歴史を持っている。同社・経営企画室長の高村太朗さんへのインタビューを通して、ランキングの変遷から浮かび上がる学生の動向と採用活動のヒントをまとめてみた。

“24卒採用”に向けたインターンシップで、企業が気をつけたいこと
企業による、来年2023年3月卒業予定者(現在、主に大学4年生)の採用選考が続くなか、2024年3月卒業予定者(現在、主に大学3年生)を対象としたインターンシップが始まる。新卒採用におけるインターンシップの重要性が高まるとともに、コロナ禍によるオンライン化や短縮化など、その形式や内容も変化してきており、インターンシップの方法や運用の巧拙が各企業の採用活動全体に影響を与えかねない――多業種の人事担当者と深くかかわり、インターンシップのプロデュースをはじめ、人材採用から育成までのコンサルティングを手がけている福重敦士さん(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース HD首都圏営業局・局長)に話を聞いた。

親世代の“当たり前”はもはや通用しない?子どもの「働き方とキャリア」の新潮流
いまの親世代と子世代では、働き方やキャリアについての“当たり前”もまったく異なる。親が就活をしていた時代、日本はまだそれなりに経済成長を続けており、会社に入れば終身雇用と年功序列で、なんとかやってこられた。しかし、これからはそうはいかない。採用方式やワークスタイルの変化など、子がこれから直面する働き方とキャリアの新潮流を学ぼう。

23卒採用の選考で、経営者や人事担当者がハマりがちな落とし穴
2023年3月卒業予定者(以下、23卒生)をメインにした、企業における採用選考が進んでいる。すでに同時期の就職内定(内々定)率が前年を上回っているという民間調査のデータもあるが、これから6月頃までが採用選考のピークで、対面やオンラインによる最終面接が行われていくだろう。そうした一連の採用活動の過程で、企業の経営者や人事担当者がハマりがちな落とし穴は何か? 多業種の企業と深くかかわり、インターンシップのプロデュースをはじめ、人材採用から育成までのコンサルティングを手がけている福重敦士氏(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース HD首都圏営業局・局長)に話を聞いた。

人的資本経営のカギとなる “アルムナイ”の可能性と“辞め方改革”
近年、企業経営において急速に注目されているキーワードが「人的資本」だ。人材を「資本」としてとらえ、その価値を最大限に引き出すことで、中・長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方は「人的資本経営」と呼ばれる。この「人的資本経営」にはさまざまなアプローチがあるが、なかでもカギを握るのが「アルムナイ」との関係である。「アルムナイ」は、退職者の再入社・再雇用との関係で考えられがちだが、その効果は人事戦略全体に及ぶ。2017年からアルムナイ専用のクラウドシステムを提供している株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員の鈴木仁志さんに、「アルムナイ」の本質と可能性について話を聞いた。
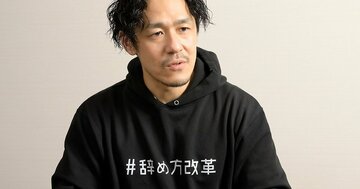
息子・娘の「いまどき就活」常識、知っている?親は今すぐ価値観をアップデート!
親世代の多くが就活に臨んだのは、バブル期から1990年代のこと。当時と現在では、就活のスタイルや内容は大きく変化している。それを知らない親は、子と一緒に就活戦線を戦うことはままならない。ここでは情報収集、インターンシップ、オンライン面接、内定獲得後の意思決定といった、特に重要な4つのポイントを解説する。

知らないと乗り遅れる「2023年卒就活カレンダー」、企業の採用活動は始まっている!
就職活動で成功するには、就活のルールを知っておく必要がある。子世代の就活ルールは、親世代と大きく異なっている。関係者が目安としている「公式ルール」はあるが、実際にはどんどん多様化、柔軟化してきており、就活生も親もその実態を知らないと大きな差がついてしまうのだ。独自情報を基に2023年卒向けの就活スケジュール(カレンダー)を整理したので、親子で参考にしてほしい。

“緊急措置”から“当たり前の選択肢”へ、ウィズコロナでのテレワークのあり方
オミクロン株の感染拡大といった気が抜けない状況とともに、「ウィズ・コロナ」が当り前になりつつある。感染の「波」の谷間では、社会も経済も少しづつ平時に戻ってはいるものの、企業の現場で継続課題になっているのが“テレワーク”の扱いだ。コロナ禍において緊急措置的にテレワークを導入したものの、状況が落ち着けば“原則出社”に戻す企業が少なくない一方、従業員の間ではテレワークの継続を望む声も強い。コロナ禍でのテレワークを巡る状況と今後への対応について、一般社団法人日本テレワーク協会の村田瑞枝事務局長に話を聞いた。
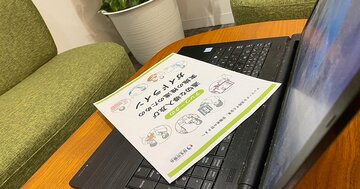
2023年卒の「就活・採用」はこうなる!データで読むコロナ禍の意外な実態
「今年も就活は厳しいかもしれない」と、身構えることなかれ。実は企業の採用意欲は、コロナ禍でも大きく落ち込んではいない。2021年卒とほぼ終了した22年卒の採用動向をにらみながら、就活トレンドを分析する。

就活の常識がコロナ禍で激変!理想の内定を勝ち取る「親子就活」の心得
アフターコロナが見え始め、新しい就活様式も定着しつつある。しかし、就活を控えた2023年卒の学生の不安や戸惑いは続いている。そんな中で意識すべきが「親子就活」だ。理想の内定を勝ち取るために、親子がタッグを組んで新しいステージに向かうための心得を説く。

「健康経営」の落とし穴は?企業が忘れてはいけない3つのポイント
コロナ禍では、多くの企業が、事業所での感染対策はじめ、リモート勤務やワクチン接種などさまざまな取り組みを通して従業員の健康確保の重要性を再認識している。今後も「従業員の健康」をどのように守るかが各方面から問われることは間違いない。しかし、企業による「従業員の健康確保」は、法律や規制への対応に終始し、医師や保健師といった専門家に任せるだけといったケースも少なくない。産業医・労働衛生コンサルタントとして就労者の現場の声に精通し、ITを活用した健康管理クラウドサービスを提供する株式会社iCAREの山田洋太氏(代表取締役CEO)に、人事戦略としての「健康経営」の課題について話を聞いた。

迫る「2025年問題」、企業は「ビジネスケアラー」にどう向き合うべきか
近年、多くの企業が人事戦略として取り組んでいるダイバーシティ(多様性)推進――これは、性別・年齢・国籍・障がいの有無…に関わらず、組織が多様な人材を受け入れてイノベーションを生み出そうとするものだ。多様性のひとつとして、今後、「2025年問題」とともにクローズアップされるのが仕事と介護の両立に取り組む「ビジネスケアラー*」の存在である。企業向けに、「従業員の両立準備状況の見える化とオンラインラーニング提供」を行うクラウドツールの展開や、シニア市場のマーケティングリサーチなどを手掛ける株式会社リクシス 代表取締役社長 CEOの佐々木裕子氏へのインタビューをもとに、企業がビジネスケアラーとどう向き合うべきかを考える。

就活で親がとるべき姿勢とは?子は「経済的サポート」が一番ありがたい
2022年3月卒業予定(現在大学4年生など)の学生の就職活動が本格化している。言うまでもなく、就活は社会の入口であり、社会人として働き始めた後には長いキャリアが待っている。就職活動にはどう臨むべきか?前稿に続き、いま、就活生とその親(保護者)に求められる姿勢を、有識者の実践的なアドバイスとともにまとめていく。
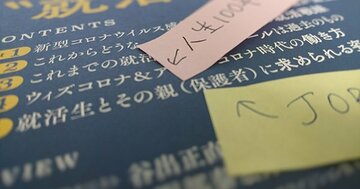
就活に親子で臨む心構えと「ワンランク上」の4つのテクニックを伝授
4月になり、2022年3月卒業予定(現在大学4年生など)の学生の就職活動が本格化している。就活は社会への入口であり、社会人として働き始めた後には長いキャリアが待っている。その道のりを充実したものにするために、就活生とその親(保護者)に求められる姿勢を、有識者の実践的なアドバイスとともにまとめていく。