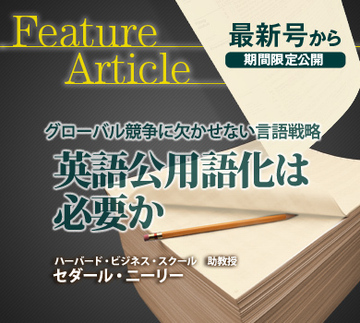幸福度の測定
データ・セットを処理して「乱暴な」指標をつくる代わりに、データの表示の仕方を改善するという方法もある。数十年間にわたって数多の開発途上国で医療活動を行ってきた医師ハンス・ロスリングは、90年代末にスウェーデンのカロリンスカ研究所で国際保健部門の教員となった。
自分が目の当たりにしてきた、発展に関する複雑な事情をいかに伝えるかに苦心した彼は、息子と義理の娘(いずれも芸術家)に協力を仰いだ。その成果が、さまざまな指標が時間の経過とともにどのように動くかをアニメーションで表示するソフトウエアである。後にこのソフトウエアはグーグルに買収された。
興奮したスポーツ・アナウンサーのようなロスリング自身のナレーションがついたこのソフトウエアは、GDPランキングのきわめて有力な代替候補となっている。何しろ、2006年のTED(テッド)のカンファレンスでのロスリングの講演は、380万回以上も閲覧されたほどである。
経済データやその他のデータは、単一の数字やランキング表として表示するよりも、さまざまな指標を示したダッシュボード形式(関連する諸指標のセット)で表示するほうがよいという考え方が、専門家や政策決定者の間で大きな話題となっている。
GDPの代替案に関するサルコジ大統領の2009年の報告書には、「ダッシュボード」という言葉が78回登場する。しかし、このダッシュボードという考え方は、一般市民の関心をとらえるには至っていない。人々の心をとらえたのは、サルコジ大統領の報告書に29回(そのほとんどが参照文献欄)しか登場しない言葉、すなわち「幸福」である。
おそらくこれは、そう驚くべきことではない。そもそも幸福は、その昔、ベンサムが最大化しようと躍起になっていたものである。50~60年代になって、心理学者と社会学者がこれを定量化できないかと再び問い始めた。一般市民の気分を測定(場合によっては決定)するものとして、当時全盛期にあった世論調査が、その試みを牽引していたのは明らかである。
経済学者のリチャード・イースタリンは幸福度の議論を自身の学説に導入し、74年の論文のなかで、国民の幸福度に関する意識調査の結果は1人当たり所得とあまり相関しないと指摘した。一般に同一国内では裕福な人のほうが貧しい人よりも幸福だが、裕福な国が貧しい国よりも幸福とは限らなかった。またある一定の水準を超えると、時間の経過とともに所得が増えても幸福度は上がらなかった。
この「イースタリンの逆説(パラドックス)」が他の経済学者から大きな注目を集めるには、かなりの時間がかかった。しかし最近、心理学的研究を重要視する行動経済学が台頭してきたことで、幸福度に関する意識調査が劇的に増えている。
このトレンドはブータンが話題になったことで拍車がかかっている。ブータンの前国王ジグミ・シンゲ・ワンチュクは、即位して間もない70年代にGNHを提唱し始めた。
この理念が世界に知られるきっかけとなったのは、『フィナンシャル・タイムズ』紙が87年に行った国王のインタビューである。
それ以降、幸福の巡礼者がブータンに長蛇の列をつくり、国王は最終的に、発展指標と世論調査データで測定できる十分な具体性を備えた指標へとGNHをつくり変えるに至った。
幸福度調査への関心の高まりは、イースタリンの逆説への批判的検討にもつながった。ペンシルバニア大学ウォートン・スクール助教授ベッツィ・スティーブンソンと同校教授ジャスティン・ウルファーズの2人の経済学者は、何十年分もの世論調査データを再検討し、この逆説に異議を唱えたことによって、2008年に大きな注目を集めた。少なくとも、裕福な国の人々は貧しい国の人々ほど幸せではないという部分は間違いだというのである。
「時間の経過とともに所得が増加しても幸せは増えない」という議論を完全に反駁するには至らなかったが、2人が集めた証拠が議論をより複雑なものしたのは確かである。
一方で、他の研究者たちは、自分の生活にどれだけ満足しているかを採点するよう求める幸福度調査と、特定の時点における感情状態に注目する調査とを区別するようになっている。前者は所得と密接に関連しているが、後者はそうではない。
心理学者で行動経済学の先駆者であるプリンストン大学教授ダニエル・カーネマンは、経済学者アラン・クルーガー(現在はバラク・オバマ大統領の下で経済諮問委員長を務める)とともに、アメリカで「国民時間計算」(national time accounts)の作成に取り組んできた。これは、労働統計局が2003年から実施している時間の利用に関する意識調査に経済価値の指標を組み合わせるもので、おそらく幸福度も含まれることになる。
この概念は独自の複雑で正確な計算を幸福度の研究に応用するが、これまでとは違って「分」の時間単位も使用する。さらに特筆すべきは、利益集団がこれに反対する明確な理由がないということである。
* * *
このようなムーブメントを推し進めようとする経済分析局の意志には限界もある。同局職員数人による2010年の論文は、GDPの概念を拡大するならば「非市場活動や市場と関連の深い活動の経済的側面に注目すべきであり(中略)そのような活動が社会の厚生に与える影響を測定しようとすべきではない」と結論づけている。
それでも彼らは「経済計算の範囲をこのように拡大するならば、既存のGDPの計算を維持し、更新し、改善するのに必要な資金を犠牲にしないことが肝要である」と警告する。
幸せはお金で買えない。しかし、幸せを測定する能力は買えるかもしれないのである。
編集部/訳
(HBR 2012年1-2月号より、DHBR 2012年5月号より)
The Economics of Well-Being
(C) 2012 Harvard Business School Publishing Corporation.