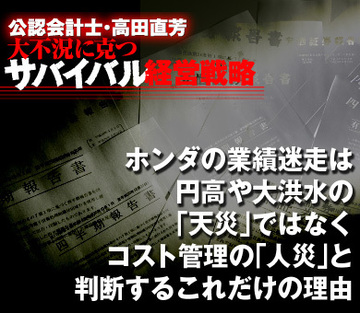ホンダが二輪、四輪の開発体制の変革に打って出た。これまで、利潤追求が優先される本社からの独立性を保ってきた研究開発部門のメンバーを製作所に配置したのだ。研究所と製作所の融合、二輪と四輪の融合──、組織間の壁を取り払い、総力戦でグローバル競争に臨む体制を構築しようとしている。創業者たちの聖域を侵してまで実施した改革に勝算はあるのか。
(『週刊ダイヤモンド』編集部 浅島亮子)
4月1日、ホンダの軽自動車を生産している鈴鹿製作所(三重県)の敷地内で、ある組織が産声を上げた。本田技術研究所四輪R&Dセンター“鈴鹿分室”──。四輪の研究開発拠点、四輪R&Dセンターは栃木県芳賀町にあり、その一部の設計開発機能を生産現場の鈴鹿製作所へ移管させたのだ。研究所の技術者、部品のグローバル調達を行う購買本部の要員など合わせて99人が栃木から鈴鹿へと転勤になった。
歴史的に、ホンダは研究開発を担う本田技術研究所を本社から分離・独立させた特異な組織形態を取ってきた。世界を見渡しても、研究所を別組織にしている自動車メーカーはホンダだけだ。狙いは、技術者が、目先の利潤を追求する販売・生産部門に惑わされることなく、自由で長期的展望に立った研究開発に没頭できるところにある(コラム参照)。
 本田宗一郎(左)以上に、藤澤武夫が研究所の独立に執念を燃やした
本田宗一郎(左)以上に、藤澤武夫が研究所の独立に執念を燃やした
労組、幹部の反対を押し切って
研究所独立に動いた藤澤武夫
ホンダが研究開発部門を本社から分離させて、株式会社 本田技術研究所を設立したのは1960年のこと。「伝わるところによれば、研究所独立への思いは、本田宗一郎さんよりも、藤澤武夫さんのほうが強かった」(山本芳春・本田技術研究所社長)とされている。
労働組合や経営幹部による猛反対に遭い、藤澤は社内のコンセンサスを得られないまま、強引に押し切った。初代社長には本田宗一郎を据えた。
常々、藤澤は「技術のわからない人では、本田宗一郎の思想を受け継ぐことはできない。独立性を保った研究所は、宗一郎が去った後のホンダの将来をにらんでつくったものだ」と発言していた。
本田技研工業から研究所へ支払われる委託研究費は、当初は売上高の2.5%(16億円)からスタートしたが、順次引き上げられて、現在は5%となった。2012年3月期のホンダの売上高予想は7.8兆円なので、委託研究費は3900億円となる計算だが、近年の売上高落ち込みを考慮して、年間約5000億円程度が支払われているもようだ。
もっとも、潤沢な研究開発資金があるからといって、ホンダの技術陣が安穏としていられるわけではない。研究所独立の目的は、利潤追求の本社に惑わされることなく、長期持続的な研究開発にいそしめるよう、技術陣の環境を整えることにある。例えば博士論文ばかり執筆しているような、象牙の塔にこもった技術者育成を目指したものではない。本田技研と研究所の間には、健全な緊張関係が存在している。