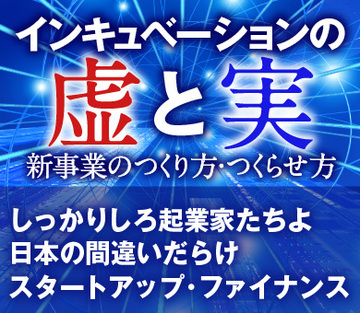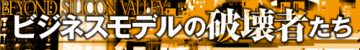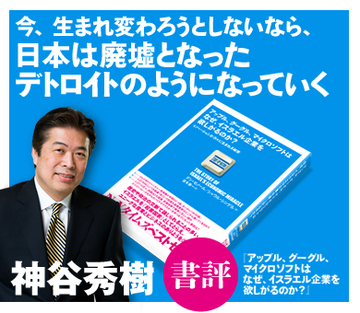何を育てるか――、それが問題だ
スタートアップのテーマ設定
千葉県柏の葉キャンパスで先月開催の「アジア・アントレプレナーシップ・アワード2012」で18社が競ったが、決勝に残った6社は海外企業ばかりで、開催国の日本のスタートアップは全て予選落ちした。審査員の一人は日本の候補について、「ビジネスとしての魅力に欠ける」とため息をつく。
500 Startups代表のデイブ・マクルーアは、ある日本のスタートアップについて、「この起業家は好きだし、いいと思うが、テーマがよくないから投資できない」と言う。
スタートアップを育成するとき、「何を育てるか」が常に問われる。テーマ設定はスタートアップの出発点であり重大問題だ。育てる対象が誤っていれば、どれだけエネルギーや金をつぎこんでも空振りに終わる。また、こんなにいいチームなのに、どうしてこのテーマなのか、と戸惑うこともある。
だからと言って、月並みなテーマでもよくない。米国のあるベンチャー・キャピタルでは、投資委員会で全員がOKを出した案件と全員がNOを出した案件には投資しないという。全員NOだと「そこで終わり」というのは当然だが、誰もがOKするようなテーマはありふれた無難なもので魅力に欠けるし、同じようなことを考える人が多いから競争も厳しくなるゆえ、却下するのだという。
筆者も、「これはちょっと」と思うテーマを目にすることは意外と多い。それは、独創的過ぎて分からないというよりは、ニーズが乏しいとか荒唐無稽、今まで似たようなものがいくつもあった、といったテーマ設定における基本的な問題が大きい。恋は盲目と言うが、起業家は自分の事業案にのめり込んで視野狭窄になっていることが多い。論理と心理の両方が、テーマ設定のカギとなるのだ。
今回は、出発点だが難物であるスタートアップのテーマ設定について議論したい。
ユニークなテーマを追求する
米国スタートアップの多様性
主な米国スーパーエンジェルの投資先が取り組む事業テーマについて分類したデータがある(NetService Ventures Group調べ、293社)。米国の首位は、広告(Advertisement)分野と並んで、ユニークで分類できないもの(One of a kind)だ。そして、全般的にみると、ある程度は集中しているが、ロング・テール的に多様だ。日本では少ない家電(CE: Consumer Electronics)が8位につけているなど、腰が引けそうな分野にも挑んでいる。