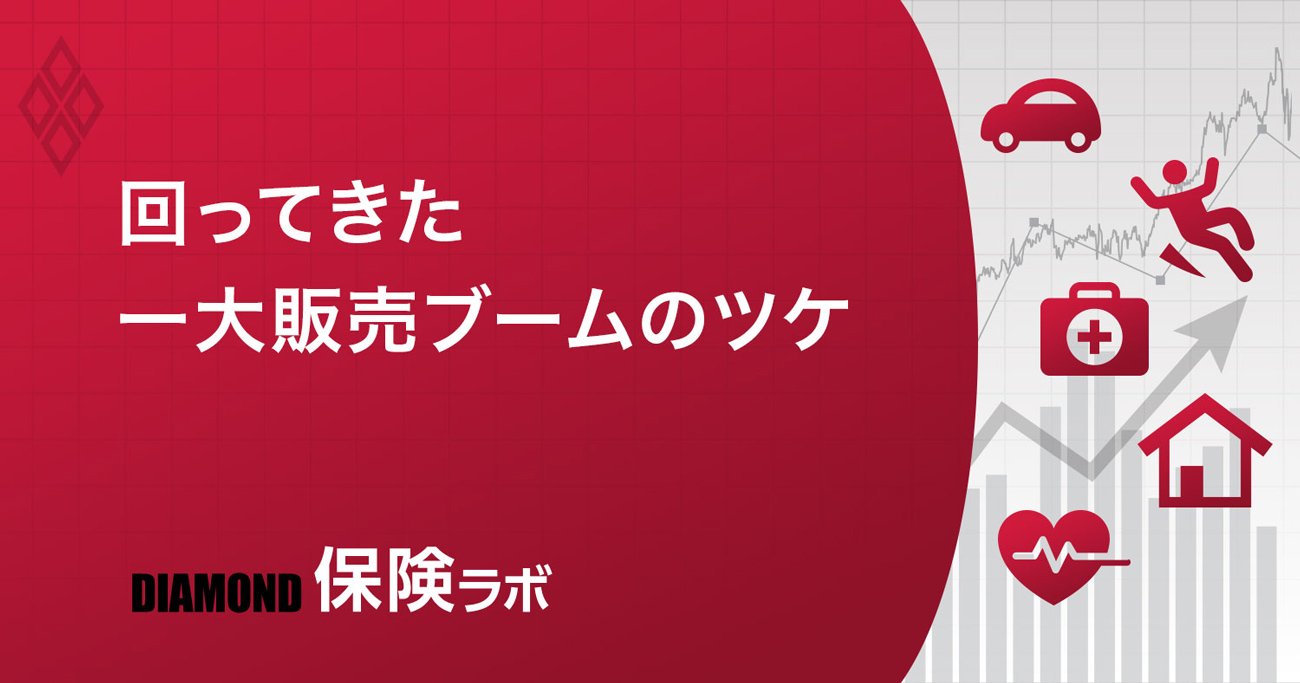
コロナ禍の大波が、生命保険各社の「節税保険」にも押し寄せている。一大ブームによって販売が過熱したことのツケが回ってきたかのように、足元で解約件数が膨らみ始めているのだ。保険営業の偽らざる実情を探った。(ダイヤモンド編集部 中村正毅)
消え失せた節税効果
「イタチごっこは終わりにしたい」
昨年2月、国税庁が生命保険各社にそう宣言し、息の根をほぼ止められることになった「節税保険(法人定期、経営者保険)」。
多額の手数料を得ていた保険代理店や営業職員は、大きく肩を落とすことになったが、その一方で既契約については不問とすることが決まったときには、至る所で安堵の声が漏れた。
節税効果が激減する新たな規制を、既契約についても遡及適用することになれば、解約が殺到し現場が大混乱することは必至だったからだ。
契約から1年未満の解約であれば、ペナルティーとして受け取った手数料を保険会社に返すことにもなるため、募集人にとっては死活問題になりかねなかったといえる。
 日本生命保険が「プラチナフェニックス」の愛称で、全額損金算入が可能な商品を開発したことで、節税保険市場に一気に火が付いた
日本生命保険が「プラチナフェニックス」の愛称で、全額損金算入が可能な商品を開発したことで、節税保険市場に一気に火が付いた
最悪の事態は辛うじて避けられたことで、後は既契約を粛々と管理していくだけのはずだったが、そこにコロナ禍が起きてしまった。
そもそも節税保険は、契約者の中小企業が黒字であることが大前提の商品だ。営業自粛などによって黒字額が大きく目減りしたり、赤字に陥ったりしてしまっては、保険料を損金算入することによる節税効果がほとんど意味をなさなくなる。
節税効果を期待して加入した中小企業にとっては、保険料を今後払い続ける意味がほぼなくなるだけでなく、家賃などの固定費を支払うために節税保険を解約し、その返戻金を充てたいという意向が強く働くことになる。
そのため、避けられたはずだった解約殺到という最悪の事態が、今まさに現実味を帯びてきているわけだ。







