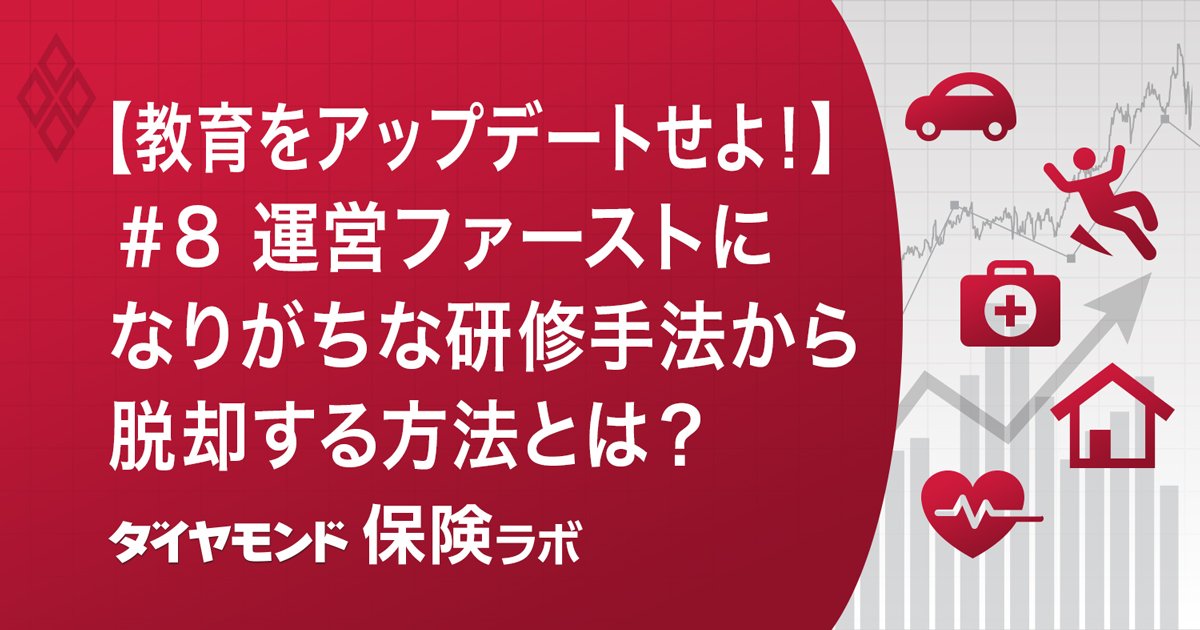
社会環境の急激な変化に対応するためにリカレント教育の必要性が高まっている。ただ、保険業界も例外ではなく、同じコンテンツの焼き直しが多く、他業界の経験者からは生ぬるい、古めかしいと感じる人も少なくない。アフターコロナを経て、保険会社は魅力的な教育体制やコンテンツを提供していく責任がある。そこで、対面とオンラインのハイブリッド型研修の効果的な運営方法の秘訣について伝授しよう。(オリックス生命保険 営業教育部 シニアエキスパートトレーナー 中楚誠二郎)
保守的で過去を踏襲しがち
研修の多くは「運営ファースト」
通勤電車の乗り方を教える研修!?
今年も4月の通勤電車には新入社員と思われる方が多く乗車してくる。スーツや靴を見れば一目で分かるが、決定的に違うのは動き・流れのぎこちなさである。さすがに面倒見の良い昨今の大学であっても、通勤電車の乗り方まで教えることはないだろう。しかし心配はいらない。2週間もたつとコツを習得してベテラン会社員と同じ流れを作ることができるものだ。
この時期は新入社員向けの研修を開催している企業も多い。主に人事部や教育部が担うが、3~4年ごとに人事異動のある保険会社では保守的な研修メニューになりがちであり、過去を踏襲する傾向が強い。中には30年前のコンテンツを使い回しているケースさえある。保険業界を取り巻く環境やマーケットはもちろん、保険募集に関する法令等も日々変化が激しいにもかかわらず、研修だけが時代に取り残されたままなのだ。
結果として受講者の身に付けさせることよりも、自分たちができることを優先してメニューを並べてしまう。運営側には現場からの注文も入ってくるが、中には「新卒社員には電車の乗り方を教えてあげるべき」といったあさっての方向を向いたメニューが追加させることさえあるのだ。まさに、運営ファーストと言わざるを得ない。
民主化が進んだ昨今の企業では、否定ができない意見は賛同を得やすい。電車の乗り方は極端であるとしても、教わることよりも慣れることの方が適切である事柄までを研修メニューに盛り込んではいないか?メニューを過剰に追加すると、キャパオーバーとなり十分な習得につながらない。
知識の習得も同様である。1年後の達成レベルを10と設定したメニューがあるとする。研修期間を2カ月とした場合、研修期間でレベル8を達成してほしいというオーダーには応えられない。時間の制約がある研修では実際には3程度が限界であろう。さらには受講者の能力も異なるため、同じ時間をかけても習得度には当然差が開く。詳しくは後述するが、この格差を埋めるには対面での研修ではなく、動画形式を活用することが有効だ。
今回は研修で解決“できること”と“できないこと”について、これまで21年間にわたり経験した具体的な教育業務を盛り込みながらお伝えしたい。まずは、現在多く導入されているハイブリッド型研修から見ていこう。







