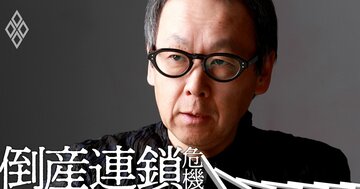Photo by Yoko Akiyoshi
Photo by Yoko Akiyoshi
新型コロナウイルス感染症によるショックは、あらゆる企業を襲った。業種によって起こった現象はさまざま。だが、生き残る企業がやっていたことは明確に「たったひとつ」だという。特集『外資コンサル総力解明 7業界の生存戦略』(全12回)の#1では、ボストン・コンサルティング・グループの杉田浩章日本共同代表と、早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授が、生き残る企業の条件を徹底激論した。(聞き手・構成 ダイヤモンド編集部副編集長 杉本りうこ)
中期計画という
企業を縛る謎の時間軸
――経済活動が再開しましたが、消費も生産も、コロナ以前の状況には遠く及びません。この中で経営者は今、どんなことを考えているのでしょうか。
杉田 多くの経営者が今共通して考えているのは、「経営の時間軸をどうマネージするのか」です。時間軸には2種類あって、一つは1~2年という短いもの。今の厳しい状況が仮に1~2年続いたとしても、利益を出せる体質にする。それには相当短期間で抜本的に事業や組織を変革しなければならない。もう一つは長い時間軸です。ニューノーマルと呼ばれるような社会と産業の長期的な変化の中で、成長領域をどこに見いだし、そこにどのように投資し、自社の事業ポートフォリオをどう変えていくのか。
この二つの時間軸の中で「やめること」「変えること」「加速すること」の三つを考えなければなりません。この三つは平時から重要でしたが、コロナ後の今は、これまでよりはるかに短期間でやりきる必要がある。スピード感が全く変わってきています。
入山 時間軸が重要というのは、僕も完全に同じ意見です。経営にとって重要なのは長期と短期で、長期に進むべき方向を見据えつつ足元の1年をガンガンやりきることが大事です。しかし日本企業の多くはどうしても、中期経営計画の3年間という謎の時間軸に縛られてきました。
しかしコロナによって意識が大きく変わった経営者が出てきた。これからいい経営、優れた経営者とそうじゃない企業や経営者の差が明確になりそうです。大きく三つに分けると、いい経営というのは、平時からキャッシュがあるので危機時の耐性もあり、リモートワークのような変革もすぐ起こせる。次に、そこまで備えはなかったものの、コロナを機にがらっと変わろうという企業。最後はいまだにぼんやりしている企業です。
僕は自動車のサプライヤーと接点が多いのですが、完成車メーカーがサプライヤーに対してどうアクションを起こしたかは、メーカーの間で歴然と差がつきました。手元のキャッシュを使ってサプライヤーをしっかり支えようという企業と、自社の工場の稼働率をどうするかしか考えられない企業の差です。自動車のサプライチェーンではサプライヤーが破綻したらアウトなのですが、そこまで考え抜いていない。そして残念なことに、日本の産業界のサイレントマジョリティーは「そこまで考えていない」企業だと思います。
杉田 確かにいい経営とそうじゃない経営は今、明確にくっきりと分かれています。そしてその理由は、実ははっきりしています。