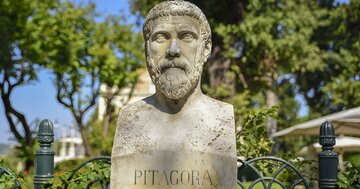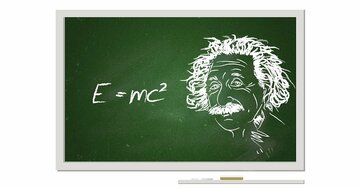「偽物」と呼ばれた数
数学の入り口で、中学1年生の春に習う負の数も、人類が発明した「新しい数」の1つである。負の数は0よりも小さい数のことで、遅くとも2世紀までに書かれた中国の数学書や7世紀の前半に書かれたインドの数学書の中には、負の数の演算に関する記載が見つかっている。
特にインドでは、7世紀の間に商人たちも、「10万円の借金」を「マイナス10万円の利益」のように表すようになり、負の数は広く使われていた。
一方、ヨーロッパの数学者たちが負の数を受け入れるようになるのは、17世紀以降のことだ。「我思う、ゆえに我あり」で有名なデカルト(1596~1650)は、方程式から得られる負の解を「偽物の解」と呼んでいた。
その後18世紀に入っても、多くの数学者にとって負の数はすんなり理解できるものではなかったようである。
「人が息をするように、鳥が空を飛ぶように計算する」と言われた天才レオンハルト・オイラー(1707~1783)ですら、「1/xの計算において、xを(正の方向から)0に向けて小さくすればするほど、1/xの値は限りなく大きくなる。『負の数』は『0より小さい数』なのだから、xが負の値になるとき、1/xの値は無限大よりさらに大きくなるはずだ」と「誤解」していたことが知られている。
マイナス3個のパンを想像できますか?
なぜ、西欧の数学者たちは負の数をまともな数として取り入れることに強い抵抗を示したり、負の数が関連する計算を誤解したりしたのだろうか?
それは負の数が直観的にはイメージしづらい数だからだ。言わずもがな、目の前に「マイナス3個のパン」を示すことはできない。イメージできないものを受け入れることは難しい。
でも、負の数を導入すれば、反対の意味の事柄を1つの概念の中で捉えることができる。たとえばある月に300万円の利益と100万円の損失があったとしよう。負の数を使うことが許されないと、利益と損失という2つの概念を考えなくてはならないので、月ごとに損益が逆転するような場合には計算が煩雑になってしまう。
しかし、100万円の損失を「マイナス100万円の利益」と表せるのであれば、損益分岐点を原点とする1本の数直線の中で売上や損益が議論できる。このように、正反対の概念を1つの概念の中で考えられるのは負の数を使う大きな利点である。
負の数が登場したことによって、「0」が数直線上の端の点ではなく、中央の点になったことにも大きな意味がある。これにより、「0」は単に無(nothing)というだけでなく、正の数と負の数が同じだけ存在している状態、すなわち均衡(balance)を表しているとも考えられるようになった。
(本原稿は『とてつもない数学』からの抜粋です)