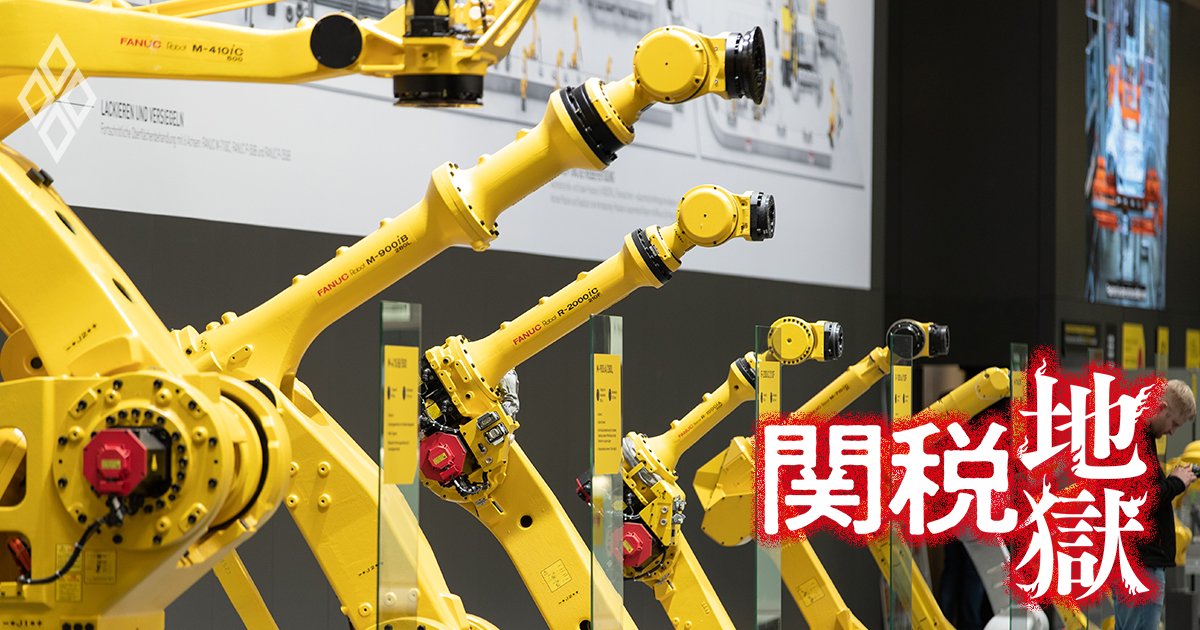去る3月19日、米・アラスカ州アンカレジで、米中外交トップによる協議が行われた。米中の価値観や国家観が激しくぶつかり合ったことは既報のとおりだが、中国国民は留飲を下げる思いでこれを受け止めた。新華社など中国メディアは二つの辛丑(かのとうし)の年を比較し、「近代以来苦難に耐えてきたが、中国は偉大な民族復興の実現の光明を迎えた」と伝えている。一体どういうことだろうか。(ジャーナリスト 姫田小夏)
 義和団の乱、北京に入城した連合軍のパレードを描いたもの(Photo:DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA/gettyimages)
義和団の乱、北京に入城した連合軍のパレードを描いたもの(Photo:DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA/gettyimages)
120年前の中国は弱体化しきっていた
2021年は、「辛丑」という、中国にとっては忘れ難い屈辱的な干支にあたる。
120年前の「辛丑」は、1901年。当時は清朝の時代だった。この年、清朝は、その前年に起きた「義和団事件」と列強8カ国(英、米、仏、露、墺、独、伊、日)に対する宣戦布告の責任を負うべく、「辛丑(しんちゅう)条約」を押し付けられた。日本では「北京議定書」で知られるが、清朝は多額の賠償金の支払いを余儀なくされ、列強による半植民地化がさらに進んだ。
この120年前の状況と、2021年3月の米中外交トップの協議はどんな共通点があり、どうつながるのか。現代に通じる欧米と中国の対立の本質が透けて見える映画があるので紹介したい。
米国の映画の巨匠、ニコラス・レイ監督は、「義和団事件」をテーマに「北京の55日」(1963年)を製作した。「義和団」とは、「扶清滅洋(清を扶=たす=け、洋を滅す)」というスローガンを掲げて排外運動を展開した清朝の宗教的民間秘密結社である。婦女子を除けば数百人の列強連合軍と、数の上では圧倒的に有利な義和団・清朝との55日間に及ぶ戦いを描いた作品である。
19世紀末期、清朝の首都・北京の外国人居留地には列強諸国の外交官や家族、牧師などの「洋人」が居留していたが、彼らは“無敵のカンフー”を身に付けた義和団の脅威に日々おののいていた。歴史と文化に高いプライドを持つ清朝に対して、列強諸国がタッグを組んで挑んでいくその構図は、まさに現代の中国包囲網を彷彿(ほうふつ)とさせる。