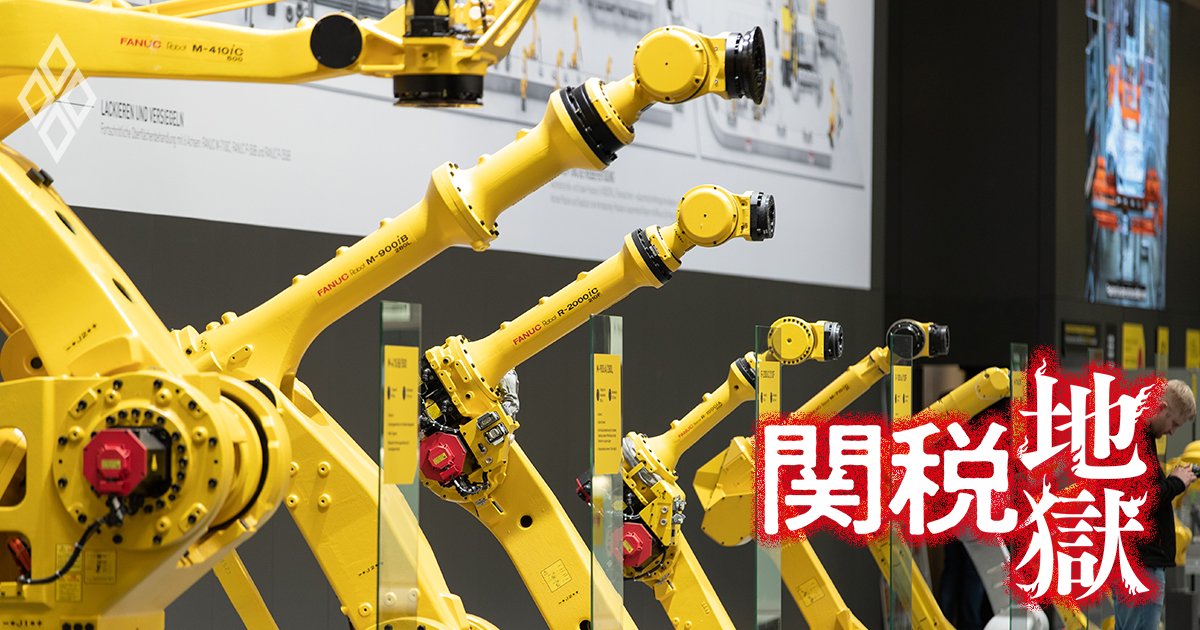Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
新型コロナウイルスの感染拡大によって、大阪や神戸では阪神大震災以来の医療崩壊が起きた。しかし、関係者は状況の好転を目指して必死で動いた。新型コロナウイルス感染症の重症診療をする集中治療医として、また災害医療を学んだ救急医として、そこで得られた貴重な教訓を振り返り、他地域での医療崩壊に備えるための情報を届けたい。(名古屋大学大学院医学系研究科救急集中治療医学分野医局長、集中治療専門医、救急科専門医 山本尚範)
コロナによって大阪は
文字通りの「医療崩壊」
2021年4〜5月に大阪で起きたことは文字通りの医療崩壊であった。重症患者に本来の診療ができず、通常なら救える命が失われた。規模は違うが、中国・武漢や欧米、新興国の多くの都市部で見られた状態だ。
大阪では21年4月12日ごろから、新型コロナウイルス感染者の重症病床がほぼ埋まっていた。最も多い時は70人以上の重症患者を、中等症以下の患者を診る病院で対応した。中等症病院の人員が不足し、病院で治療すべき人が入院できず、救急車を呼んでも病院に搬送されない例も確認された。自宅で医療を受けることなく亡くなる人もいた。
大阪は「コロナ医療崩壊」に
どのように対処したのか
大阪府は、知事や幹部職員の強いリーダーシップの下、改正感染症法に基づいてコロナ専用病床のない病院にコロナ患者の入院受け入れを要請した。応じない医療機関名は公表できる。その結果、重症病床の確保数は当初の224床から一気に100床増やして324床での運用となった。それでも足りず、5月5日は重症病床を365床まで拡大した。大阪府と大阪の医療機関が未曾有の危機に対して、極めて迅速に重症病床を増やしたことは評価されるべきだ。他の地域で、これほど大規模かつ速やかに重症病床が拡大できるとは思えない。