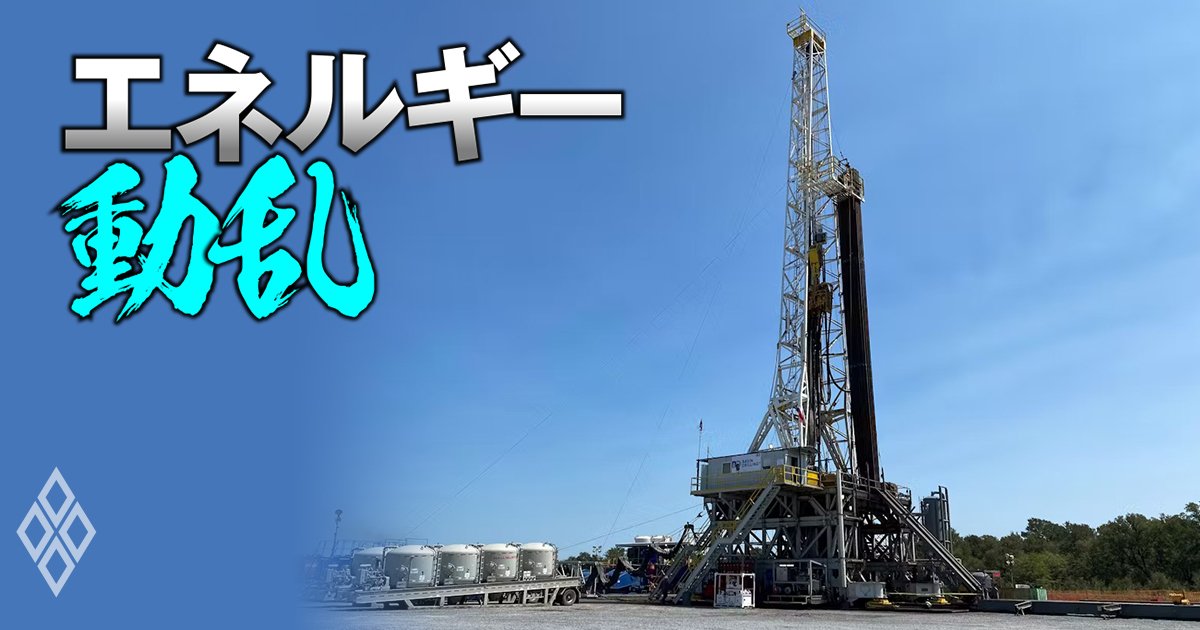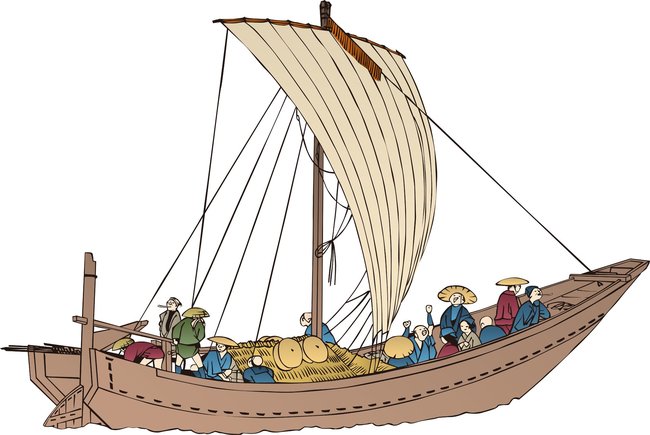 画像はイメージです Photo:PIXTA
画像はイメージです Photo:PIXTA
室町時代、数ある海賊集団のなかでも、村上海賊と並んで有名だったのが琵琶湖に面した近江国堅田(現在の滋賀県大津市)の海賊である(琵琶湖は海ではないので、厳密には「海賊」ではなく「湖賊」なのであるが、彼ら自身が「海賊」と自称しているので、ここではそれに従おう)。彼らが起こした無差別殺傷事件の逸話がある。『室町は今日もハードボイルド: 日本中世のアナーキーな世界』(新潮社)から一部抜粋・編集してお届けする。
琵琶湖の海賊
琵琶湖は縦に延びた日本最大の湖で、中世では北陸から京都に向かう物資は、みな琵琶湖上の水運を利用して運搬された。
しかし、この琵琶湖は堅田付近で、まるで紐で縛られたように細くくびれている。広いところでは湖東と湖西の間の距離は約20キロほどもある琵琶湖だが、この堅田付近だけは湖東と湖西の距離はわずか1キロほどしかない。堅田から対岸はいつでも見通せる距離にある。そのため琵琶湖を運行する船は、必ず堅田の目先を通行しなければならなかった。琵琶湖を運行する船から通行料を徴収しようとする場合、琵琶湖の自然の関門となっていた堅田は、最良の場所だったのである。
堅田自体は小さな町ながら、この立地を活かして、当時「湖九十九浦知行」といわれ、琵琶湖全域にわたる支配権を保持していた。この時期の堅田の風景を描いた『近江名所図』にも、湖畔の集落の端に、竹矢来で囲まれた役所のような建物が描き込まれている。そばには腰を低くしてその建物に近づく人物が描かれ、その手前には積み荷を満載した船が接岸されている。これは関所の建物と考えられ、琵琶湖を往来する船は必ずこの場で停船して、通行料を支払うことが義務づけられていたのだろう。
もちろん支払わずに強行突破しようとした船は、狭い水道でたちまち拿捕されてしまい、堅田の海賊衆からとんでもない制裁を受けることになる。中国の古典『水滸伝』に、山賊たちが立て籠もる「梁山泊」という治外法権の沼沢地が描かれているが、まさに堅田の存在は「日本版梁山泊」といったところである。