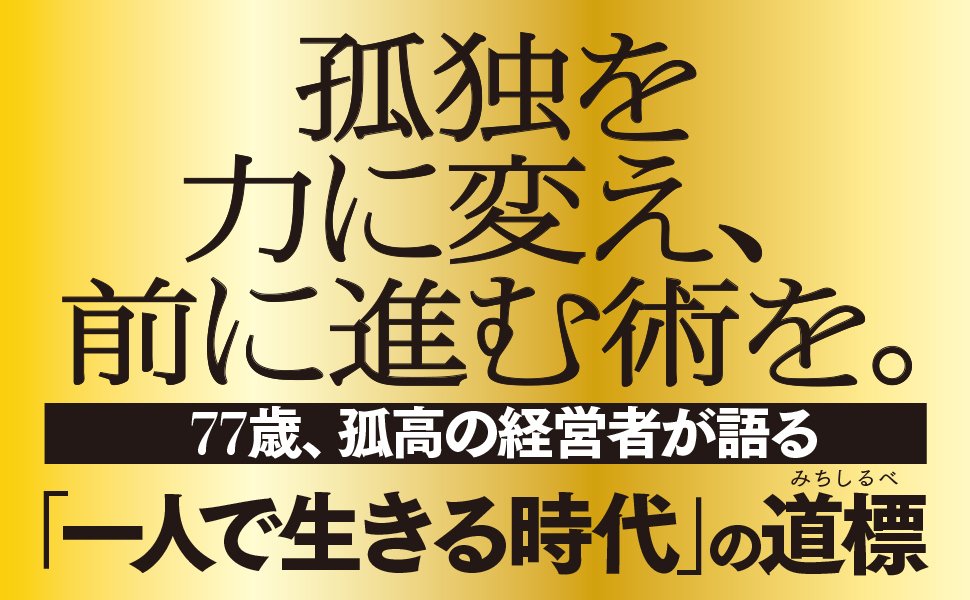「一人で大丈夫」と強がっている場合ではない
孤独を認め、たった一人で存在する頼りなさを隠さず見せることから、いつも何かが始まりました。
両親から離れて暮らす幼い僕を、「おいで」と呼んで抱き締め、放課後の教室でピアノを一緒に弾いてくれた小学校の担任の先生。
野球に明け暮れ、まともに就職活動をしないまま呆然と大学生活を過ごしていた僕に、「私の親戚に聞いてあげる」と就職先を紹介してくれた花屋のおばさん。
殺風景な寮生活にせめて一筋の彩りをと、毎日の練習帰りに花を一輪、買い続けた僕を気遣ってくれたのです。
花の美しさを教えてくれたのは、祖母。僕が中学に入る前に他界してしまった、おばあちゃんでした。
祖母は僕の将来の孤独を案じてか、花を通じて四季の豊かさを愛でる目を養ってくれました。
大人になってから、初めての海外赴任、昭和四十年代の香港でも、人の情けに助けられました。
ただでさえ物価が高いのに、当時の送金事情では給料の着金が数日ずれるのは当たり前。よって、月末になると、生活に困窮していた僕に寝床を与えてくれた彼女がいなければ、僕の今はありません。
依存はよくない。
けれど、困ったときに他人に助けを求める力は命をつなぎます。
「一人だけで大丈夫」と強がっている場合ではない。
自分が無力で、孤独な存在であると、認めることから始まるのです。
(本原稿は、中野善壽著 『孤独からはじめよう』から一部抜粋・改変したものです)