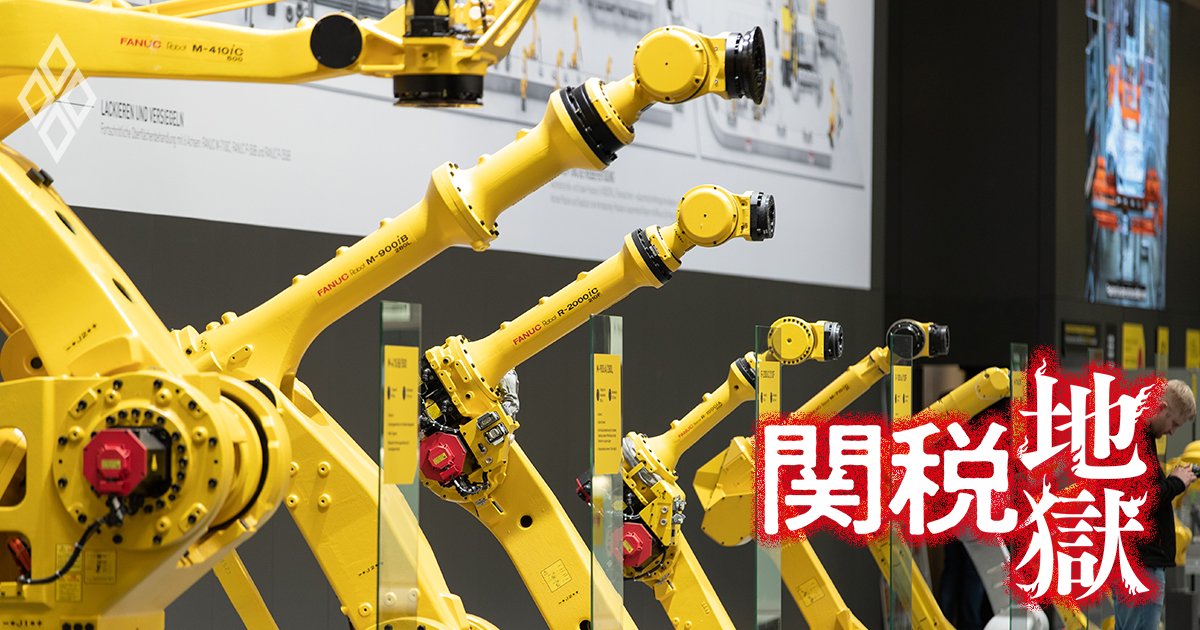写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
潤沢な防衛費や核ミサイルよりも大切なこと
ウクライナ侵攻を受けて、防衛費増額の議論が盛り上がっている。自民党安全保障調査会も今のGDP比1%程度から2%へ引き上げる案を今後の論点整理として示した。
確かに、「戦争犯罪を繰り返す悪の帝国」と目されるロシアが、北海道にまで侵攻する恐れがあるという専門家やメディアは後を絶たない。この世界の混乱に乗じて、中国も尖閣諸島へ乗りこんでくると主張される論者もおり、簡単に侵略されないよう、日本も何かしらの形で核の抑止力を持つべきだと主張する評論家やコメンテーターも増えてきた。
「平和ボケ日本がようやく尻に火がついてきたな」と喜ぶ愛国心あふれる方も多いだろうが、残念ながら防衛費を増やしたり、核の抑止力を持ったりすれば日本が守られるという発想もなかなかの「平和ボケ」だと言わざるを得ない。潤沢な防衛費や核ミサイルがいくらあっても、間違いなく国を守れない。大事なものが、見事にスコーンと抜けているからだ。
それは、「エネルギーと食料の自給自足」である。
残念ながら日本はこの二つがほとんどできていない。なので、敵基地攻撃能力を身につけたとしても、アメリカ・中国と並ぶ軍事大国になったとしても、他国とガチンコで戦ったら間違いなく負けてしまうのだ。
「日本の自衛隊は世界一優秀だ!さては貴様はロシアや中国の手先だな!」というお叱りが飛んできそうなので、実際に日本が周辺国から攻められたと仮定して、日本のエネルギーと食料がどうなっていくのかを考えていこう。