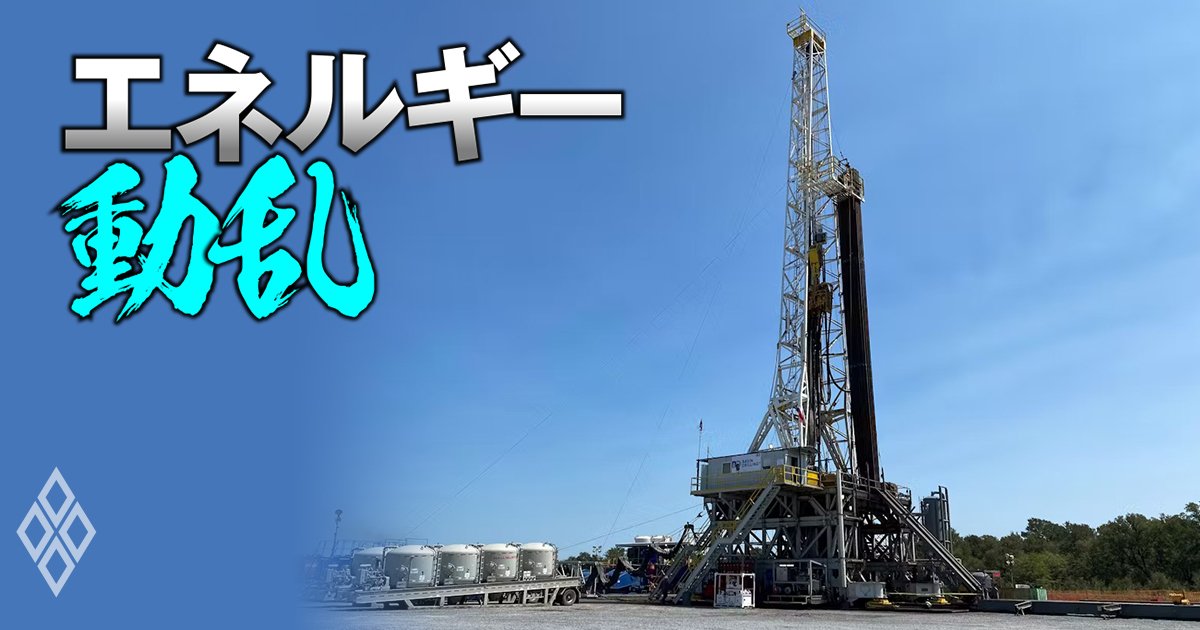Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
「死後、人の意識はどうなるのか」。誰しも一度は考えたことがある問いだろう。死後の世界について、確実なことを立証できる人はこの世にいない。だが、死の淵から生還した人の中には、「死後の世界を見た」という人がいる。京都大学学際融合教育研究推進センター教授のカール・ベッカー氏は、何十年にもわたり、こうした臨死体験者の証言を集めてきた。体験者が語る人知を超えた現象は、私たちに人間という存在、あるいは生きる意味についてを問いかける。(ライター 藤山亜弓)
人は死の淵で何を見るのか?
死ぬ直前に「一生の傾向」が表れる
当時15歳だったN君は、学校の帰りに自動車にはねられて重傷を負い、救急車で病院に搬送された。
その途中、N君は人生の走馬灯を見たという。これは、臨死体験者の約4人に1人が見る「ライフリビュー」と呼ばれるものだ。N君は自分が誕生する場面から救急車で搬送されて病院に到着するまでの様子をスライドショー形式で見たそうだ。
死の間際に人生を振り返ることはN君に限らず、インドやアメリカなどでも証言されている。そのときに見るのは、親や友達に親切にしたことや他者を傷つけたことといった、自分の倫理観を問われる出来事だという。死の淵に立つ人間は、自分の行いを第三者の視点で見るのだ。
このN君の証言を記録したのは、京都大学学際融合教育研究推進センター教授のカール・ベッカー氏だ。