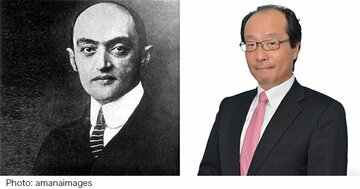円安は、輸出比率の高い製造業には追い風となる。決算の上方修正が続出するかもしれない。製造業を長年研究してきた藤本隆宏氏は、今こそ日本経済を「設備投資増→輸出再拡大・増産→価格・付加価値アップ→利益・賃金の同時アップ→人員確保と生産性向上で増産」の好循環軌道に戻すチャンスだという。長期視点で、日本の製造業の競争力を高める戦略を、3回の連載で詳しく伺った。第1回目は、その戦略論のベースになる「設計の比較優位説」を解説いただいた。(聞き手/ダイヤモンド社 ヴァーティカルメディア編集部 編集長 大坪亮、構成/嶺竜一)。
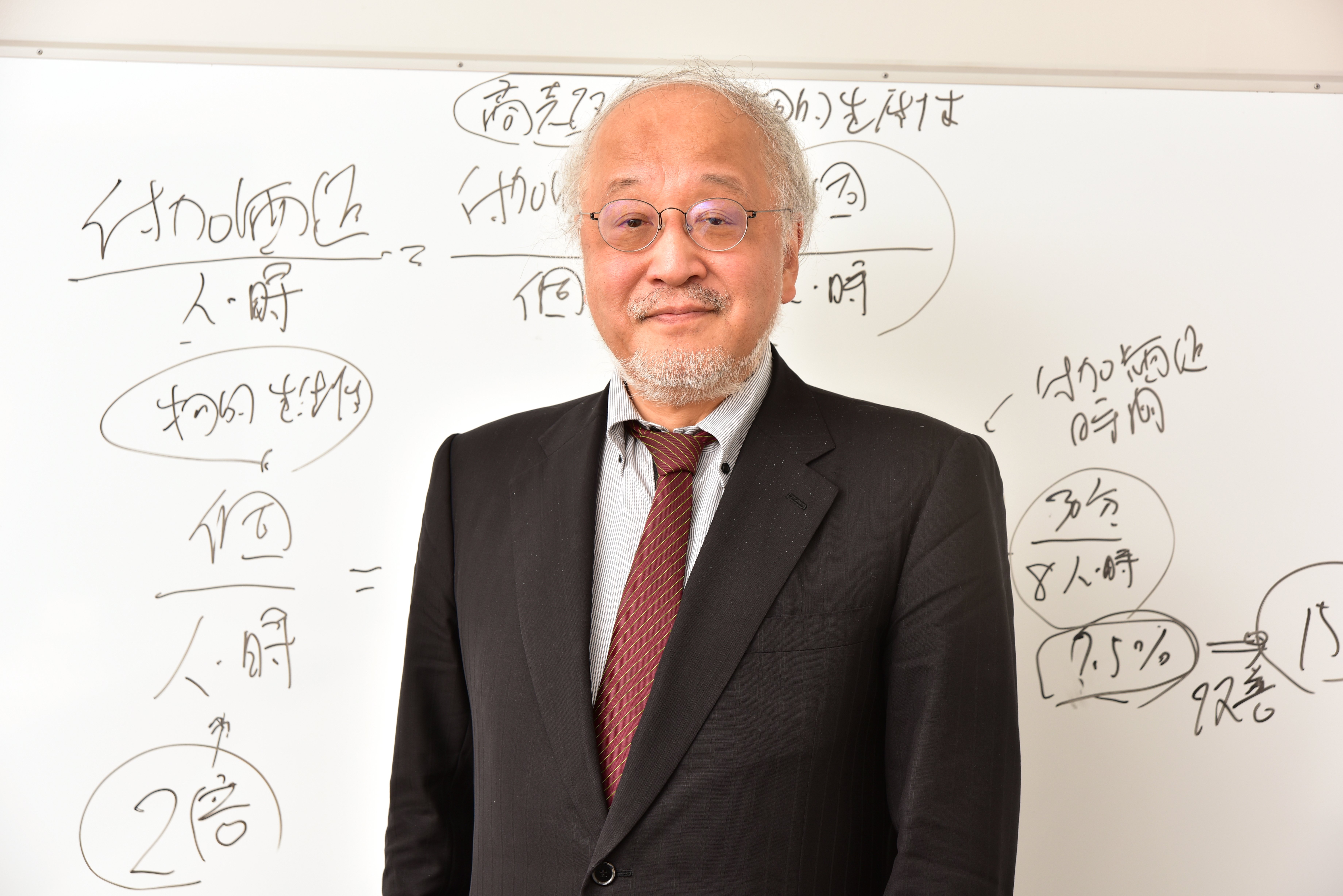 藤本隆宏(ふじもと・たかひろ)1955年生まれ。東京大学経済学部卒。ハーバード大学ビジネススクール博士(D.B.A.)。専攻は、技術管理論・生産管理論、進化経済学。東京大学大学院経済学研究科教授、同ものづくり経営研究センターセンター長等を経て、2021年より現職。『生産システムの進化論』(有斐閣)、『生産マネジメント入門〈Ⅰ〉〈Ⅱ〉』(日本経済新聞出版社)、『現場主義の競争戦略』(新潮社)など著書多数。
藤本隆宏(ふじもと・たかひろ)1955年生まれ。東京大学経済学部卒。ハーバード大学ビジネススクール博士(D.B.A.)。専攻は、技術管理論・生産管理論、進化経済学。東京大学大学院経済学研究科教授、同ものづくり経営研究センターセンター長等を経て、2021年より現職。『生産システムの進化論』(有斐閣)、『生産マネジメント入門〈Ⅰ〉〈Ⅱ〉』(日本経済新聞出版社)、『現場主義の競争戦略』(新潮社)など著書多数。Photo by Ryuichi Mine
製造業の競争環境は
長期的に改善している
――円安が進み、24年ぶりの1ドル=140円台です。日本の製造業で輸出比率が高い企業は、価格競争力がある状態ではないでしょうか。
藤本隆宏(以下、略) 急激な円安も円高も経済が混乱し好ましくありませんが、成り行きでこうなった以上、輸出可能製品を持つ企業がまず頑張る局面だと思います。実際、輸出で為替差益を得ている企業は既にかなりありますが、その多くは黙っています。
とはいえ、円建て200万円だったクルマを250万円にしても、他条件が一定ならドル建て輸出価格はまだ値下げ可能ですから、輸入材料費が膨大でない限り、輸出財の付加価値は大きく増えるでしょう。
そして、この付加価値増加分は、利益増、賃金アップ、人員確保、設備投資、いずれにも使えます。
実際、来年は、大企業の設備投資計画は増勢ですが、仮に大規模投資を避けたい企業でも、既存設備の活用・改良により輸出余力はかなりあるとみます。それでも人員不足なら、率先して賃金を上げるのです。
最大のネックは、約30年間の負け癖によって縮小均衡マインドが強い、多くの大企業経営者かもしれません。
しかし、今の日本で、「設備投資増→輸出再拡大・増産→価格・付加価値アップ→利益・賃金の同時アップ→人員確保と生産性向上で増産」という良循環を先導するファーストペンギンになれるのは、輸出可能企業です。
実は今回の円安がなくても、日本製造業の競争環境は、30年かかりましたが、長期的に改善しています。
国内工場の自助努力による生産性向上、中国との賃金格差の縮小、サプライチェーン混乱による海外顧客の納期重視、日本製品の高品質イメージ保持、サステナビリティによる最適設計(インテグラル型)物財の需要堅調、これらは、現在の円安がなくても生じていた追い風です。
産業趨勢は、あくまでも長期の歴史観を持って洞察すべきです。経済の片面しか見ない今の円安危機論も、逆に円安しか見ていない唐突な製造業復活論も、短期動向に振り回されているという点では、どちらも間違いでしょう。
――日本の製造業の限界説を、メディアで多く目にします。
間違いです。多くの人が過去の思い込みで語っていますが、経済統計を見れば、誤りが一目瞭然です。日本の製造業の実質付加価値総額は100兆円超で、過去30年で1.3倍以上になっています。この数値が国内総生産(GDP)の20%を超えるのは主要7カ国では日本とドイツだけです。
また、1人当たりの年間付加価値生産性は約1100万円で、過去30年間で2倍近くになり、非製造業の約1.4倍です。
中国経済や米国デジタル産業の成長には遠く及ばないものの、国内製造業全体は縮小していません。家電や半導体など局地戦での大敗はありましたが、勝てている分野があったからこそ全体は維持されたのです。
そもそも各国に比較優位産業があり、それぞれの強みを生かして貿易すると経済厚生が高まるという古典派経済学者デヴィッド・リカードの比較優位説は、今も最重要原理です。