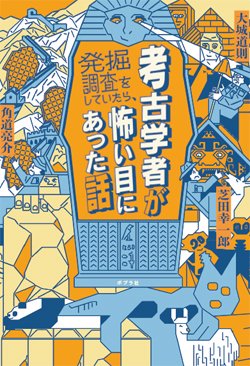発掘していたら、三体の骨が現れた!
翌朝は朝から気温が高くやけに暑かった。作業は今日も一人だ。他の墓の調査の方が佳境に入っていて、私のいる墓が見るからにたいしたことないものだからだ。現場に到着すると一人だけ違う方向に歩きだす。後ろから「今日はこっちの現場に来るか?」と隊長から声が掛かるが、「いえいえ大丈夫です。気にしないで下さい。ありがとうございます」と言って、そそくさと逃げるように自分の持ち場に入った。
もちろん現場は昨日の帰りにシートを掛けたままだ。まずシートを片付ける。骨は見えているが、そして大腿骨であろうと推測しているが、上下の配置がまだわからない。とりあえず壁に向かって骨を検出して行くことに決めた。三十分もしないうちにすぐ傍から違う骨が出てきた。どうやら坐骨のようだ。ということは骨盤? そこからは真横に進んだ。もちろん竹べらと手スコを駆使して。坐骨の次には恥骨があるはずだ。恥骨はそこから年齢や出産の有無が判明することから、何より重要だと形質人類学の先生に聞いていたので後回しにする。
まずは足の方から始めよう。下半身から上半身という手順で掘ることに決める。表面の土を少し剥ぐと膝蓋骨が見えてきた。その下には脛骨と腓骨が並んでいた。最後に足の指の骨がバラバラと出てきた。続いて上半身に取り掛かる。すぐに腕の骨と手の指の骨が現れた。全体像がイメージできたので、そこからはガツガツと掘り進めた。肋骨と背骨、そしてついに頭蓋骨の登場だ。
首の骨から少し離れているようだ。偶然か? いずれにせよ、一仕事終えた。骨自体は脆かったが、ほぼ完形の全身骨格が目の前に出現したのだ。しかしそれと同時に今掘り出した人骨の向かってすぐ右側に新たな骨が顔を覗かせていることに気づいてしまった。やれやれである。もう一体ありそうだ。まあ時間はまだまだある。もう一体やっつけよう。
二時間くらい経った頃、背恰好がほぼ同じ人骨が出てきた。兄弟なのか、親子なのか、夫婦なのか、それとも双子なのか? これだけでは判断がつかないなと思案していると、二体目の人骨の横にもう一つ新たな人骨が見えたのである。ええ、三つ子か? 思わず見なかったことにしようかと本気で思ったが、そういうわけにもいかないので諦めて掘り進めた。こんな砂漠の真ん中の墓の中で考えても仕方がない。考えるだけ無駄だ。発掘マシーンと化し、機械的に骨を出していく。同じ背恰好の人骨が綺麗に並んで三体現れた。
不思議な体験
パルミラ遺跡には、観光客にも人気の「三人兄弟の墓」という名所がある。これもまた地下墓で美しい壁画が内壁に描かれているのだ(壁画は球の上に立つ女神によって掲げられた被葬者の顔とその上のスペースに娘たちに囲まれたアキレウスが描かれている)。
「三人」という共通点に何らかの意味があるのかもしれないなと考えながら眺めているうちに気づいた。三体とも胴体から首が離れているのだ。直感的に人為的な気がした。首を意図的に切断されたのであろうか。古代の墓では死者の蘇りを防ぐために遺体の上に重い石を置いたり、手足を縛ったり、わざと身体に損傷を与えることがある。それと同じ意味があるのかもしれない。ちょっと嫌なものを目にした気がした。
その夜珍しく夢を見た。私はあまり夢を見ない体質なのだが……。夢の中で私は戦場にいた(ような気がする)。阿鼻叫喚の中、多くの人たちが逃げ惑いながらこちらに向かって走って来る。実際には耳に音は聞こえてこないのだが、不思議と身体に声を感じる。声の先には人がいた。走っていた。何者かに追われているのだ。何者なのかは暗くてよくわからない。闇の中を人々が通り過ぎた後、さらに三人の男の姿が目に入ってきた。三人とも何者かから逃れようと後ろを何度も振り向きつつ必死に走っていた。私はなす術もなく少し離れた場所からその光景を眺めているだけだった。
するとローマ兵が使うグラディウス(先端が鋭角になった刃渡り50センチメートルほどの刀剣)がとうとう彼らを捉えた。一閃! それは一瞬の出来事であった。三人が崩れ落ちる際、私は彼らの前に立っていた。なぜだか気づかないうちに移動していたのだ。2メートルほどの距離で目にした彼らの苦悶の表情は今でも忘れることができない。彼らの目にも私の姿は映ったのであろうか。
その後、グラディウスによって彼らの首がはねられたのかどうかは知らない。なぜなら突然耳の近くで鳴り出した目覚まし時計のアラームに叩き起こされたからだ。窓からのぞく外はまだ暗かった。すぐに夢だと気づいたが、あまりにもリアルであったのでまだ声が耳に、臭いも鼻に残っている感覚が抜けていなかった。
その後、イタリアやエジプトでも発掘調査を経験したが、後にも先にもあのような不思議な体験をしたことはない。