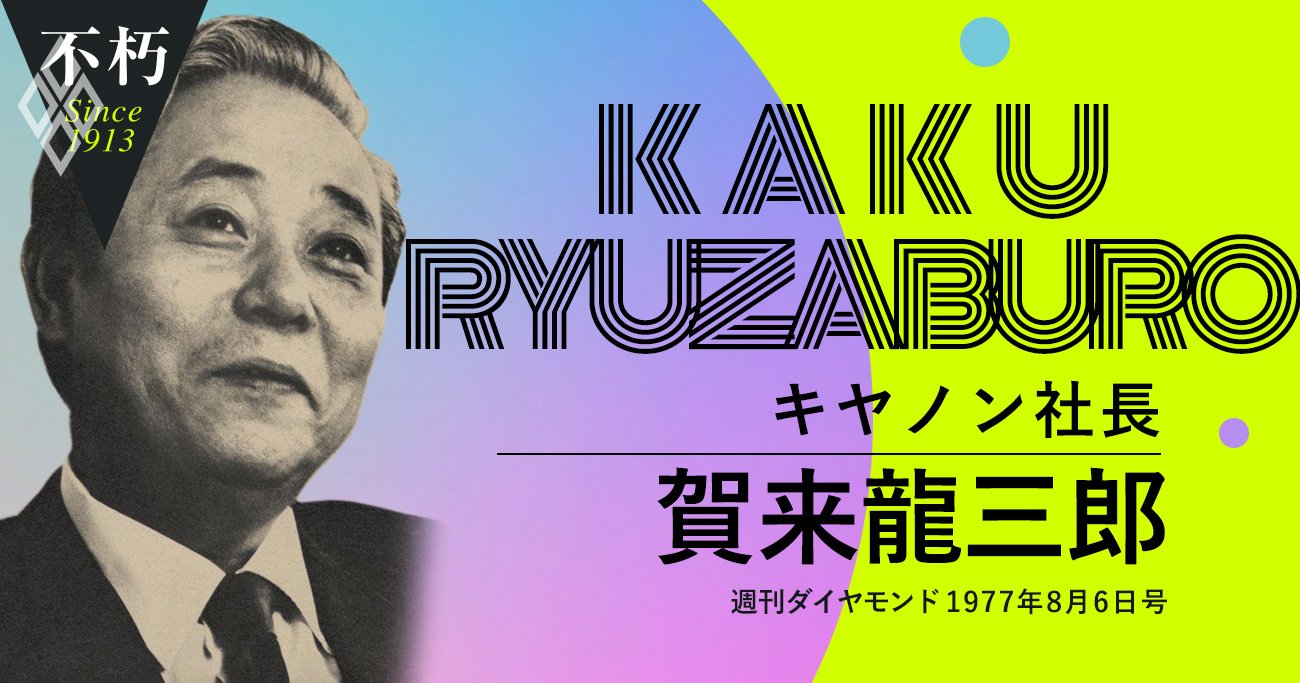
賀来龍三郎(1926年5月19日~2001年6月23日)は、第2次世界大戦の戦中戦後の混乱期に青春時代を過ごし、食べるため、学ぶために苦労した世代だ。賀来も一度千葉工業大学工学部に入学したが中退。小学校の代用教員や繊維や雑貨類のセールスマンなどを務めた後、九州大学に入り直し、卒業したときには29歳になっていた。
キヤノンの前身、精機光学研究所は1933年11月創業。ドイツのライカに「追い付け追い越せ」で国産カメラの開発にいそしむ。47年にキヤノンカメラに社名変更し、54年にはライカに劣らぬ名機と評価を受ける「IV Sb改」を世に出した。賀来が入社したのは、まさにその年である。
入社以来経理畑を歩み、62年には企画課長だった賀来は、第1次長期(5カ年)経営計画の策定に携わる。当時のキヤノンはカメラの売り上げが全体の95%を占めていたのだが、賀来はカメラ事業を80%にまで縮小して事業の多角化を進める計画を打ち出した。
そして77年、キヤノンの創業メンバーの一人で2代目社長だった前田武男が、社長就任からわずか3年で死去したことを受け、急きょ社長に就任したのが賀来である。当時、51歳だった。
今回、紹介するのは社長就任直後の「週刊ダイヤモンド」77年8月6日号に掲載された賀来のインタビューだ。記者はリードにこう書いている。「無名の苦学青年でも、51歳の若さで大企業の社長の地位に就くことができる。日本の大企業の民主性と精神的な若さを示している。これから、この世代の大企業経営者が出てくる時代である」。
この後の賀来は、77年から89年の社長在任期間に、電卓や複写機などカメラ以外の事務機分野への多角化に注力し、さらに欧米での事務機の現地生産をはじめとする国際化を強力に推し進めた。かくしてキヤノンを高収益のグローバル企業に育て上げたことから、「キヤノン中興の祖」と呼ばれる存在となるのである。(敬称略)(週刊ダイヤモンド/ダイヤモンド・オンライン元編集長 深澤 献)
キヤノンの前身、精機光学研究所は1933年11月創業。ドイツのライカに「追い付け追い越せ」で国産カメラの開発にいそしむ。47年にキヤノンカメラに社名変更し、54年にはライカに劣らぬ名機と評価を受ける「IV Sb改」を世に出した。賀来が入社したのは、まさにその年である。
入社以来経理畑を歩み、62年には企画課長だった賀来は、第1次長期(5カ年)経営計画の策定に携わる。当時のキヤノンはカメラの売り上げが全体の95%を占めていたのだが、賀来はカメラ事業を80%にまで縮小して事業の多角化を進める計画を打ち出した。
そして77年、キヤノンの創業メンバーの一人で2代目社長だった前田武男が、社長就任からわずか3年で死去したことを受け、急きょ社長に就任したのが賀来である。当時、51歳だった。
今回、紹介するのは社長就任直後の「週刊ダイヤモンド」77年8月6日号に掲載された賀来のインタビューだ。記者はリードにこう書いている。「無名の苦学青年でも、51歳の若さで大企業の社長の地位に就くことができる。日本の大企業の民主性と精神的な若さを示している。これから、この世代の大企業経営者が出てくる時代である」。
この後の賀来は、77年から89年の社長在任期間に、電卓や複写機などカメラ以外の事務機分野への多角化に注力し、さらに欧米での事務機の現地生産をはじめとする国際化を強力に推し進めた。かくしてキヤノンを高収益のグローバル企業に育て上げたことから、「キヤノン中興の祖」と呼ばれる存在となるのである。(敬称略)(週刊ダイヤモンド/ダイヤモンド・オンライン元編集長 深澤 献)
実際の会社の体質は
バランスシートだけでは表せない
──先輩の記者に聞いてきたんですが、賀来さんは課長時代から会社の在り方について、はっきりした自分の考え方を持っていたそうですね。
もう忘れちゃいました(笑)。
──キヤノンの行き方が賀来さんの考え方と違っていて悩んだそうじゃありませんか。
 1977年8月6日号より
1977年8月6日号より
キヤノンという会社は、いまのコンピュータ用語でいうと、ハード志向の会社だった。もちろん製品は良いものを造らなければいけないが、良い製品を造れば経営そのものは終わり、という感じがみなぎっている会社で、このへんはキヤノンのいい点だと思うんです。
非常にユニークな製品が出るという意味でハード型の会社だったけれども、ソフト面では比較的弱かった、そこを強くしたらどうかということを一生懸命言ったわけです。
ソフトというのは、一つに経営面です。バランスシートや損益計算書の自己資本比率、利益率というのは金額計算できる。ところが、実際の会社の体質はバランスシートだけでは表せないものがある。人間の問題を例に言いますと、1万人の従業員がいるとしかいえない。その能力は金額査定できませんね。しかし、その能力はポテンシャルの高いものにしていかなければならない。個々の人の能力開発が当然、会社の実力になってくるわけです。さらに、課とか部、工場といったグループの能力開発が当然必要になってくる。







