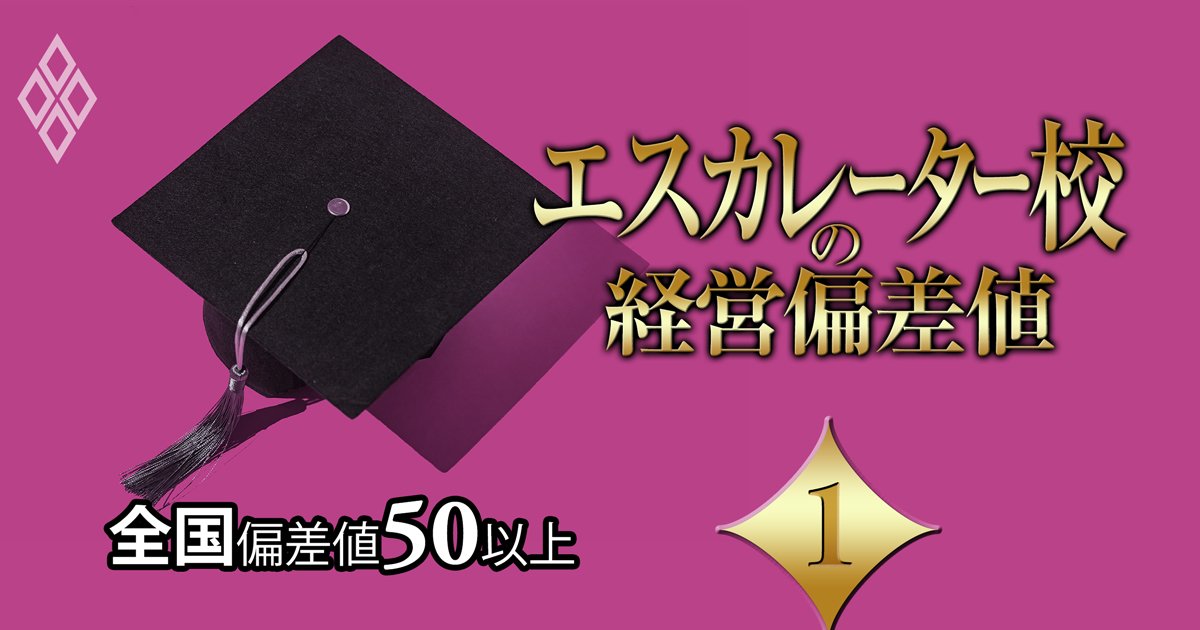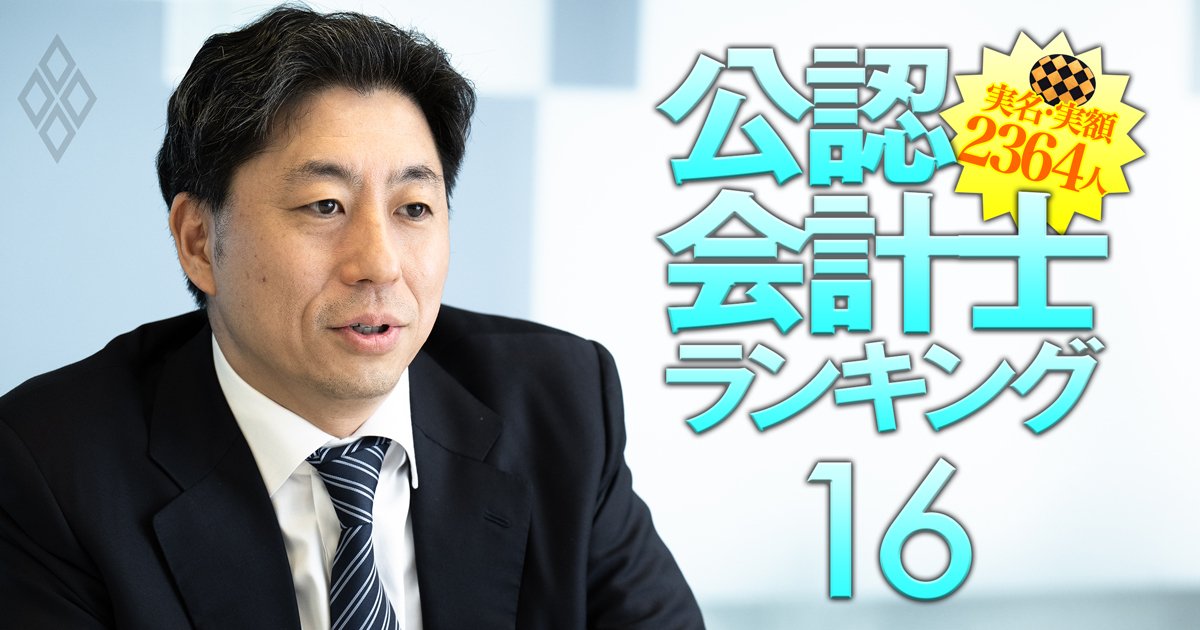Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
国家公務員の初任給を1万円以上引き上げるよう、人事院が内閣・国会に対して勧告した。大卒・高卒の初任給をともに1万円超引き上げるのは、33年ぶりのことだという。しかし今回に関しては、公務員の給与アップのスピードを政治的にさらに加速することが適切だったのではないか。(経済評論家 山崎 元)
国家公務員の給与改定は
人事院勧告にプラスαが欲しかった
人事院は、8月7日に2023年度の国家公務員の給与改定に関して、内閣と国会に勧告を行った。勧告文書は川本裕子総裁から岸田文雄首相に手渡しされた。
国家公務員の給与は人事院の勧告に基づいて国会で承認されて決まり、勧告はある程度以上の規模を有する民間企業の給与水準を参考にして決定されるのが大まかな仕組みだ。
今回の人事院勧告では、国家公務員を志望する学生が減っている近年の傾向に鑑みて、大卒で1万1000円、高卒で1万2000円の初任給引き上げを行ったことが、ニュースの見出し的には「目玉」になっている。勧告後の大卒の初任給は24万9640円だ。
全体として、若手の給与の伸びを大きくするバランスになっていて、全体の平均で見たベースアップはプラス0.96%だ。金額では月額3869円に相当する。また、ボーナスが年間4.40月分から4.50月分に0.10カ月分増額され、増額分は期末手当の増と勤務の評価に基づいて支給される勤勉手当分に二分されている。
人事院の資料によると、モデルケースで試算した定期昇給分を加えると月収で約2.7%、年収で約3.3%の増加率になるという。