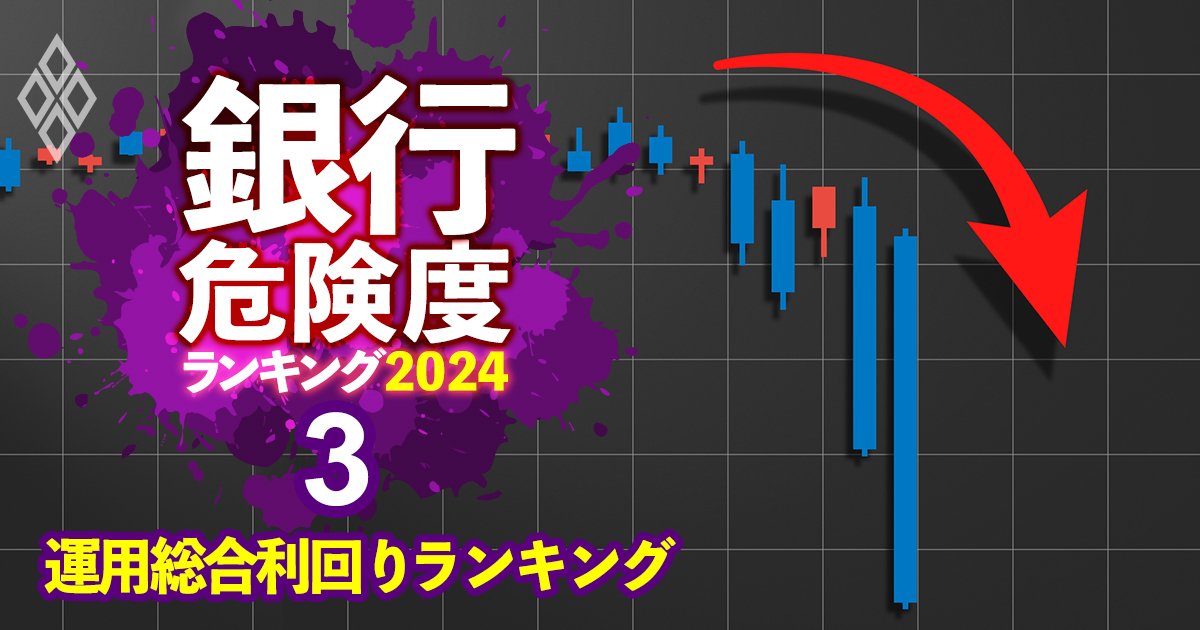スモールビジネスを取り巻くBtoB取引の課題
なぜ次の挑戦の場としてBtoBコマースに着目したのか。菅野氏によると家族の運営していたブランドが1つのきっかけになったという。
「実は私の妻がShopifyを使ってハーブティーのブランドを運営しているのですが、その在庫が自宅の子ども部屋を圧迫しているような状態でした。妻のような個人に近い人たちがECのプラットフォームによってエンパワーされたことは、ここ数年のテクノロジーの浸透の事例としてもすごく良いことだと思っています。その反面、小売だけでは生産した商品を捌ききれなかったり、在庫の扱いに苦労したりするといった課題もあると感じていました」
「その年に妻のブランドでは、たまたまヨガチェーンスタジオから問い合わせがきて、1回の発注で元々の年商分くらいの注文をいただいたんですね。ただ本人にとっては初めての卸売ということもあり、価格設定や手続きなどを進めながら、数カ月かけてなんとか納品までたどりつけました。この場合は1対1の相対取引でしたが、N対Nの取引になったらどうなるのだろうか。そこにおける課題はあまり解決されていないのではないかと考えたことも、goooodsを立ち上げる1つの理由になりました」(菅野氏)
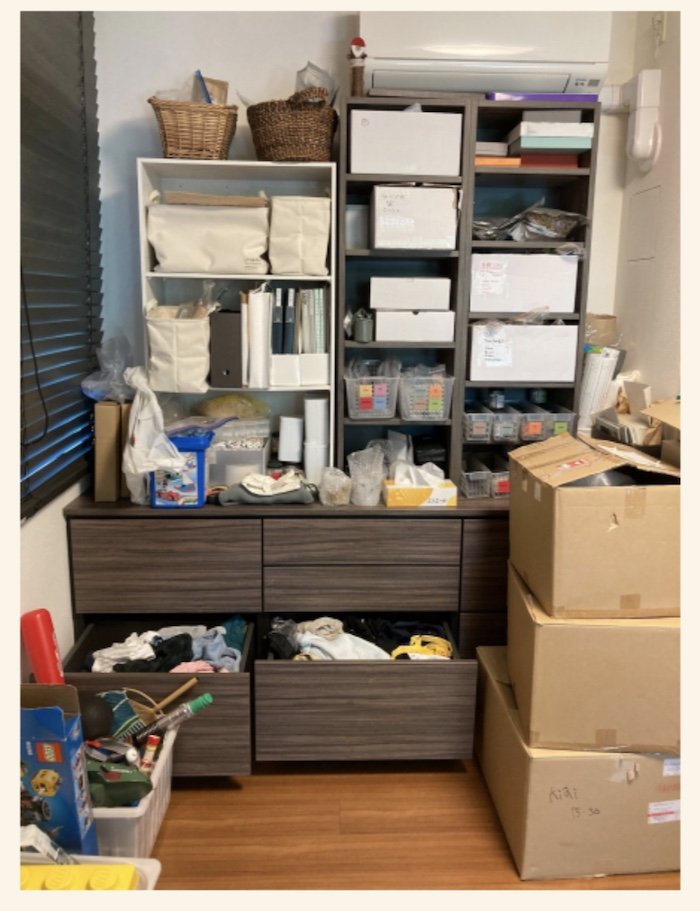
現在Shopifyを活用する事業者(マーチャント)は170万を超えており、BASEでも約180万のショップが開設されるほどの規模になってきている。新しいブランドが生まれ市場が広がっている一方で、特に小規模なブランドに関しては営業リソースやネットワーク、マーケティングノウハウの不足などによって「卸売先の開拓ができずに販売チャネルの拡大に悩む人たちも増えている」というのが菅野氏の見立てだ。
これまで卸売先の開拓手段としてはオフラインの展示会へ出展したり、卸問屋など中間流通事業者へ開拓を依頼したりするのが主流だった。ただそこには「デジタル化の壁」と「信用の壁」が存在していると菅野氏は話す。
商談から納品までのプロセスがデジタル化されておらず、データも構造化されていないため効率化が図りづらい。取引の実績がない場合は保守的な条件などによって信用を補完するしかなく、個人や小規模のブランドにとってはハードルが高かった。
goooodsの狙いはここに機械学習技術などをはじめとしたテクノロジーを持ち込むことで、新しいBtoBコマースの体験を構築することだ。
「マシンラーニングなどの技術は広告やBtoCのコマースでは一般的な技術になりつつありますが、BtoBの取引の領域にはまだあまり浸透していないと考えています。この技術を持って、新しい世代のコマースプラットフォームを作っていくというのが私たちがやろうとしていることです」(菅野氏)