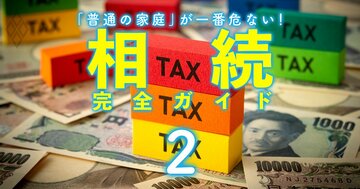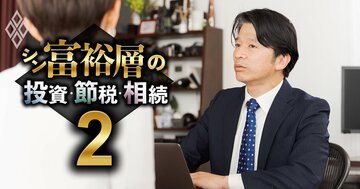Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
相続税の負担を軽くするために、「タンス預金」が有効だと考える人は少なくない。しかし、税務署の調査でタンス預金はバレることがほとんどだ。しかも7月からの新紙幣発行開始で、タンス預金がいっそう危うくなるかもしれない。特集『法改正で知らない間に損をしない!相続・贈与・実家の新常識』(全13回)の最終回では、相続税の税務調査で税務署が狙うポイントについて解説する。(ダイヤモンド編集部副編集長 大矢博之)
家計資産の現金は109兆円
多額のタンス預金が眠っている
20年ぶりの新紙幣発行まであと2週間を切った。
7月3日に発行される新紙幣では1万円札の肖像が渋沢栄一に、5000円札は津田梅子に、1000円札は北里柴三郎にとデザインが一新される。
新紙幣を発行する理由について、日本銀行は偽造防止対策の強化とユニバーサルデザインの向上を挙げている。ただし、裏の狙いがあるとの見立ては絶えない。それは家庭に眠る「タンス預金」の炙り出しだ。
 7月3日から発行される新紙幣の見本。20年ぶりにデザインが一新された Photo:SOPA Images/gettyimages
7月3日から発行される新紙幣の見本。20年ぶりにデザインが一新された Photo:SOPA Images/gettyimages
日銀の資金循環統計によれば、2023年末の家計の金融資産は2141兆円で、前年同期から5.1%増えた。このうち現預金全体では同1.0%増の1127兆円と増加したものの、現金に限れば同0.8%減の109兆円と減少に転じた。
現金が減った理由について、昨今のインフレで価値が目減りすることを嫌って預金など他の資産形態に切り替えるほか、新紙幣発行を前に家庭で保管していた旧札を預金するケースなどが考えられる。
家計の現金を人口で割り、1人当たりが保有する現金を単純計算すると平均約88万円だ。全てがタンス預金とまではいえないものの、日本の家庭には数十兆円規模の現金が眠っているとみていいだろう。
また、高齢者の中にはタンス預金は相続税対策になると信じている人も少なくない。相続税は相続財産が増えるほど負担が大きくなる。所有者がすぐに突き止められる預金や株などとは異なり、現金のままならば見つかりにくく、税務署に申告しなくてもバレないと考えるからだ。
しかし、実際にはタンス預金は税務署にバレてしまうことがほとんどだ。そして新紙幣の発行でそのリスクも高まりそうだ。次ページでは、相続税の税務調査で税務署が狙うポイントについて解説する。