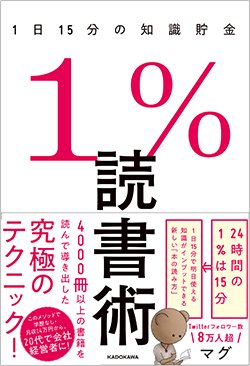 『1%読書術 1日15分の知識貯金』(KADOKAWA)
『1%読書術 1日15分の知識貯金』(KADOKAWA)マグ 著
では、「20%の主張と、80%の補足」を理解して何ができるのか。
「(2)読む順番には秘密がある」で説明した通り、読書をするとき人はよく迷子になります。
それもそのはず、1冊の書籍は平均すると約10万字で構成されており、全てを記憶することはできないからです。
そのため、読む順番を変え、全体像をつかむことにより、迷子にならない方法をお伝えしました。
ですが、それは全体感を理解するだけの話。
章立てのひとつひとつが短ければ良いですが、長い章の場合、章の中で迷子になる可能性もあります。
そこで、「20%の主張はどこだろう」と探すことによって、途中のページから開いても、その本が伝えたいことを理解することができるのです。
そこを考えずに、80%の補足(理由や具体例の部分)から読みはじめると、何について語っているか全く理解できないことでしょう。
パレートの法則を意識するだけで、いい意味での先入観を持って読み進めることができます。
ここでひとつ注意点があります。
「20%の主張と、80%の補足」と話すと、「重要なのは2割に過ぎないので、その2割の部分を読むことができれば十分だ」という人がいますが、それは大きな間違い。
たとえば、2割だけ読むとは、次のような部分のみ読むということです。
・アームレスリングは腕の筋トレをすると強くなる。
・ボクサーがジャブを打つときは、脇を締める。
・野球のスイングは頭を動かさないほうがいい。
考えていただきたいのですが、この2割の知識で読者は何を実践できるでしょうか。
アームレスリングであれば、腕に筋肉をつければ確かに力は増します。
ですがつけた筋肉を、どの角度で、どの瞬間に使うかを理解しなければ、実践できず、強くなるとは到底思えません。
つまり、ただ知識を取り入れた人と、「なぜこの知識は重要なのか」を理屈で理解した人では、結果に雲泥の差が出るのです。
パレートの法則は、書籍の中で迷子にならずに読むための法則であり、決して「重要な20%を読めば全体の80%を理解できる」という法則ではありません。
そもそも、書籍から学べる知識の上限は100%ではなく、読み手によって変わります。
知識は活かすためのものであり、言葉は思考のテーブルを広げるためのもの。
学びの上限を決めるのではなく、限られた時間の中で得た知識を無駄にしないために、パレートの法則を読書に活かしてみてください。







