学生にとって「大学が役に立つ」は
大学が提供するコンテンツの問題ではない
――おっしゃる通りですが、それをやるためには少人数教育のための教室の数がもっと必要になりますし、海外の大学のように訓練された院生などの補助教員から成るTA(ティーチングアシスタント)もいないといけません。
そういうコストをかけられない大学も多いでしょうし、もともと博士課程の院生が少ない大学ではTAの確保が難しいことも考えると、結局、東大のような大学でないと無理なんじゃないでしょうか。
吉見 いやいや、東大は一番難しいでしょうね。現実にはいろいろな問題があって、簡単にはいかないのはわかっています。でも、たとえばTAの問題にしても、大学間の横断的な連携を強化していけばなんとかなるはずです。私たちは、科研費の共同研究は大学を越えて、かなり横断的にやっていますよね。
同じように、博士課程やポスドクの若手研究者の初期キャリアについても、大学横断的な仕組みを作っていくべきです。それぞれの大学が、タテ割りタコツボでやっていける時代ではありません。その発想をやめなければ、日本の多くの大学は18歳人口の急激な減少に対応できず、潰れていくでしょう。
研究だけでなく、教師も、TAも、そしてとりわけ学生も、複数の大学に所属して、自分が探究しようとするテーマにしたがって大学や学部、指導してくれるシニアの先生方の間を渡り歩いていくべきなのです。
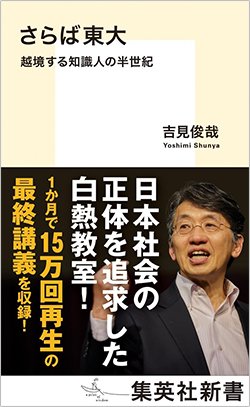 『さらば東大 越境する知識人の半世紀』(集英社新書)
『さらば東大 越境する知識人の半世紀』(集英社新書)吉見俊哉 著
その際、忘れてならないのは、学生にとって「大学が役に立つ」というのは、大学が提供するコンテンツの種類の問題ではないということです。大学が、特定の専門知識によって社会の「役に立つ」という認識には誤りがあります。そうではなく、大学はそれ自体が一種のパフォーマンスなのであって、知的演技力のある俳優たちを育てているのです。優れた俳優は、さまざまなジャンルの知識の体系を自分のものとして演じていくことができます。
上演論的に言えば、個々の授業はもちろん、大学のカリキュラム全体も一群のドラマの集合体です。ドラマというものは時間を構造化することによって成立しているパフォーマンスですから、大学において時間がどう構造化されているかが重要です。
そのドラマの上演において、学生たちは決して観客ではなく俳優です。大学という知の舞台において、学生たちはまだ新米の俳優ですから、彼らが自分たちでシナリオを作り、演じられる俳優になっていくためには手助けが必要です。その役割を果たすのが、大学教員なのです。







