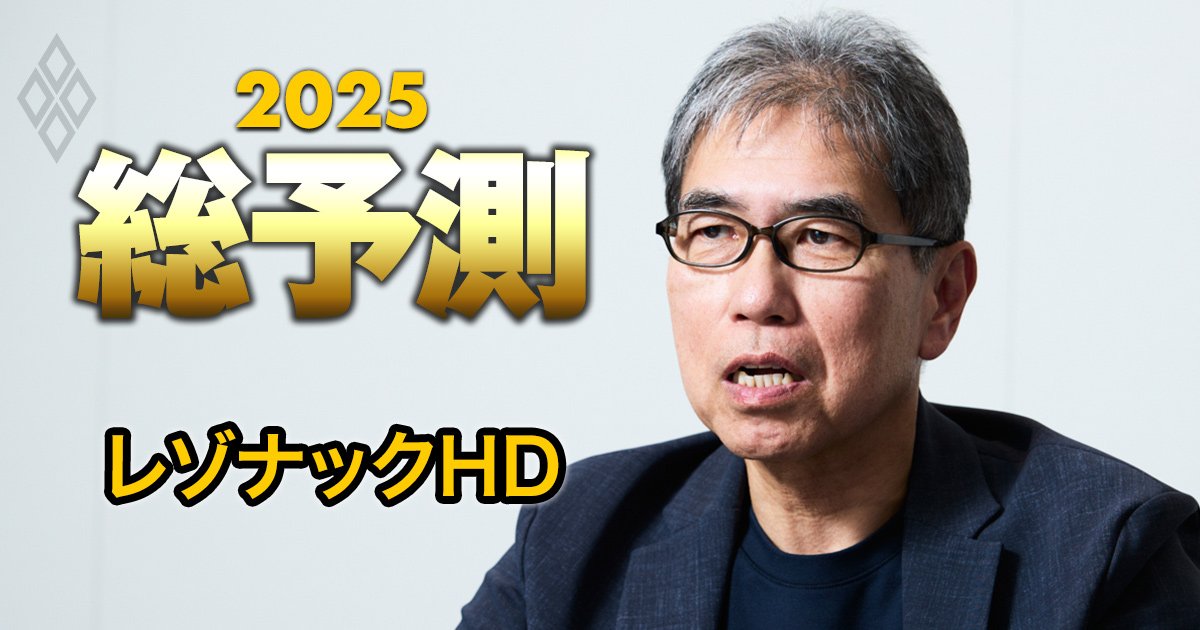Photo:JIJI
Photo:JIJI
ユニクロを世界的なアパレルブランドへ育て上げた、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長。かつて柳井氏にインタビューした際に「職場のお悩み」をぶつけたところ、思いもよらぬ厳しいアドバイスが返ってきたことがある。柳井氏がカチンときたNGワードとは?(イトモス研究所所長 小倉健一)
編集長はつらいよ
早いもので会社組織から独立して7月1日で丸3年になった。
古巣の雑誌『プレジデント』では新しい編集長が7月1日付で就任したようなので、私の肩書(?)も「前編集長」から「元編集長」へと変わったことになる。紙の雑誌単体で利益を出すのが相当困難な出版界の情勢になっているが、新編集長には腐らずに頑張ってほしいものだ。
現場の編集者・記者と、編集長の何が違うか。団体競技と個人競技の違いと言ったらわかりやすいだろうか。出版業界で働いている人は変わり者ばかりだが、特に古い歴史を持つ雑誌の現場では、やるべきことがだいたいわかっているので、個人の裁量で好き勝手やっても許される部分がある。
1人が暴走してワケのわからない色合いのページができたとしても、周りのページと並べられることで、むしろ読者にとって刺激的な雑誌ができあがったりするものだ。
何より編集長やデスクと呼ばれる管理職は忙しすぎて、現場のコントロールなど初めからあきらめているケースも多い。よって雑誌づくりの現場では、実績を残していく必要はあるものの、基本的には1人で好き勝手できたりする。
しかし、管理職となると全く違う。デスクは現場と編集長との調整をひたすらさせられながら、自分自身の成果も要求される。