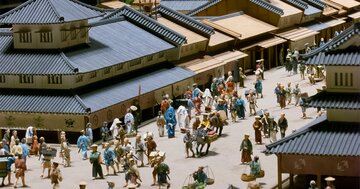『吉原三茶三幅一対(さんちゃさんぷくいっつい)』(延宝9年〈1681〉)には、伊勢屋という遊女屋の花代(はなよ)について、こんな評判が書かれています。
顔は丸顔だが、たしかに綺麗な顔立ちで、まさに花のようだ。しかし、お年がふけていらっしゃるので、おやぢは好かない風だろう。
どうも、おやぢは年のいった遊女があまり好みではなかったことがうかがえます。年齢が近いほうが話も弾みやすいんじゃないかと思いますが、求めるところは別にあったんでしょう。新造や遊女に好き嫌いがあったように、お客だっていろいろ選り好みしていたわけですね。
江戸時代では40歳前後の人でも
「初老」「年寄り」と扱われた
「おやじ」という言葉は現代でも使われますが、厳密な意味を問われても、なかなか答えにくい言葉ではないでしょうか。『日本国語大辞典』には「年取った男を親しみをこめて、また、見くだして呼ぶ語」とありますが、「年を取った」が何歳くらいからをいうのか、はっきりした定義がある訳ではありません。それは江戸時代でも同じですが、もう少し「おやぢ」がどういう存在を指したのか、掘り下げてみましょう。
『吉原つれづれ草』には「おやぢ」の言い換えとして、「老(おい)ぬる客」という言葉がでてきます。老いた客という意味ですね。そう言われると、なんとなく現代の「おやじ」よりも年長の印象を受けます。しかしながら、現代と江戸時代では、その寿命が大きく異なることにも注意が必要です。
もちろん、江戸時代だって、現代のように80、90歳と長生きする人はいましたが、その長短は地域によっても随分異なったようです(氏家幹人『江戸人の老い』草思社、2019)。私が目にした史料では「人生五十年」などと書かれているものもあり、いまからみると随分短命なひとも少なくなかったことが読み取れます。
そのせいか、40歳くらいから「おやぢ」といわれたり、甚だしくは「年寄り」「初老」扱いされる場合なんかもあったようです。