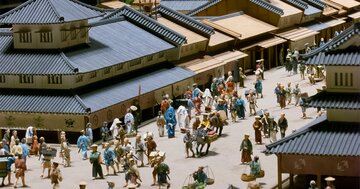少し時代は下りますが、『遊婦多数奇(ゆうだすき)』という史料には、「人は四十の内外(前後)になれば、猶更色深くなるもの也」とあり、甚だしくは、「腎虚」して死ぬ人も多かったとあります。「腎虚」というのは漢方の病名で、腎水(精液)が涸渇し身体が衰弱すること、すなわち性行為のし過ぎ等でおこる衰弱症を意味します。
現代ではほとんど耳にしないので、「そんなこと本当に起きるのか……?」と疑問に思えてしまいますが、当時の史料に「腎虚」の記述は非常に多く、一般的な病としてとらえられていたことがうかがえます。
さて、『吉原つれづれ草』には、「おやぢ」が遊女に嫌われることの詳しい説明として、こんなふうに書かれています。
「老いた客は物事に気力が衰え、それでいてくどくどと益のないことを繰り返し言ったり、だらだらとしてのろく、淡白だ」
「おやぢ」を「老いた客」と説明し、その欠点ばかりをあげています。ひどい言いようですが、遊廓関連の史料では、「おやぢ」や老いた客について、似たような書き方がされていることは珍しくありません。
こうした説明以外にも、「老人は必ず疑うものだから、その人の想う遊女には近づかない方がいい」(『大通伝』)といった、その疑い深さや嫉妬深さを揶揄するような記述などもみられます。
「おやぢ」が客になると、他の客が寄り付かない――そんなことになるのであれば、「おやぢ」が遊女たちから嫌がられたのも頷けます。くどくどしい話をするから嫌だというのも、類推できます。
「おやぢ」は見習いの新造の客になる場合が多かったといいますが、新造は、ほとんどが10代。いくら今より成人が早いといったって、そんなに若い女性が、くどい「おやぢ」の話を楽しめる訳がありません。
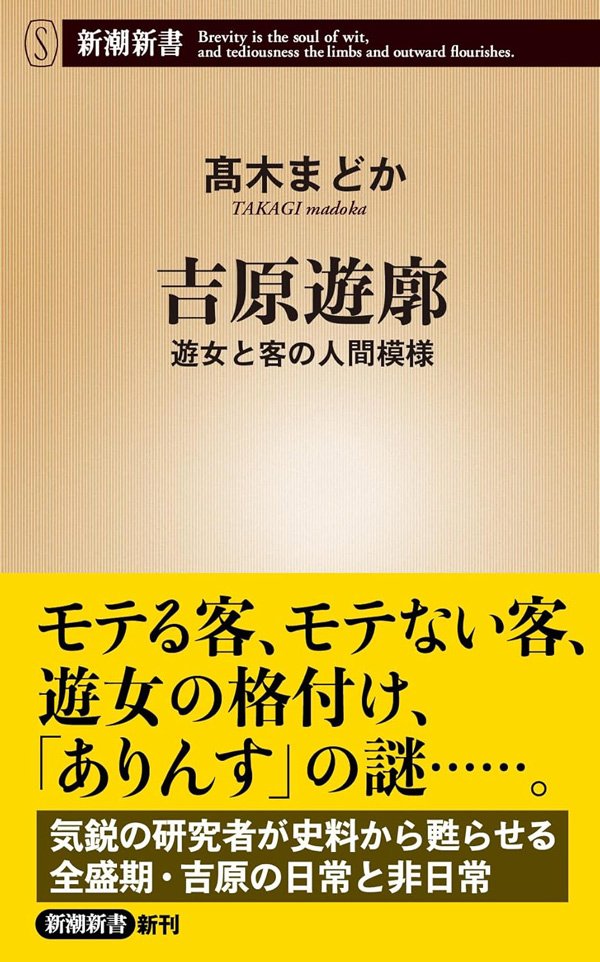 『吉原遊廓 遊女と客の人間模様』(高木まどか、新潮社、新潮新書)
『吉原遊廓 遊女と客の人間模様』(高木まどか、新潮社、新潮新書)