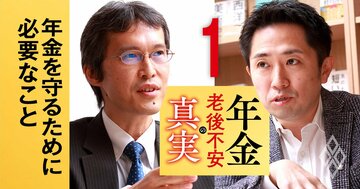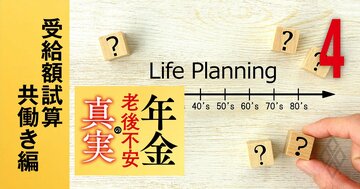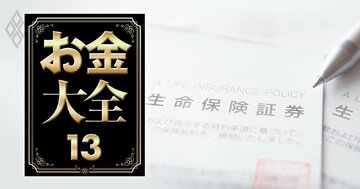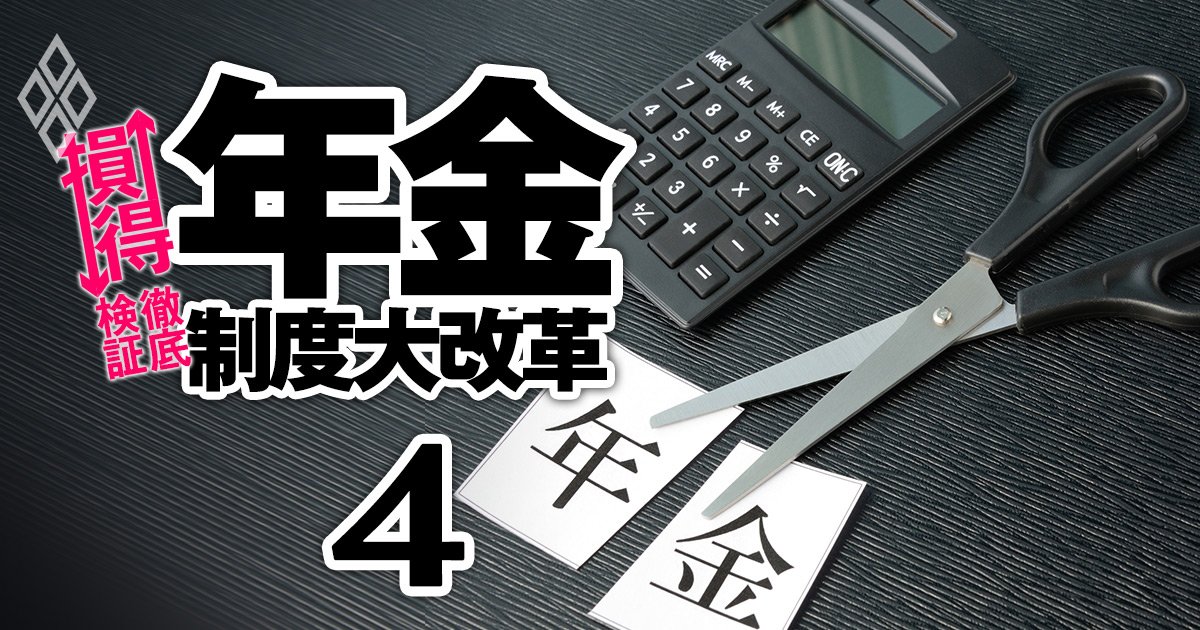 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
今回の財政検証では最も妥当な前提といえる過去30年投影ケースでも、所得代替率50%を割らずに「100年積立金が残る」との結果になった。ただ、就労人口の増加や運用成果が現在のペースで続くとは限らない。足元の出生率の低さを考えれば今回の人口の前提は楽観的といえる。特集『年金制度大改革 損↓得↑徹底検証』の#4では、財政検証での人口などの前提を改めて検証し、年金の将来への拭えない不安の正体を明らかにする。(ダイヤモンド編集部 竹田孝洋)
自公政権が打ち出した
100年安心年金の意味するもの
2004年の年金改正で、自公政権は「100年安心年金」というスローガンを打ち出した。それは100年後も公的年金の財政が破綻することなく、公的年金制度が継続しているということだ。
具体的には公的年金加入者数の増減と平均寿命の伸びに合わせて年金給付額を抑制するマクロ経済スライドを適用することで、100年後も1年分の年金給付額と同額の積立金を維持できることを表す。
積立金の水準を維持することだけを優先すれば、給付額を積立金が残るように削減すればいい。ただ、給付額を削減し過ぎては、老後の生活に支障が出る。一定水準の年金給付を維持できなければ安心とはいえない。
そこで、100年後の積立金を確保するために給付を抑制するマクロ経済スライドを適用することで、5年ごとの財政検証時に、その5年後に所得代替率が50%を割る見込みとなった場合には「給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずる」とされている。
つまり、給付水準が低くなり過ぎるとされた場合は、給付抑制をやめて年金制度を見直すというわけだ。
ここでいう所得代替率とは、年金のモデル世帯(現役世代の平均賃金と同額の収入に見合った保険料を40年間納付してきた厚生年金加入者本人とその配偶者である第3号保険者)が受け取る年金額(厚生年金の報酬比例部分と基礎年金2人分の合計)の現役世代の手取りの平均賃金に対する比率である。
年金の水準を議論するときには、この指標で議論されることが多い。年金が実質的に2割減少するということは、所得代替率が2割低下するということになる。50%を維持することで現役世代に比べて年金を受け取る世帯の生活水準が大きく下がらないようにするためだ。
50%という水準をメルクマークにしている以上、100年後も1年の給付分の積立金があることに加えて、所得代替率が50%を維持できてこそ100年安心といえる。
次ページでは、財政検証が提示する年金財政の複数のケースの経済、人口などの前提を踏まえて、年金は100年安心と言い切れるのかどうか検証する。