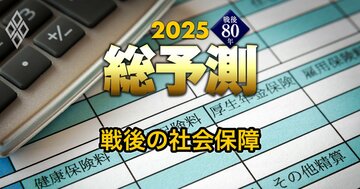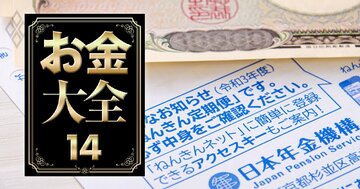Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
現在検討されている基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの適用期間の一致によって受取額はどう変わるか。特集『年金制度大改革 損↓得↑徹底検証』の#7では、日本年金機構の見込み額試算や「ねんきん定期便」では見えてこない本当の年金受取額を共働き世帯について試算した。(ダイヤモンド編集部 竹田孝洋)
年金の議論で取り上げられる
モデル世帯は現実には少ない
モデル世帯。この言葉は、財政検証や社会保障審議会年金部会の資料など公的年金を議論するときによく使われる。
これは、20歳から60歳まで40年間平均賃金で働く男性と、その間ずっと専業主婦だった女性で構成される世帯のことを指す。
所得代替率(現役世代の平均手取り賃金に対する年金給付額の水準)を議論するときもモデル世帯の年金額によるものが中心となる。
これまでの年金の議論からの継続性を考えれば、モデル世帯で検討することに意味はあるが、言うまでもなくモデル世帯のような世帯は少ない。
年金部会の委員である是枝俊悟・大和総研主任研究員は「現実の平均年金額で議論した方がよい」と語る。今回の財政検証では、平均年金額での資料も多く見られるようになった。
制度全体の議論では、平均年金額を中心にしていくことは妥当だろう。ただ、個人にとってみれば、平均金額だけでも判断しにくい。
そこで、ダイヤモンド編集部はもう一歩踏み込んで、世帯類型別、収入金額別に年金の受取額を試算した。現行制度と、現在検討されている厚生年金の報酬比例部分と基礎年金のマクロ経済スライドの適用期間を一致させた場合の受取額を比較してみた。
もちろん、試算で置く世帯の在り方の前提も全てではないが、それぞれ自分に近いパターンを参照してほしい。
今回は、共働き世帯について試算した。2023年時点で共働き世帯は1278万世帯、専業主婦世帯は517万世帯。共働き世帯数は専業主婦世帯数の2倍以上である。
「ねんきん定期便」や日本年金機構の見込み額試算で分かる受け取り額は、実際の受取額ではなく、現時点での算出基準によるものだ。
受け取り開始日までの名目賃金上昇率や物価上昇率の変動、マクロ経済スライドによる給付抑制が反映されているわけではない。
そこで、次ページでは、24年の財政検証で最も現実的なケースである「過去30年投影ケース」を前提に、上に挙げた変動要素を織り込んだ本当にもらえる年金額を試算した。