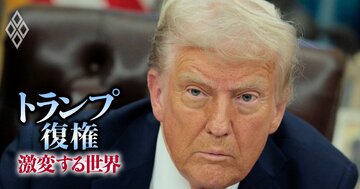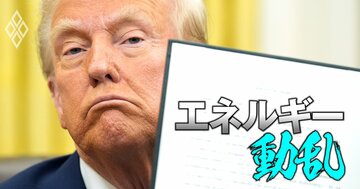Photo:Andrew Harnik/gettyimages
Photo:Andrew Harnik/gettyimages
意外だった米長期金利の低下
関税政策やDOGEが市場をにぎわせる
トランプ政権が発足し、様々な政策が打ち出されてきているが、市場はなかなか消化しきれていないのが現状であろう。
そんな中で、やや意外ともいえるのが長期金利の低下である(グラフ)。
というのも、トランプ政権の経済政策(トランポノミクス)にはインフレを促進する内容が多く含まれており、政権発足に伴って長期金利には上昇圧力がかかると予想されていたからだ。トランポノミクスの具体的な中身や方向性が固まるまでにはもう少し時間がかかりそうだが、現在の状況を簡単に整理しておこう。
トランプ政権が真っ先に取り組んでいる課題はいくつかあるが、市場に影響を与えるという点では、関税政策の発動と政府効率化省(DOGE)の動向が大きい。
関税政策はトランプ政権の看板政策の一つである。焦点となる対中国では、選挙時に「60%の追加関税」が謳われていたが、現時点では10%とやや抑えた内容にとどまっている。また、コロンビア、カナダ、メキシコ相手には関税をちらつかせて外交上の圧力をかけるやり方をとっており、関税はあくまでも外交上の交渉材料として用いられているとの見方も強い。
とはいえ、最終的にどの程度の関税が適用されるか定かではないものの、今後とも様々な局面で関税の引き上げが取りざたされ、市場を右往左往させることはまず間違いないところだろう。
関税は、言うまでもなくインフレ要因となる。ただし、1回限りの関税引き上げであれば物価への影響も一過性のものとなる。しかし、ことあるごとに少しずつ引き上げられていけば、影響は長く続く可能性が出てくる。
次に、テスラCEOのイーロン・マスクが率いるDOGE(政府効率化“省”と呼ばれているが、正式には省ではなく、外部組織である)を考えてみるが、その政策については現時点で明らかになっていない部分も多い。
ただし、全体としてインフレ促進的とされるトランポノミクスの中で、DOGEによる政府支出削減に関してはインフレ抑制効果を持つ。同時にそれは、景気に対してマイナス要因となる。
冒頭にも触れたとおり、トランプ政権発足後に米長期金利は若干の低下傾向を示している。その背景としては、インフレ要因となる関税がとりあえずは小出しになっていること、不透明要因は多いもののDOGEの動向が耳目を集めており、インフレや景気に対する一定の下押し効果が見込まれていることなどが考えられる。