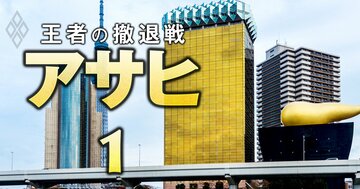介護・医療・飲食・物流・建設は人手不足
労働ミスマッチは「現状維持」志向も関係
少子化、高齢化、人口減少を背景に、わが国全体で人手不足が深刻だ。厚生労働省の『一般職業紹介状況』によると、3月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍、前月から0.02ポイント上昇した。
主な業種ごとに見ると、サービス分野で人手不足感が強い。介護や医療の分野では、労働力の供給は明らかに需要を下回っている。飲食の調理や接客、物品の販売でも人手不足だ。訪日外国人(インバウンド)の増加も、関連分野で人手不足の要因となっている。
物流や建設分野でも人手不足が深刻だ。トラックの運転手、建設躯体工事や土木作業に従事する人の絶対数が足りない。それに伴い業務の自動化・省人化につながる設備投資を行う企業も増えている。
その一方で、個社ベースで見ると過剰な人員を抱える企業が存在している。わが国の労働市場には顕著なミスマッチがあり、その要因として、労働慣行の影響は大きいだろう。
入社後は、基本的に入社の年次で昇進や給与水準が決まり、定年まで働くことが事実上保証されている。この労働慣行もあって、日本人の価値観は「現状維持」へのバイアスが強い。基本的に変化を嫌い、組織全体で事業環境の変化に対応することが難しい。
しかし近年、AI(人工知能)関連分野が急速に成長している。あるいは、トランプ関税が各国を振り回し、ロシアとウクライナによる戦争は長期化し、中東における地政学リスクも頻繁に変化する。企業が生き残るためには常に柔軟でいる必要がある。構造改革(リストラ)の心構えは欠かせない。
改革の一部として、在来事業の資産を売却し、AIなどIT先端分野に積極的に資金を投じることが挙げられる。また、国内外の企業を買収することで収益拡大に取り組む企業もある。早期退職、希望退職を募る企業が増えているのは、経営体力の余裕があるうちに割り増しの退職金を支払い、人員配置や人員数を適正化するのが狙いであり、至極当然の流れだろう。