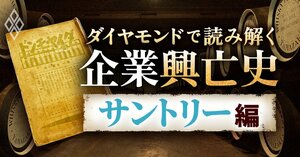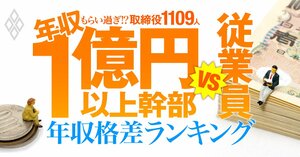足元の政策金利は46%。延々と続く通貨安で、何度も投資家を落胆させてきた“裏切り通貨”トルコリラが、いま本気で変わろうとしている。トルコ政府と中銀がタッグを組んだ「インフレ退治」の覚悟により、市場の空気は明らかに変化の兆しを見せている。2025年末に向けての政策金利や為替動向の予測を交えつつ、トルコ経済の「これから」を見極める。(投資ライター、「FXコレクティブ」主宰 高城 泰)
高金利で根強い人気の通貨・トルコリラ
インフレ、通貨安のワナはまだ続くのか
高金利通貨の代表格といえるのがトルコリラだ。トルコの政策金利は46%と他国を圧倒し、インカムゲインを求める投資家から熱い眼差しを浴びてきた。しかしトルコリラは投資家を惹きつけながら、幾度となく裏切ってきた通貨でもある。
超高金利はインフレの裏返し。トルコの消費者物価指数(CPI)は2022年のピーク時に80%(前年同月比)を超えた。
為替市場のセオリーは「インフレ通貨は売られる」。トルコリラはセオリー通りに売られてきた。過去10年の対円チャートを見ると、きれいな右肩下がりを描いている。
2025年にトルコを襲った
「2つのショック」とは
2025年3月にはトルコ当局がエルドアン大統領の政敵とされるイスタンブール市長を拘束し、トルコリラが3円台半ばまで急落する場面があった。
これまで急落するたびに「今度こそ底!」「0円にはならない!」と意気込む投資家の買いを誘いながら下げ続けてきたトルコリラだが、一方で46%の超高金利は魅力的だ。悩ましいトルコリラへの投資、どう考えるべきか。
「今年3月、4月とトルコは「2つのショック」に見舞われました」
 ムラット・ドゥラン(Murat Duran)。TEBアセットマネジメントのチーフ・エコノミスト。グローバルおよびトルコ経済の分析を担当し、同社の投資戦略、ポートフォリオの意思決定に反映させている。以前はトルコ中央銀行のエコノミストとして、金融政策の策定やマクロ経済調査を担当し、金融政策の分野で18年の経験を持つ
ムラット・ドゥラン(Murat Duran)。TEBアセットマネジメントのチーフ・エコノミスト。グローバルおよびトルコ経済の分析を担当し、同社の投資戦略、ポートフォリオの意思決定に反映させている。以前はトルコ中央銀行のエコノミストとして、金融政策の策定やマクロ経済調査を担当し、金融政策の分野で18年の経験を持つ
そう教えてくれたのはトルコ大手運用会社TEBアセットマネジメントでチーフエコノミストを務めるムラット・ドゥラン氏だ。
トルコを襲った「2つのショック」とは何か。
「ひとつは国内市場のショック、もうひとつはトランプ米大統領の関税による世界的なショックです。それでもトルコの中央銀行は市場のボラティリティが高まる中で、利下げサイクル中に政策金利を引き上げることで対応しました。インフレ抑制策で経済活動は低迷していましたが、トルコの経済チームはインフレ抑制を優先したのです。」
過去、こうしたショックがあるとトルコ政府は成長を重視し、インフレを容認してでも利下げするよう中央銀行に圧力をかけてきた。
「しかし、今回トルコ政府はインフレ抑制プログラムへの支持を繰り返し表明しました。これは非常に重要なポイントです」
トルコ政府と中央銀行による
新たな経済チームはインフレ退治に本気
政府・中銀が一体となってインフレ抑制へ乗り出している、というわけだ。過去、トルコではインフレに対して利下げで対抗するという独特な金融政策を採用していた。正統路線に転じた理由は?
「2023年の大統領・国会選挙後、シムシェキ財務相を中心とした新たな経済チームが発足しました」
シムシェキ財務相は以前、メリルリンチでストラテジストも務めた経済通だ。
「トルコ中央銀行もオーソドックスな金融政策慣行に戻り、政策金利をわずか9カ月で8.5%から50%へ引き上げました」
「財政規律を重視し、投資家との関係改善にも務めました。2025年1月には、2023年の大地震による財政支出拡大以降では初めて、税収(年率換算)が政府支出(除く利払)の伸びを上回っています」
「その結果、4月のインフレ率は38%(前年比)まで低下しています。依然として高い水準ではありますが、年末に30%、2026年末には20%強へ落ち着くと予想しています」
トルコ中銀は「為替レート安定のため
あらゆる手段を活用する」
インフレ率の上昇はトルコリラ安による輸入物価の上昇にも一因があった。中央銀行は通貨安によるインフレ退治にも本気だ。
「トルコ中銀は、為替レートが物価に与える影響が大きいことから通貨の安定を最優先としています。中銀総裁の講演、金融政策委員会の決定、インフレ報告書など各種資料でも、トルコリラの実質価値を維持することの重要性を強調しています。インフレ抑制プログラムの要である為替レートの安定を維持するため、トルコ中銀は3月と4月に多額の外貨準備を売却し、利下げサイクルの最中に政策金利を引き上げました。」
これを受けて、実際にトルコリラの実質為替レートはすでに反転上昇が始まっている。
「私は15年間トルコ中銀に勤務したエコノミストです。今回、中銀が為替レートの安定に真剣に取り組む姿勢は本物。この目標を達成するためにあらゆる手段を、躊躇なく活用するだろうと確信しています」
2023年から始まったインフレ抑制プログラムによりトルコリラはいよいよ底打ちしそうな感もある。