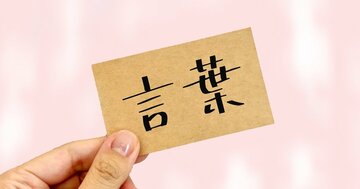聞き手の脳内関所が、脳内整理棚を準備するより早く説明を進めても、その情報は、行き先が決まっていないので、脳内関所で失われてしまいます。脳内関所では、長時間記憶を保てないからです。この状態では、せっかくの話も聞き手の脳内整理棚に届くことはありません。あなたがどんなに熱弁をふるっても、聞き手に理解されることはないのです。
分かりやすい説明のためには、聞き手の脳内関所で行われている「脳内整理棚の選定」作業には一定の時間がかかることに配慮し、そのために「待つ」あるいは「その選定作業を助けてあげる」などができなければなりません。
タイムラグは気づきにくい概念です。聞き手には、世界が、あなたと同じように見えているわけではないのです。映画館で席まで案内するのは、友人の目が暗闇に慣れるまで待ちましょう。
意図がわかりにくい
郵便物に困惑
私は帰宅すると最初に、その日配達された郵便物に目を通します。郵便物にはいわゆるダイレクトメールもたくさんあります。その中には、開封するとさまざまな印刷物がドッと出てきて、その封書で来たメール全体としての意図がなかなか分からないものがあります。
たとえばある日の電話会社からの封書は、先月分の電話代の請求書だと思って開きました。ところが出てきたのは、特別キャンペーン中のプレゼント商品を詳細に写真紹介した1枚、来月中旬のシステム工事期間中、関東地域で深夜2時から3時まで電話がつながりにくくなる旨のお知らせの1枚、来年から始まる画期的な新しいサービスの技術的な説明が1枚、……他にもいろいろな印刷物が何枚もバラバラと出てきました。
こうなると、この郵便物を送った一番の目的、すなわち「説明者の意図」が不明確です。電話会社が私に一番知らせたいのは、工事期間中に電話がつながりにくくなることなのか、新サービスに加入してもらいたいのか、あるいはキャンペーンのプレゼント商品なのか。このままではたくさんの印刷物に紛れて、その一番肝心なことが私には分かりません。
このゴチャゴチャと同封した郵便物の意図が分かりにくい理由は、最初に「理解の枠組み」を与えていないからです。これは「概要をまず話せ」という意味で、説明術の中でも基本中の基本です。