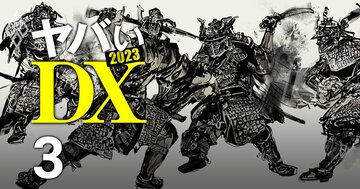Photo:artpartner-images/gettyimages
Photo:artpartner-images/gettyimages
“日本発の製造業DXの標準化”を目指して発足したEdgecrossコンソーシアム。中心にいたのは三菱電機だ。だが、理想の「つながる世界」は静かに終息した。標準化の時代は終わり、各社が“自分の庭”を耕し始めたのだ。特集『製造業DX 破壊と創造 9兆円市場の行方』の#1では、プラットフォームの転換点に迫る。(ダイヤモンド編集部 井口慎太郎)
「標準化」の理想掲げた連合軍だったが…
生成AIの登場で、潮流はエッジからクラウドへ
三菱電機やオムロンなどが幹事会社を務めた製造業IoT(モノのインターネット)プラットフォーム、Edgecross(エッジクロス)コンソーシアムがサービスを終了する。ものづくりのDX(デジタルトランスフォーメーション)における「標準化」を実現し、作業効率の改善につなげようとしていた。いわば日本企業の連合軍として発足したといえる。
サービス提供を始めた2018年は、IoTプラットフォームの普及により製造現場の効率化に革新が起きると期待されていた。ドイツでは11年に生産プロセスのデジタル化で効率化を図る「インダストリー4.0」が提唱された。独シーメンスは早くからデジタル企業の買収に着手し、基盤を整えていた。米国でも同様の動きがあった。
外資の競合に対抗できる枠組みを設けなければ、プラットフォーム市場をごっそり奪われてしまうのではないか――。当時はそんな焦りもあった。
ダイヤモンド編集部は昨年12月、エッジクロスコンソーシアムが終了することを報じた(詳細は『【スクープ】三菱電機、日立、NEC、オムロンなどが主導したIoTプラットフォーム「エッジクロスコンソーシアム」が終了へ!』参照)。
エッジクロスコンソーシアム事務局は今年1月にサービス終了を正式発表。理由について、次のように説明した。「DX化が加速する環境においては、エッジ上での価値提供から、製造業のバリューチェーン全体に貢献するアプリケーションへのニーズが高まってきております。このような変化を受け、生産現場のオープンなIoT化を推進するという当初の目的は十分に果たしたと判断しました」。
生産現場ではさまざまなファクトリーオートメーション(FA)機器が稼働している。通信プロトコルはメーカーごとに異なるため、ひとまとめにITシステムにつなげる際の障壁になっていた。そこで、エッジクロスコンソーシアムのソフトウエアを介することで現場と全体のシステムが統合できるようになる。
規格が異なるデバイスをひとまとめにする“架け橋”の役割を担えるのが強みだったのだ。通常のPCで利用でき、特殊なハードウエアを必要としないことも導入のハードルを下げた。利用料金も売り切りで9万円から。ソフトを追加しても20万円未満と実に手頃だ。顧客の多くは中小企業だったが、費用面での負担は軽かった。
では、なぜ製造業DXで主役になれなかったのか。まず、事務局が言及した「バリューチェーン全体への貢献」が求められるようになった時代の変化がある。製造現場に特化したエッジクロスコンソーシアムは、この新たなニーズに対応し切れなかった。さらに、標準化を目指したものの会員の裾野を広げ切れなかった側面もあった。では、新たに覇権を握りそうなのはどの製造業DXプラットフォームなのか。生成AIは製造現場をどのように変えるのか。創造と破壊の後に隆盛する「第2世代DX」とは。次ページで詳報する。