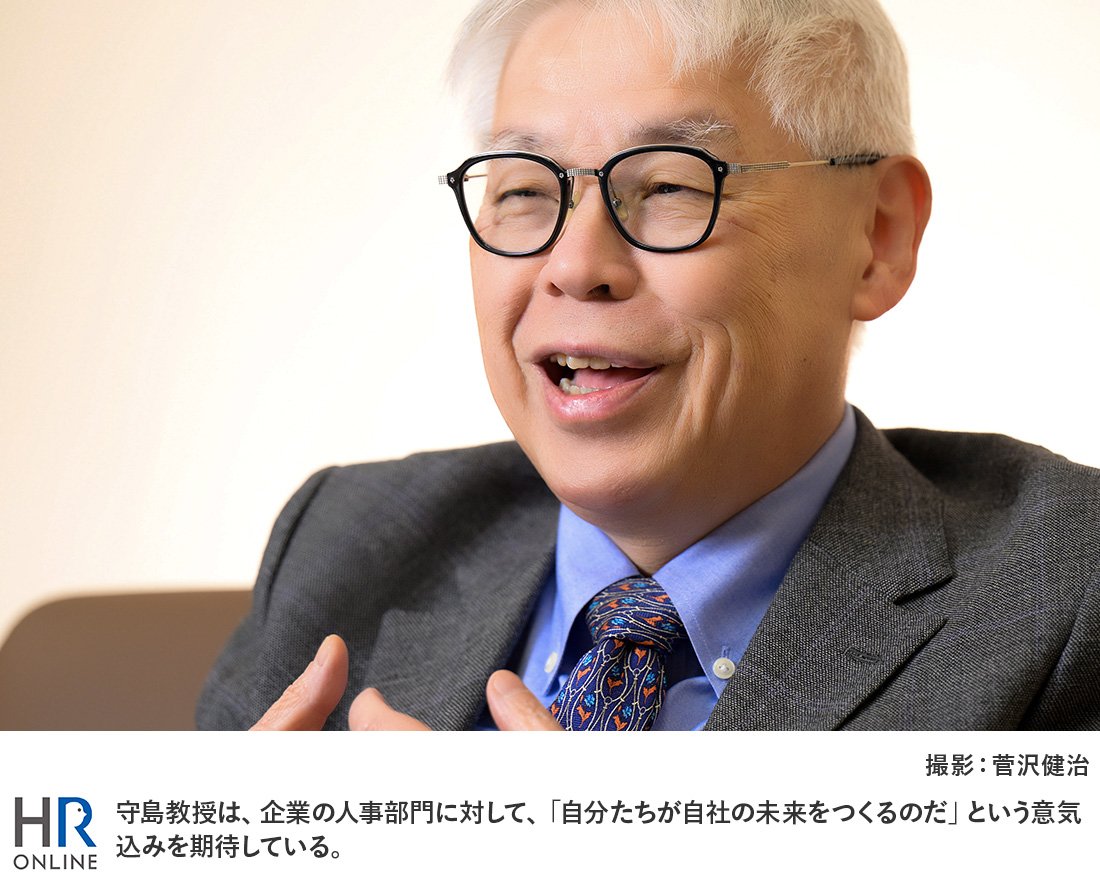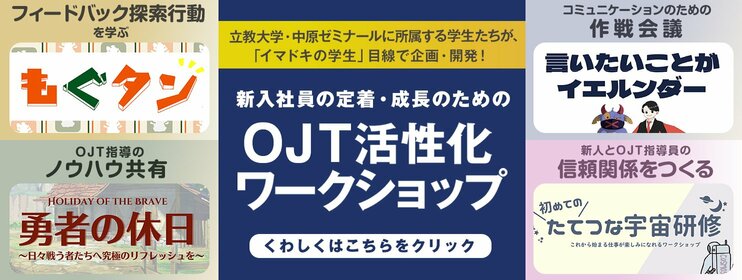「キャリア自律」に不可欠な「仕事自律」と「学習自律」
では、一般的なビジネスパーソンが「キャリア自律」を実践するにあたって、どうしていけばいいのだろう? 最初の一歩は、どこにあるのか?
守島 まず、「キャリア自律」という概念を分解するのがよいと、私は考えます。
分解して現れるひとつは、「仕事自律」です。上司から仕事を渡されたとき、「私はこう進めようと思います」と自分なりの方法論を提示し、そのための情報や人脈といったリソースも自分で調達し、結果を出す。それが「仕事自律」です。
もうひとつは、「学習自律」です。これは、業務遂行にあたって不足している知識やスキルを見極め、自主的にフォローアップしていくというものです。例えば、リーダーシップについて学ぶ必要があるのであれば、関連する書籍を読んだり、セミナーに参加したり、ロールモデルに教えを請うたりするのです。
「キャリア自律」はハイレベルな複合概念であり、「仕事自律」と「学習自律」をベースとした層構造になっています。ベースができていないのに、上のところだけを取り組んでもうまくいかないのは当然です。
その点、欧米では、子どもの頃から、「社会に出て、何をやりたいのか?」というように、キャリアについて考えさせる授業が繰り返し行われています。企業における業務の渡し方も、ホワイトカラーはジョブ型雇用を前提に成果目標を与え、そのあとは任せるやり方です。日本ではそうした習慣が少なく、特に、企業に入社後は、個人の自由な選択を抑え、会社の指示命令に従うことを良しとしてきたので、キャリア自律があまり浸透しなかったのでしょう。
いつの時代も、人事部門の役割は、企業として必要とする人材を確保し、組織を整え、「全員戦力化」を図ることである。人事制度としての「ジョブ型雇用」も、社員のマインドセットやスキルとしての「キャリア自律」も、そのための手段といえる。
最後に、守島教授に、“新たな「全員戦力化」”に向けた、人事部門の役割を尋ねた。
守島 かつて、人事部門の役割は、採用や配置転換、給与計算、勤怠管理など、人材と人事制度の管理でした。これからはそうではなく、経営戦略を実現するための“人と組織に関する司令塔”になるべきです。
例えば、企業が事業内容やビジネスモデルを根本的に変えるとなったとき、人材の採用にも育成にも非連続な変更が必要になります。経営層と連携しながら、社内のしがらみにとらわれず、人事部門として主体的に意思決定をしなければなりません。それができないと、戦略と人材のミスマッチが拡大し、経営危機にもつながりかねないでしょう。
また、働く人たちが自社のために人的資本を投資し、貢献したいと思うような環境を整えることも重要です。具体的な施策としては、自社の現状と課題に応じて、そこにフォーカスすることで得られる利点を説明し、そのためのメニューを提供していくことが重要です。
さらにいえば、次世代のトップリーダーをつくるのも人事部門の役割です。これまで、日本企業では、事業部門で揉まれて結果を出した管理職が昇進し、経営層に上がるのが一般的でした。しかし、それでは全体を俯瞰して経営判断できるトップリーダーは生まれにくい。これからは、事業部門で揉まれる前の、30代くらいの人材を対象にアセスメントを行い、リーダー候補を選んで育成するやり方に切り替えるべきです。それを人事部門が経営層と一緒になって行うのです。
課題は多岐にわたりますが、「自分たちが、人材と組織を通して、自社の未来をつくるのだ」という意気込みで、人事部門が活躍していくことを、私は期待しています。