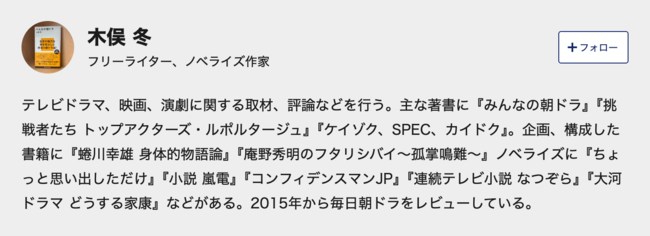「あいつの絵や物語は人の心を動かす」と言いながら八木は厳しい顔になり、浮浪児の盗みは生きる術として染み付いたものだと、「きれいごとでは何も解決しない」とのぶに語る。
つまり、嵩が漫画を描くことで生き残れたように、浮浪児は盗みを働いている。逆をいえば、子どもたちに盗みではない生きる術を身に着けさせる必要があるということだ。
それでものぶは浮浪児と向き合おうとする。誰かがハーモニカで吹いている「荒城の月」が物悲しい。
「リンゴの唄」など戦後を明るくさせる唄もある一方で、このように無情の哀切を歌った唄も流れている。それが戦後なのだろう。焼け跡の虚しさ、そこで歯を食いしばって生きていく人々。
警察に追われるアキラを親戚の子を預かっているのだと毅然とかばうときののぶの瞳は権力に動じない強さを放っていた。これまでずっと目が揺らいでいたのぶが、ついに強い意思を放ちはじめている。こういうときの今田美桜はとても輝く。
雑誌の表紙は「母に似ている」と言わせる創作の力とは
警察は浮浪児を捕まえては施設に送る。それを「狩り込み」という。「狩り込み」は同じ朝ドラの『なつぞら』(19年度前期)や『虎に翼』(24年度前期)にも出てきた。
浮浪児のなかには話すことを持たない(持てない)子もいるが、アキラのように心を開く子もいる。のぶは辛抱強く、浮浪児たちと接して彼らを救う手立てを思いつくことができるだろうか。
アキラは『月刊くじら』の表紙の女性が母親に似ている気がすると言い、でものぶにも似ていると言う。誰もがのぶに似ているという嵩の絵。ひとりの女性への強烈な思慕が、アキラのように母の思い出と重なる。おそらくそれが創作の力というものなのだ。
のぶのもとに蘭子からのはがきが届く。そこには『月刊くじら』の最新号の編集後記に、のぶのお別れの言葉が載っていると記してあった。
高知新聞から出ている書籍『やなせたかし はじまりの物語:最愛の妻 暢さんとの歩み』にのぶのモデルである小松暢さんの書いた編集後記が載っている。これはドラマでは引用されないのだろうか。
嵩のモデル・やなせたかしが月刊高知で書いた漫画はふんだんに引用されているが、小松暢さんの文章は引用されない。主人公はのぶなのになぜ。