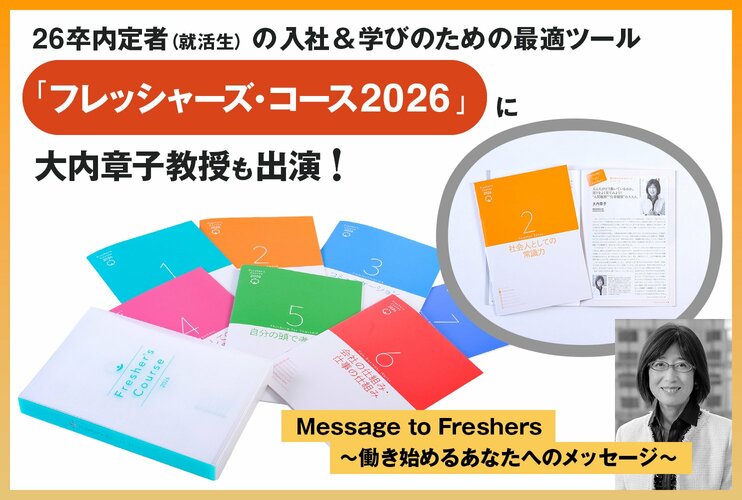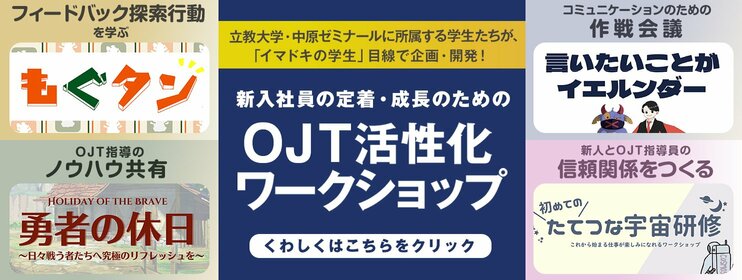「見かけの数字」ではない、長期的な視点での人材育成を
2015年に成立した女性活躍推進法は、10年間の期限付きで制定された時限立法だ。働く女性の個性と能力が十分に発揮される社会の実現を目的に掲げ、事業主に対し、女性活躍の状況把握や行動計画の策定、情報の公開を義務付けている。当初は2026年3月を期限としていたが、「いまだ、その役割を終えたといえる状況にない」として、2036年3月まで10年延長される見込みだ。女性活躍推進を阻んでいるものは何なのか。
大内 課題はいろいろありますが、最大の壁になっているのは、やはり、性別役割分業意識に根ざした「管理職のバイアス」だと思います。スキルアップやキャリアアップにつながるような仕事は男性社員に任せ、女性には「細かい作業が得意だろう」という思い込みで補助的な仕事を与える。女性に男性と同じような仕事を任せているような場合でも、出産後はスキルアップ・キャリアアップにつながる仕事から外す。こういった人材育成では、キャリア格差を広げるだけでなく、賃金格差も助長されてしまいます。
「女性は昇進意欲が低い」ともいわれがちですが、私は昇進意欲を育てるのは職場の環境だと思っています。学びや成長の機会がなければ、自己効力感も高まりませんから、昇進意欲を持ちようがないのではないでしょうか。女性活躍の第一歩は、管理職がジェンダーバイアスを排し、個人の能力を正当に評価して、育成に取り組むことだと考えています。
政府は、2030年までに女性役員の比率を30%以上にする「203030」という目標を掲げているが、現場の実情はどうだろうか。
大内 数値目標をいくら設定しても、それが「見かけの数字」になってしまっては意味がありません。管理職の女性比率を上げるために、意思決定に関わらない「担当課長」のような肩書だけを与えているケースも多く、これでは本質的な女性活躍にはつながらないでしょう。
また、女性役員の多くが社外取締役である実態も指摘されています。外部から登用すれば数値目標はクリアできますが、社内での育成と登用が伴わなければ、本質的な変化は起きないでしょう。育成には時間がかかりますが、10年後の女性幹部候補を育てるつもりで本気で取り組まないと、企業の将来は見えません。
女性リーダーを育成するには、社内の研修やキャリアアップ制度などに加えて、ビジネススクール(社会人大学院)や大学のリカレント教育を活用するなど、多様で手厚い支援をしていくべきです。特に、管理職を目指す女性には、必要なスキルを身につけるだけでなく、いままで得られにくかった現場経験を通じて自信を深めるような機会を提供することが欠かせません。実践的な経験を積む場を設けることで、彼女たちの昇進意欲を喚起できるでしょう。
また、女性ならではの視点や意見を尊重し、企業の意思決定に反映させる仕組みを整えることも、ダイバーシティ促進のためには不可欠です。企業が、「ダイバーシティ促進」という課題に本気で向き合うことが、長期的な視点での人材育成と組織の持続的成長につながるでしょう。
人口が減少していくこれからの時代は、「男性だから」「女性だから」といった先入観を捨て、誰もが成長できるように育てていく組織の姿勢が求められます。適切に育成された人材は、必ずや、企業の戦力になってくれます。ただの「働きやすさ」だけでなく、「働きがい」を重視した環境づくりこそが、人材の定着やモチベーション維持の鍵を握るのです。いまこそ、「選ばれる企業」となるために、多様な人材の育成と活躍の推進に向けて本気で取り組むときです。