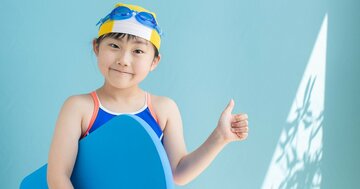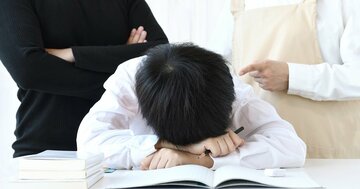これは、赤ちゃんの援助行動が他者に褒められるために行われているわけではないことを意味しています。また、瞳孔の変化を測定した別の研究では、2歳児は困っている人が助けを受けられない場合に覚醒状態が高まり、自分や他者がその人を助けることができると覚醒状態が抑えられることがわかっています(注2)。
赤ちゃんの援助行動は、自分の評判や褒められることを基盤にしているのではなく、純粋な他者への思いやりや心配から生じていると考えられます。
5歳頃になると他人の視線と
自分の評価が気になり始める
5歳頃になると、子どもは自分の評判を気にするようになり、他者に見られているときには自分を良く見せようと行動を変えるようになります(注3)。このような評判操作を調べるために、「独裁者ゲーム」という実験がよく用いられます。
このゲームでは、子どもにとって魅力的なお菓子やシールなどが、実験者から子どもに渡されます。そして、子どもはそれらをその場にいない他者と分けるように求められます。分ける相手は子どもの知らない人物で、今後も顔を合わせることはないという設定です。子どもは、すべて自分のものにしてもよいし、一部を取り、残りを相手に渡しても構いません。
独裁者ゲームでは、分配を決める立場になった場合、相手に何も渡さずすべて自分のものにするのが合理的な行動です。相手は知らない人物であり、今後も顔を合わせることがないため、文句を言われることもありません。
実験では、子どもにシールが渡され、それをどのように分けるかが調べられました。このとき、観察者が見ている場面と、誰も見ていない場面を設定し、子どもの分配行動を比較しました。
その結果、5歳児は、観察者に行動を見られているときに、他の子どもにシールを多く分ける利他的な行動をとりました。観察者に見られている場面では、子どもは自分の評判を意識し、他者に配慮した利他的な行動をとる傾向が強くなったと考えられます。また、他人のものを盗むといった良くない行動を控えることも確認されました。