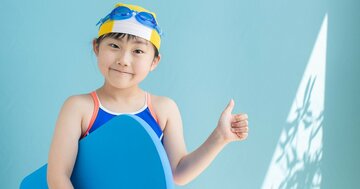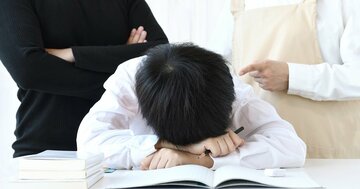取ったシールの枚数は、大人に観察されている場合には平均0.7枚、目のイラストが掲示されている場合は2.9枚、観察者なしの場合は4.4枚でした。大人に観察されていると、シールを取る行動はほとんど見せず、1枚も取らなかった子どもの割合は67%にのぼりました。
一方で、観察者がいない場合には、この割合が13%と大幅に減少しました。目のイラストが掲示されている場合には、観察者なしの場合よりシールを取る行動は少なくなったものの、統計的に有意な違いは確認されませんでした。
この結果から、5歳児は観察者がいるときには、他者のシールを取る行動を控えることが示されましたが、目のイラストではその効果はみられませんでした。大人の研究結果とは異なり、5歳児には「目」の効果が現れなかったのです。
「目の効果」は工夫一つで
子どもにも効く可能性がある
5歳児で目の効果がみられなかった理由として、子どもは大人ほど自分の評判を気にしないことが挙げられます。目のイラストだけでは、子どもは誰かに評価されているという感覚を持ちにくいと考えられます。
また、目のイラストからは直接的な賞賛や罰といった反応が得られないため、子どもは見られているという感覚がなく、行動を調整しなかったと推測されます。
一方で、別の研究では、「目は見るためのものだよね」などと実験者が目の機能について話をした後に分配課題を実施すると、目のイラストの前でも他者に分け与える行動が増えることが報告されています。
この結果は、目について考えたことで、子どもが目のイラストに対して見られているかもしれないと意識するようになり、道徳的な行動が引き出されたと解釈されています。
このように、子どもにおける目の効果は、状況や文脈によって変わります。その仕組みをさらに明らかにすることで、教育や日常生活の中で効果的に活用できる可能性があります。
「褒め言葉」次第で
行動が180度変わる
子どもへの褒め言葉は、子どもに道徳的な行動を促すことがわかっています。