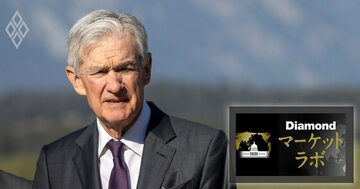Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
米国の利下げと日銀の緩やかな利上げで日米金利差の縮小が見込まれる。長期的には購買力平価(PPP)が為替の基準を示し、円高方向への修正余地は大きい。経常収支構造、投資資金フローの変化で趨勢的なドル高シフトはあるものの、26年にかけて1ドル130円前後への円高が予想される。(龍谷大学名誉教授 竹中正治)
長期ではインフレ率格差が
為替相場を決める
米国の雇用統計の下方修正と8月下旬のジャクソンホール会議でのパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げの可能性を示唆するスピーチを受けて、FRBが年内に利下げに動く可能性が濃くなった。一方、日銀の動きはスローながらも年内に0.25%の利上げの可能性が高い。
年明け以降の米国の金融政策は、トランプ政権の利下げ要求の意を受けたFRB理事への交代、さらにパウエル議長の任期満了による交代(2026年5月)を考えると、関税引き上げによる物価上昇圧力にある程度目をつぶってでも、さらなる利下げに向かう可能性が高い。一方、日銀は26年も穏やかな利上げ(金融政策の正常化)プロセスをたどるだろう。
20年以降のドル円相場は、過去四半世紀をさかのぼってみても日米金利格差の変化に最も強く反応する傾向が続いている。来年に向けて日米金利格差の縮小を前提にすると1ドル130円前後までの円高・ドル安への揺り戻しの可能性が高いと筆者は予想している。今回はこの点を解説しよう。
通貨は商品の価格を表示するのだが、逆に通貨の価値とは何か。通貨の価値とは、その通貨1単位でどれだけの商品を買えるかだといえる。これを通貨の「購買力」という。
例えば10年前から現在までに、米国の物価は1.5倍になったが、日本の物価は1.2倍にとどまったとしよう。10年前の相場が1ドル=120円の場合、仮に今の相場が1ドル=96円(=120×1.2/1.5)だと、ドル円相場は日米の物価上昇率格差(インフレ率格差)をちょうど反映して、その分だけドル安・円高になったことになる。
ところが実際の為替相場が1ドル=140円台なので、日本人は米国に旅行すると「物価が高い」と感じ、逆に米国人は日本では「物価が安い」と感じるわけだ。
過去のある時点を起点に、その後のある時点までの2国間のインフレ率の格差をちょうど反映した為替相場の理論値を「相対的購買力平価」と呼んでいる。「相対的購買力平価」という表記は長いので以下では英語表記の略でPPP(purchasing power parity)と記載しよう。
筆者が昔チーフエコノミストとして勤務していた(公益財団法人)国際通貨研究所のサイトでは、ドル円、ユーロドル、ユーロ円の3つの為替相場とそれぞれのPPPをグラフで開示しているので、ご覧になっていただきたい。
次ページではPPPと実際の為替レートとの乖離、日米金利差を基に来年に向けたドル円相場動向を分析する。