
竹中正治
日本の所得格差はこの30年で拡大したという通説に対し、厚労省「所得再分配調査報告書」を基に検証すると、税・社会保障の調整と世帯人数補正を行う「等価再分配所得」では格差はほぼ拡大していない。増加したのは高齢者世帯の比率という構造要因だ。一方で相対的貧困率や資産格差には別の動きも見える。

米国を中心に多くの国でAI関連の株価は高騰し、「第二のITバブル」との懸念が強まっている。一方で、ITバブル時の株価急騰企業の多くが赤字だったのに対し、AI関連企業が利益を計上していることを背景に「今回は違う」との楽観も根強い。バブルのピークや崩壊時期を正確に当てることは不可能だが、資産配分とリバランスを通じて暴落リスクに備え、長期リターンを高める道は個人投資家にも開かれている。

東京都心のマンション高騰は、超高額価格物件では投機色が強まり調整余地がある。一方、ファミリー層向けの物件の上昇は賃料の期待上昇、実質低金利、需給逼迫(ひっぱく)と建設費上昇に支えられている。当面は大幅に価格が下落するとは考えにくい。

米国の利下げと日銀の緩やかな利上げで日米金利差の縮小が見込まれる。長期的には購買力平価(PPP)が為替の基準を示し、円高方向への修正余地は大きい。経常収支構造、投資資金フローの変化で趨勢的なドル高シフトはあるものの、26年にかけて1ドル130円前後への円高が予想される。

参議院選挙での与党敗北による政局不安をよそに、日経平均株価は米国との関税交渉合意を受けて4万円台に突入した。TOPIX(東証株価指数)も史上最高値を更新した。中長期ではアベノミクス以降の株価上昇トレンドが継続しており、2028年に日経平均が5万円を突破する可能性もある。そのけん引役はインフレ率とROE、そして売上高利益率の持続的向上だ。
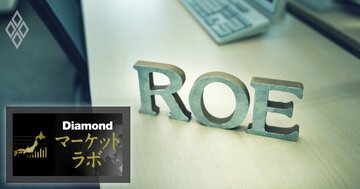
日本経済は「需要不足」から「供給制約」へと局面を変えている。輸入物価上昇から始まったインフレは内生化し、物価上昇が3年にわたり2%超を維持し、建築費や米価の急騰が日常を揺るがしている。インフレ期待の高まりや人手不足など内生的要因が物価に与える影響を考察し、金融政策や財政政策の再構築が迫られている現状を分析する。

トランプ大統領による相互関税発動で、世界の株価は暴落し、金融市場の動揺は続いている。中長期の投資家にとっては、買い場を探る好機でもある。相場の急変動時に上昇するVIX指数、別名恐怖指数を使った買い時のタイミングの測り方を紹介する。

トランプ政権の関税外交に振り回され、日米の株価は調整し始めた。割高な米国株の比率を落とし米国債を買いますことはリスクを低減させる一法だ。では、日本株のリスクを軽減するにはどうしたらよいのか。割安圏に放置されているJ-REIT(上場不動産投資信託)をポートフォリオに加えることは有効な手段の一つだろう。

投資成績はリターンだけでなくリスクとのバランスが重要です。新NISAで米株偏重の投資家が取るべきリスク分散策とは?

前回の「トランプ1.0」と今回の「トランプ2.0」では、米国の景気循環ステージが異なる。公約の通り減税と関税引き上げが加わればインフレ再加速の可能性が高い。2026年の中間選挙に大きな影響を与えることになりそうだ。

9月の自民党総裁選のさなか、日本の財政健全性を巡って波紋を呼んだ高市早苗氏の「G7で2番目」発言。財務省資料では様相は全く異なる。いったいどういうわけだろうか?

円高方向への相場修正を受けて、日本株の先行きを案じる声が高まっています。しかし今回は、過去の暗い局面とは異なりそうです。その根拠とは?

日本でもインフレ率の底上げに伴って、10年前にピケティが説いた「r(資本収益率)>g(経済成長率)」の原理が一段と際立ってきました。中間所得層がとるべき選択肢とは?

過去20数年も継続した物価も賃金(ベースアップ)も前年比ほぼゼロという日本のノルム(社会的な習慣)はなぜ壊れたのか。「期待インフレ率」の底上げが起こったのだと考えれば辻褄が合う。

株高を背景に、新NISAも順調に投資資金の受け皿となっているようです。今後20年で預貯金偏重だった日本の家計資産は本当に変わるのか。一定の想定のもと、大胆にシミュレーションしました。

日経平均が高値を更新する中、「失われた30年の終焉」などといった論説が飛び交っている。しかし、同指数はそもそも算出の合理性に問題がある上に、バブル期の「蜃気楼相場」を起点として見ること自体が無意味なことだ。

日本株の上昇基調とは対照的に低迷が続くJ-REIT(国内不動産投資信託)市場。この状況は、逆張りで買って将来報われる投資チャンスを意味するのだろうか。

米国が次の景気後退に入るタイミングは来年の可能性が高いが、日本経済と株価に対する負のインパクトはさほど深刻にならないだろうと筆者は分析する。その根拠とは?

足元では反落しているものの、年初来では上昇基調にある日本の銀行株。長短金利差拡大とROE向上をどこまで織り込んでいるのか?さらなる上振れシナリオの条件を探った。

来年1月から始まる新NISAが話題になっていますが、個人投資家は本当に効率的な資産形成を実現できるのでしょうか。3つのNG行動を解説します。
